2007年10月30日
71 マンション管理組合の監事、機能しているか?
一般的に管理組合には、居住する組合員のうちから役員として理事長、副理事長、理事と共に「監事」が総会で選任されることになっています。
法人化された管理組合では監事は必ず置かなければいけませんが、一般の管理組合でも組合の公正な業務遂行のために通常は設置しています。
監事の仕事は非常に重要な役割を担っています。 管理組合の財産状況や理事の業務状況を監視することです。理事の業務が適正に行われているかどうかをチェックします。
監事は、理事会にも出席し、適正な業務が行われているかを確認し、意見を述べることも出来ます。
また、会計業務のチェックを行い、総会で報告することになっています。
監事は、理事の仕事に問題点を見つけたときには臨時総会を招集する権限が与えられています。
監事は、理事の業務のチェックが仕事ですから理事と兼任することは出来ません。
他の役員と同じように監事も、組合員が持ち回りで引き受けていることが多いので、厳密にその役割を実行できる人は少ないと思われます。
現実には、管理会社が作成した「監査報告書」に印鑑を押し、形式的にお墨付きを与えるだけの役割で済ましていることが多いようです。
監事には、管理組合の業務に精通した知識や経験を持つ組合員を選任するのが理想ですが、現実にはそのような人はあまりいないでしょうから、外部の専門家に依頼することも考えなければ、その機能を十分に果たすことは出来ないでしょう。
管理会社に依存するだけの体質から、真に管理組合が主体的に運営できる状態に変えていくためにも、又、管理組合の業務のチェックのためにも、外部の信頼できるマンション管理の専門家に監査業務を依頼することを話し合ってみてはどうでしょう。
防衛省の前事務次官の証人喚問。ストレス解消に倫理規定違反を承知でのゴルフ接待漬け、その姿や哀れ。
法人化された管理組合では監事は必ず置かなければいけませんが、一般の管理組合でも組合の公正な業務遂行のために通常は設置しています。
監事の仕事は非常に重要な役割を担っています。 管理組合の財産状況や理事の業務状況を監視することです。理事の業務が適正に行われているかどうかをチェックします。
監事は、理事会にも出席し、適正な業務が行われているかを確認し、意見を述べることも出来ます。
また、会計業務のチェックを行い、総会で報告することになっています。
監事は、理事の仕事に問題点を見つけたときには臨時総会を招集する権限が与えられています。
監事は、理事の業務のチェックが仕事ですから理事と兼任することは出来ません。
他の役員と同じように監事も、組合員が持ち回りで引き受けていることが多いので、厳密にその役割を実行できる人は少ないと思われます。
現実には、管理会社が作成した「監査報告書」に印鑑を押し、形式的にお墨付きを与えるだけの役割で済ましていることが多いようです。
監事には、管理組合の業務に精通した知識や経験を持つ組合員を選任するのが理想ですが、現実にはそのような人はあまりいないでしょうから、外部の専門家に依頼することも考えなければ、その機能を十分に果たすことは出来ないでしょう。
管理会社に依存するだけの体質から、真に管理組合が主体的に運営できる状態に変えていくためにも、又、管理組合の業務のチェックのためにも、外部の信頼できるマンション管理の専門家に監査業務を依頼することを話し合ってみてはどうでしょう。
防衛省の前事務次官の証人喚問。ストレス解消に倫理規定違反を承知でのゴルフ接待漬け、その姿や哀れ。
Posted by haru at
07:51
│Comments(0)
2007年10月29日
70 マンションの集会室、有効に活用されているか?
戸数が20戸以下のマンションにはあまりないようですが、50戸以上のマンションになりますと、集会室と呼ばれる場所が設けられています。規模としては戸数の3割前後の人数が収容出来る程度が多いようです。
大規模な団地型マンションでは別棟として集会所を含む管理棟として設けられています。又、キッチンを設けて料理教室が出来るような集会所のあるマンションもあるようです。
多くのマンションでは、集会室(所)の管理や使用に関して、必要な事項を定めた「集会室使用細則」がつくられていますが、その使用目的は、一般的には次のような用途に限定して、政治活動、宗教活動、営利活動等は禁止しています。
1) 居住者やその親族の葬儀等
2) 管理組合の理事会や専門委員会の会議や総会等
3) 公的機関が行う説明会等
4) 居住者の福利や親睦を目的とした交流活動や集会等
子育てサークルや趣味のサークル活動等積極的に活用しているマンションもあるようですが、使用時間の制限や管理のわずらわしさ等であまり利用されていないようです。せいぜい、月に一度の理事会か、年に一度の実出席率の低い総会に使用するくらいのマンションもあります。
総会の開催は7割以上のマンションが近くの公民館等の公共施設を利用しているようです。
最近では集会室の有効利用を積極的に考えようという動きがあります。老人介護サービスや子育て支援のの拠点としたり、住宅街のマンションでは公的施設の一つとして自治体から助成を受けて、町内会等の集会所としての利用が考えられています。
古いマンションで集会室のないところでは、わざわざ空き住戸を管理組合で購入したり、賃借しているようです。
集会室を外部の人に有料で貸し出し、その収入を管理費に充当する考えもありますが、居住者の利用を優先しないと新たなトラブルの発生となる可能性がありますので、その場合は、慎重に居住者の合意を得ることが必要です。
集会室もマンション所有者が共有している大切な財産です。貴方のお住まいのマンションではどのように使われていますか。
ゴルフのシニアツアーで65歳の青木功が優勝。10代から60代までこのスポーツの活躍の年齢幅は広い。
大規模な団地型マンションでは別棟として集会所を含む管理棟として設けられています。又、キッチンを設けて料理教室が出来るような集会所のあるマンションもあるようです。
多くのマンションでは、集会室(所)の管理や使用に関して、必要な事項を定めた「集会室使用細則」がつくられていますが、その使用目的は、一般的には次のような用途に限定して、政治活動、宗教活動、営利活動等は禁止しています。
1) 居住者やその親族の葬儀等
2) 管理組合の理事会や専門委員会の会議や総会等
3) 公的機関が行う説明会等
4) 居住者の福利や親睦を目的とした交流活動や集会等
子育てサークルや趣味のサークル活動等積極的に活用しているマンションもあるようですが、使用時間の制限や管理のわずらわしさ等であまり利用されていないようです。せいぜい、月に一度の理事会か、年に一度の実出席率の低い総会に使用するくらいのマンションもあります。
総会の開催は7割以上のマンションが近くの公民館等の公共施設を利用しているようです。
最近では集会室の有効利用を積極的に考えようという動きがあります。老人介護サービスや子育て支援のの拠点としたり、住宅街のマンションでは公的施設の一つとして自治体から助成を受けて、町内会等の集会所としての利用が考えられています。
古いマンションで集会室のないところでは、わざわざ空き住戸を管理組合で購入したり、賃借しているようです。
集会室を外部の人に有料で貸し出し、その収入を管理費に充当する考えもありますが、居住者の利用を優先しないと新たなトラブルの発生となる可能性がありますので、その場合は、慎重に居住者の合意を得ることが必要です。
集会室もマンション所有者が共有している大切な財産です。貴方のお住まいのマンションではどのように使われていますか。
ゴルフのシニアツアーで65歳の青木功が優勝。10代から60代までこのスポーツの活躍の年齢幅は広い。
Posted by haru at
07:53
│Comments(0)
2007年10月26日
69 マンションの最新設備、誰が維持管理するのか? その2
最近のマンションの設備で人気の高いのがキッチンのディスポーザーです。
ディスポーザーとは、キッチンの排水設備に設置する生ゴミ処理機のことです。モーターと生ゴミ破砕用の金具がセットになって、生ゴミを破砕し、水道の流水で押し流すようになっています。
基準が異なる為、各自治体で対応が違うようですが、下水に流入する有機廃棄物を処理するディスポーザーに対応した浄化槽・浄水設備が必要となります。
大変便利なことから新しいマンションでは標準装備として急速な普及をしています。しかし、排水管が詰まるとか、悪臭がするとか虫が発生するとかの苦情が増えているようです。
原因は、投入してはいけない生ゴミにもあるようですが、ディスポーザーの使用に適した配管設計や維持管理に適した配管清掃口の設置等が不十分であることのようです。
マンション購入者には確認の出来ない隠蔽部分においての設計や施工監理の配慮不足です。
マンションを完成させるには事業主(売主)と売主のニーズを具体的に表現し、工事を監理する設計者それに設計意図を形にする建設会社の存在が必要です。同じ会社で全てのことをする場合もありますが、一般的にはそれぞれが別々の会社で実施されています。
マンション購入者は、マンションの売主や建設会社のネームバリューには関心を持っています。しかし、マンション全体の品質をコントロールしているのは専門家として設計・監理をする設計事務所等ですが、その重要性については、あまり知られていないようです。
たとえば、耐震偽装をした構造事務所の不正を見抜けなかった元請けである設計事務所等はその役割を果たしていないといえるでしょう。
先日も、「全戸天然温泉付のマンションから多量のレジオネラ菌が検出され給湯を中止せざるを得なくなった」と報じられていますが、設計担当者が計画段階でどこまでの安全性を配慮していたのでしょうか。
マンションの最新設備をマンション購入者が安心して長期にわたり維持管理するためには、機器設置に伴う配管・配線や機器の取替えのし易さ等にも配慮した設計・監理をする会社(設計事務所)の役割は重要です。
大阪府和泉市の公園で秋のコスモスと夏のヒマワリが咲き競っているそうです。これも本当に地球温暖化のせいでしょうか。
ディスポーザーとは、キッチンの排水設備に設置する生ゴミ処理機のことです。モーターと生ゴミ破砕用の金具がセットになって、生ゴミを破砕し、水道の流水で押し流すようになっています。
基準が異なる為、各自治体で対応が違うようですが、下水に流入する有機廃棄物を処理するディスポーザーに対応した浄化槽・浄水設備が必要となります。
大変便利なことから新しいマンションでは標準装備として急速な普及をしています。しかし、排水管が詰まるとか、悪臭がするとか虫が発生するとかの苦情が増えているようです。
原因は、投入してはいけない生ゴミにもあるようですが、ディスポーザーの使用に適した配管設計や維持管理に適した配管清掃口の設置等が不十分であることのようです。
マンション購入者には確認の出来ない隠蔽部分においての設計や施工監理の配慮不足です。
マンションを完成させるには事業主(売主)と売主のニーズを具体的に表現し、工事を監理する設計者それに設計意図を形にする建設会社の存在が必要です。同じ会社で全てのことをする場合もありますが、一般的にはそれぞれが別々の会社で実施されています。
マンション購入者は、マンションの売主や建設会社のネームバリューには関心を持っています。しかし、マンション全体の品質をコントロールしているのは専門家として設計・監理をする設計事務所等ですが、その重要性については、あまり知られていないようです。
たとえば、耐震偽装をした構造事務所の不正を見抜けなかった元請けである設計事務所等はその役割を果たしていないといえるでしょう。
先日も、「全戸天然温泉付のマンションから多量のレジオネラ菌が検出され給湯を中止せざるを得なくなった」と報じられていますが、設計担当者が計画段階でどこまでの安全性を配慮していたのでしょうか。
マンションの最新設備をマンション購入者が安心して長期にわたり維持管理するためには、機器設置に伴う配管・配線や機器の取替えのし易さ等にも配慮した設計・監理をする会社(設計事務所)の役割は重要です。
大阪府和泉市の公園で秋のコスモスと夏のヒマワリが咲き競っているそうです。これも本当に地球温暖化のせいでしょうか。
Posted by haru at
08:50
│Comments(0)
2007年10月25日
68 マンションの最新設備、誰が維持管理するのか? その1
最近のマンションは、最新設備が豊富で各デベロッパー(マンション販売業者)が競うように宣伝しています。たとえば次のような設備です。
☆ 居室の床に埋め込まれた、人に優しい快適な床暖房設備。
☆ 室内の汚れた空気の入れ替え、カビや結露の発生を抑える24時間換気システム。
☆ キッチンで発生する生ゴミをスイッチ一つで流し台の排水口で処理できるディスポーザー。
☆ 食器と洗剤を入れてスイッチを押せば、乾燥までしてくれる食器洗浄乾燥機。
☆ 手入れのしやすさと安全性の高いIHクッキングヒーター。
☆ 洗濯物干しやカビ防止、冬の暖房に浴室乾燥機と全自動のフルオートバス。
☆ 循環式温泉給湯設備のついた全戸天然温泉付マンションまで
その他、数え上げればきりがないほど、新しい設備を標準装備したマンションが誕生しています。
しかし、いいことずくめではあるがデメリットはないのだろうか、これらの設備の耐用年数はどのくらいあるのでしょうか。売主が保証するのはアフターサービス期間のせいぜい引渡し後2年間です。
平成12年から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、売主による新築マンションの瑕疵担保責任は強化されましたが、上記の設備については、売主が任意の住宅性能表示制度を利用しない限りほとんど該当していません。
つまり、マンションを購入した後は、特別に欠陥がない限りマンション所有者の責任で全ての設備を維持管理しなくてはなりません。
これらは、売主が契約時に作成した建物の長期修繕計画書にはあまり反映されていないと思われます。
便利な設備を手にすると同時に将来の出費を覚悟しなければなりません。
次回、その一例を見てみたいと思います。
全国小中学力調査結果、知識はOK、応用問題に課題ありだそうです。世の中、何が正解かわからないことだらけです。
☆ 居室の床に埋め込まれた、人に優しい快適な床暖房設備。
☆ 室内の汚れた空気の入れ替え、カビや結露の発生を抑える24時間換気システム。
☆ キッチンで発生する生ゴミをスイッチ一つで流し台の排水口で処理できるディスポーザー。
☆ 食器と洗剤を入れてスイッチを押せば、乾燥までしてくれる食器洗浄乾燥機。
☆ 手入れのしやすさと安全性の高いIHクッキングヒーター。
☆ 洗濯物干しやカビ防止、冬の暖房に浴室乾燥機と全自動のフルオートバス。
☆ 循環式温泉給湯設備のついた全戸天然温泉付マンションまで
その他、数え上げればきりがないほど、新しい設備を標準装備したマンションが誕生しています。
しかし、いいことずくめではあるがデメリットはないのだろうか、これらの設備の耐用年数はどのくらいあるのでしょうか。売主が保証するのはアフターサービス期間のせいぜい引渡し後2年間です。
平成12年から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、売主による新築マンションの瑕疵担保責任は強化されましたが、上記の設備については、売主が任意の住宅性能表示制度を利用しない限りほとんど該当していません。
つまり、マンションを購入した後は、特別に欠陥がない限りマンション所有者の責任で全ての設備を維持管理しなくてはなりません。
これらは、売主が契約時に作成した建物の長期修繕計画書にはあまり反映されていないと思われます。
便利な設備を手にすると同時に将来の出費を覚悟しなければなりません。
次回、その一例を見てみたいと思います。
全国小中学力調査結果、知識はOK、応用問題に課題ありだそうです。世の中、何が正解かわからないことだらけです。
Posted by haru at
07:31
│Comments(0)
2007年10月23日
67 マンションは永住にふさわしい住まいか? その7
このブログで何度か紹介しているマンション総合調査は、国土交通省が 「マンション管理に関し、これまでに講じられてきた施策の効果の検証、必要となる施策の提示を行うための基礎的な資料を得る事を目的として、マンションの管理状況、マンション居住者の管理に対する意識等を調査」 したものです。
昭和62年、平成5年、平成11年と調査され、最新が平成15年6月に調査されています。
マンションに居住していても、他のマンションの事を知る機会はあまりありません。ほとんどが管理会社の情報だけを頼りにしています。他のマンションがどのように管理組合の運営をし、マンション居住者がどのような意識を持っているか等の傾向を見るには参考となる資料だと思います。
その調査項目の一つに「現住居に対する居住者の評価」というのがあります。
満足 18.1% やや満足 29.9% 普通 30.6% やや不満17.6% 不満4%です。
約8割が現住居に不満を持っていないことがうかがえます。これは平成11年度.平成15年度の調査でもあまり変化はありません。
現状で、マンションに永住するつもりだと考える人が多いのも納得できます。
マンションを終の棲家と考えている方は、このタイトルの前回までをもう一度読み直してみてください。
それと比較して、貴方のマンションの現在の実態を確認してみてください。
特に築20年以上のマンションでは、様々な問題が少しずつ現れてきています、そこに住む人たちがマンションの将来像をどう考えているか、そしてどのように行動しようとしているかを話し合う機会を作ってみてください。
そして、永住にふさわしいマンションかどうか想像力を働かせてみてください。今まで通り安心して住み続けられるのか、よりいっそう価値をあげる為にマンション居住者と一体となり努力できるのか、あるいは他の居住場所を選択するほうが良いのか等、心身ともに元気なうちに考えておきましょう。厳しいようですが、他人任せで放置したままでは、将来に待っているのは悲劇だけではないかと思います。
松坂、岡島それに松井稼、日本人の活躍が楽しみなワールドシリーズです。
昭和62年、平成5年、平成11年と調査され、最新が平成15年6月に調査されています。
マンションに居住していても、他のマンションの事を知る機会はあまりありません。ほとんどが管理会社の情報だけを頼りにしています。他のマンションがどのように管理組合の運営をし、マンション居住者がどのような意識を持っているか等の傾向を見るには参考となる資料だと思います。
その調査項目の一つに「現住居に対する居住者の評価」というのがあります。
満足 18.1% やや満足 29.9% 普通 30.6% やや不満17.6% 不満4%です。
約8割が現住居に不満を持っていないことがうかがえます。これは平成11年度.平成15年度の調査でもあまり変化はありません。
現状で、マンションに永住するつもりだと考える人が多いのも納得できます。
マンションを終の棲家と考えている方は、このタイトルの前回までをもう一度読み直してみてください。
それと比較して、貴方のマンションの現在の実態を確認してみてください。
特に築20年以上のマンションでは、様々な問題が少しずつ現れてきています、そこに住む人たちがマンションの将来像をどう考えているか、そしてどのように行動しようとしているかを話し合う機会を作ってみてください。
そして、永住にふさわしいマンションかどうか想像力を働かせてみてください。今まで通り安心して住み続けられるのか、よりいっそう価値をあげる為にマンション居住者と一体となり努力できるのか、あるいは他の居住場所を選択するほうが良いのか等、心身ともに元気なうちに考えておきましょう。厳しいようですが、他人任せで放置したままでは、将来に待っているのは悲劇だけではないかと思います。
松坂、岡島それに松井稼、日本人の活躍が楽しみなワールドシリーズです。
Posted by haru at
11:47
│Comments(0)
2007年10月22日
66 マンションは永住にふさわしい住まいか? その6
マンションの完成年次が古いほど賃貸化率が高くなる傾向になるといわれています。平成15年の調査では築10年以上のマンションは賃貸化率21%以上が3割~4割あると報告しています。
マンションのルールである管理規約には通常、賃借人はマンションの住まい方についてマンション所有者と同一の義務を負うとしています。その中には、管理費等の支払義務は含まれていません。
賃貸化率が高くなると、現実には、どのような問題が生じているでしょうか。大きくは二つの問題があります。
その一つは賃貸したマンションの所有者(区分所有者と呼ばれる人です)に関する事です。
1) マンションに居住していない為、組合員としての義務が果たしにくくなる。
2) 管理費等の滞納が発生した場合、回収が困難になる。
3) マンションに居住していない為、情報が伝わりにくく、管理組合から総会案内等が来ても賛否の判断ができにくい。
4) 管理組合の役員にはなりにくい。
5) 現に居住する組合員と意見が対立しやすくなる。
もう一つは実際に居住している賃借人に関する事です。
1) 賃借人は、直接にはマンションを維持管理する責任がないため、管理費や修繕積立金の納付義務がないことによりマンション管理には無関心となりやすい。
2) 建物使用上のルールを守らない場合が多くなる。ルールそのものをよく知らない。
3) 賃借人が転貸した場合、現居住者の実態把握が困難になる。たとえば暴力団組員に貸してもわかりにくい。
4) 組合員ではない為、コミュニティー活動への参加がしにくい。
私有財産であるマンションの賃貸を管理組合が阻止することは出来ません。
賃貸化率が20%も超えてくると、管理組合運営自体が難しくなります。
賃貸等でマンションに居住していない組合員に対して、義務を履行できない代わりに管理費等を高くすることも考えられますが、賛否は分かれています。
ほとんどのマンションで管理費等の額については、組合員の共用部分の共有持分(専有部分の床面積の割合)に応じて算出する、としていることが理由だと思います。
貴方の住んでいるマンションの現在の賃貸化率はご存知ですか、一度確認してみてください。
今のうちに、賃貸化の増加等に備えて、各マンションの実情を考慮した管理規約の見直しが必要です。
昨年他界した義母は「赤福」が好きでした。「今日作ったものしか、売らないそうだから、朝早くから沢山の人で作っているんだろうね」と言っていました。
マンションのルールである管理規約には通常、賃借人はマンションの住まい方についてマンション所有者と同一の義務を負うとしています。その中には、管理費等の支払義務は含まれていません。
賃貸化率が高くなると、現実には、どのような問題が生じているでしょうか。大きくは二つの問題があります。
その一つは賃貸したマンションの所有者(区分所有者と呼ばれる人です)に関する事です。
1) マンションに居住していない為、組合員としての義務が果たしにくくなる。
2) 管理費等の滞納が発生した場合、回収が困難になる。
3) マンションに居住していない為、情報が伝わりにくく、管理組合から総会案内等が来ても賛否の判断ができにくい。
4) 管理組合の役員にはなりにくい。
5) 現に居住する組合員と意見が対立しやすくなる。
もう一つは実際に居住している賃借人に関する事です。
1) 賃借人は、直接にはマンションを維持管理する責任がないため、管理費や修繕積立金の納付義務がないことによりマンション管理には無関心となりやすい。
2) 建物使用上のルールを守らない場合が多くなる。ルールそのものをよく知らない。
3) 賃借人が転貸した場合、現居住者の実態把握が困難になる。たとえば暴力団組員に貸してもわかりにくい。
4) 組合員ではない為、コミュニティー活動への参加がしにくい。
私有財産であるマンションの賃貸を管理組合が阻止することは出来ません。
賃貸化率が20%も超えてくると、管理組合運営自体が難しくなります。
賃貸等でマンションに居住していない組合員に対して、義務を履行できない代わりに管理費等を高くすることも考えられますが、賛否は分かれています。
ほとんどのマンションで管理費等の額については、組合員の共用部分の共有持分(専有部分の床面積の割合)に応じて算出する、としていることが理由だと思います。
貴方の住んでいるマンションの現在の賃貸化率はご存知ですか、一度確認してみてください。
今のうちに、賃貸化の増加等に備えて、各マンションの実情を考慮した管理規約の見直しが必要です。
昨年他界した義母は「赤福」が好きでした。「今日作ったものしか、売らないそうだから、朝早くから沢山の人で作っているんだろうね」と言っていました。
Posted by haru at
07:17
│Comments(0)
2007年10月19日
65 マンションは永住にふさわしい住まいか? その5
マンションに永住したいと考えている人は、いま居住しているマンションの住み心地が良いと感じている人たちでしょう。
永く住めば住むほど、周辺の環境も含めてそのマンションに愛着を感じるものです。高齢になった時に、他のより良いマンションに移り住むことはあまり考えていないと思います。もちろん、経済的に余裕のある人は別の選択を考える人もいるでしょう。
高齢者の為の住まいは条件さえ合えば、実に沢山あります。
ケアハウス(軽費老人ホーム)、有料老人ホーム、高齢者グループホーム、生活支援ハウス、高齢者向け優良賃貸住宅、グループリビング、シルバーハウジング、コレクティブハウジング等々、
これからもますます多様な住まいの選択が可能になるでしょう。
それでも、今のマンションをリフォームしてでも、長年すみ慣れた家で自立した生活を送りたいと考えている人が多いのではないかと思います。
これまでの長い期間、マンションの維持管理に関しては、無関心で、他人任せできた人が多いのではないでしょうか。それは、これまであまり大きな問題もなかったか、委託した管理会社がそれなりに対応してきた結果であったのかも知れません。しかし、問題があっても、気づかなかったり、一部の人は知っていても放置したきた例がかなりあります。
本当の問題が発生するのは、これからです。
たとえば、高齢化により体が不自由になり老人施設に入居する人は、愛着があるほどマンションの所有権をそのままにして賃貸に出す人があるでしょう。あるいは値下がりをして必要な価格で売却できなくて賃貸する人もいるかもしれません。
そのような人が増えて、マンションの賃貸化率があがったとき、どのような問題が生ずるでしょうか。
マンション管理に対する無関心層の増加となり、マンションの老朽化,沈滞化に拍車をかけるだけになります。
次回は、すでに賃貸化率の高いマンションで発生している問題について考えてみたいと思います。
「過疎と高齢化で存続が危ぶまれる 限界集落 が全国で急増」に 行政が支援策の検討を開始。私有財産であるマンションには行政の支援はあまり期待できそうにありません。
永く住めば住むほど、周辺の環境も含めてそのマンションに愛着を感じるものです。高齢になった時に、他のより良いマンションに移り住むことはあまり考えていないと思います。もちろん、経済的に余裕のある人は別の選択を考える人もいるでしょう。
高齢者の為の住まいは条件さえ合えば、実に沢山あります。
ケアハウス(軽費老人ホーム)、有料老人ホーム、高齢者グループホーム、生活支援ハウス、高齢者向け優良賃貸住宅、グループリビング、シルバーハウジング、コレクティブハウジング等々、
これからもますます多様な住まいの選択が可能になるでしょう。
それでも、今のマンションをリフォームしてでも、長年すみ慣れた家で自立した生活を送りたいと考えている人が多いのではないかと思います。
これまでの長い期間、マンションの維持管理に関しては、無関心で、他人任せできた人が多いのではないでしょうか。それは、これまであまり大きな問題もなかったか、委託した管理会社がそれなりに対応してきた結果であったのかも知れません。しかし、問題があっても、気づかなかったり、一部の人は知っていても放置したきた例がかなりあります。
本当の問題が発生するのは、これからです。
たとえば、高齢化により体が不自由になり老人施設に入居する人は、愛着があるほどマンションの所有権をそのままにして賃貸に出す人があるでしょう。あるいは値下がりをして必要な価格で売却できなくて賃貸する人もいるかもしれません。
そのような人が増えて、マンションの賃貸化率があがったとき、どのような問題が生ずるでしょうか。
マンション管理に対する無関心層の増加となり、マンションの老朽化,沈滞化に拍車をかけるだけになります。
次回は、すでに賃貸化率の高いマンションで発生している問題について考えてみたいと思います。
「過疎と高齢化で存続が危ぶまれる 限界集落 が全国で急増」に 行政が支援策の検討を開始。私有財産であるマンションには行政の支援はあまり期待できそうにありません。
Posted by haru at
13:44
│Comments(0)
2007年10月18日
64 マンションは永住にふさわしい住まいか? その4
現在住んでいるマンションを永住するのにふさわしいマンションにするには、ハード面に関しては、あるところまでは、そこそこの費用さえ負担できれば方法はあります。
建物のバリアフリー対応として 「段差の解消やスロープ化」 「手摺の取り付け」 「出入り口の改良」 「車椅子移動用のスペースの拡大」等は、ある程度は比較的可能です。
しかし、寝たきり老人が暮らす為に、ストレッチャーが自由に使用できるには、費用を掛けても既設のマンションではかなり無理があります。
たとえば、ストレッチャーのまま、エレベーターで移動できるようにする改良費用はエレベーターシャフトであるコンクリート部分の改良が必要であり、多額の費用を負担しなければなりません。
ただし、あまり知らない人もいるようですが、既設のマンションでも通常はエレベーターの籠の中にあって、扉で閉鎖されていますが、ストレッチャーや棺桶のまま運搬可能なエレベーターもありますので、自分の住むマンションはどうなっているか一度確認してみてください。
最近では単に障害を取り除く「バリアフリーデザイン」という考え方から、最初から障害のないものをあわせてつくる、高齢者等だけではなく誰でもが住みよい環境として「ユニバーサルデザイン」と呼ばれる考え方に代わってきています。社会的なニーズが複雑に変化してきています。そしてそれに対応したマンションも生まれつつあるようです。
最近は、若い人でも発症するようですが、長寿になればなるほど、認知症の可能性は高くなることが、想像できます。
まだ、利用率は低いそうですが、平成12年からスタートした「成年後見制度」の利用など単身高齢者の増加を想定した対策を講じておく必要もあります。
本当に安心して永住する為には建物のハード面を改良するだけではなく、高齢者同士の相互扶助や介助のシステムをマンションを含む地域全体で取り組むコミュニティーとして考え、高齢者対応に関するソフトの問題を解決しなければなりません。
阪神・淡路大震災後に経験した仮設住宅やその後の復興住宅での多くの「孤独死」が、これから予想される「限界集落化」したマンションで再現されない為にも。
亀田父子、謝罪会見。18歳の子よりも親が丸刈りになるほうが良かったのでは?
建物のバリアフリー対応として 「段差の解消やスロープ化」 「手摺の取り付け」 「出入り口の改良」 「車椅子移動用のスペースの拡大」等は、ある程度は比較的可能です。
しかし、寝たきり老人が暮らす為に、ストレッチャーが自由に使用できるには、費用を掛けても既設のマンションではかなり無理があります。
たとえば、ストレッチャーのまま、エレベーターで移動できるようにする改良費用はエレベーターシャフトであるコンクリート部分の改良が必要であり、多額の費用を負担しなければなりません。
ただし、あまり知らない人もいるようですが、既設のマンションでも通常はエレベーターの籠の中にあって、扉で閉鎖されていますが、ストレッチャーや棺桶のまま運搬可能なエレベーターもありますので、自分の住むマンションはどうなっているか一度確認してみてください。
最近では単に障害を取り除く「バリアフリーデザイン」という考え方から、最初から障害のないものをあわせてつくる、高齢者等だけではなく誰でもが住みよい環境として「ユニバーサルデザイン」と呼ばれる考え方に代わってきています。社会的なニーズが複雑に変化してきています。そしてそれに対応したマンションも生まれつつあるようです。
最近は、若い人でも発症するようですが、長寿になればなるほど、認知症の可能性は高くなることが、想像できます。
まだ、利用率は低いそうですが、平成12年からスタートした「成年後見制度」の利用など単身高齢者の増加を想定した対策を講じておく必要もあります。
本当に安心して永住する為には建物のハード面を改良するだけではなく、高齢者同士の相互扶助や介助のシステムをマンションを含む地域全体で取り組むコミュニティーとして考え、高齢者対応に関するソフトの問題を解決しなければなりません。
阪神・淡路大震災後に経験した仮設住宅やその後の復興住宅での多くの「孤独死」が、これから予想される「限界集落化」したマンションで再現されない為にも。
亀田父子、謝罪会見。18歳の子よりも親が丸刈りになるほうが良かったのでは?
Posted by haru at
08:52
│Comments(0)
2007年10月17日
63 マンションは永住にふさわしい住まいか? その3
永住するのにふさわしいマンションにするには、どのような条件が必要でしょうか。
基本的には、いつまでも安心で快適な住まいとしての居住価値の高さであり、いざというときには高く処分しやすい財産となる資産価値の高さを維持しているマンションのことだと思います。
そのためには、以下のことが考えられます。
1) なんといっても、毎月支払い続ける管理費や修繕積立金等が適正な価格に設定され、適正な時期に適正に使用されていることです。それには、他人任せにしないで、居住者自らが積極的にかかわっていることです。
2) マンションは敷地や建物のほとんどを所有者全員で共有しています。ある種の共同社会を形成しています。そのためのルールがマンション独自なものとして設定され、そこに住む住民全員がよく理解して守っていることです。
3) 社会的ニーズの変化に対応した改良がされていることです。高齢者や身障者の為のハード、ソフト面からのバリアフリー化、防犯カメラの設置等や非常時用の備蓄倉庫の設置、あるいは電気設備の多様化に対応した電気容量のアップ等々です。
4) マンションはその誕生過程で周辺地域と対立していることがあります。マンションに住む住民まで
対立することはありません。地域の自治会、町内会等に積極的に参加し、地域と一体の活動をしていることです。まちづくりに参加することで行政のさまざまの助成等も可能になります。
5) これはかなり難しいことですが、望ましいのはそのマンションで育ち、独立した子供が再び帰ってきてそこに住みたいという気持ちを起こさせる環境を維持していることです。
エスカレーターで子供が事故のニュース。エレベーターや車、動く物は便利だが常に危険と隣り合わせ。
基本的には、いつまでも安心で快適な住まいとしての居住価値の高さであり、いざというときには高く処分しやすい財産となる資産価値の高さを維持しているマンションのことだと思います。
そのためには、以下のことが考えられます。
1) なんといっても、毎月支払い続ける管理費や修繕積立金等が適正な価格に設定され、適正な時期に適正に使用されていることです。それには、他人任せにしないで、居住者自らが積極的にかかわっていることです。
2) マンションは敷地や建物のほとんどを所有者全員で共有しています。ある種の共同社会を形成しています。そのためのルールがマンション独自なものとして設定され、そこに住む住民全員がよく理解して守っていることです。
3) 社会的ニーズの変化に対応した改良がされていることです。高齢者や身障者の為のハード、ソフト面からのバリアフリー化、防犯カメラの設置等や非常時用の備蓄倉庫の設置、あるいは電気設備の多様化に対応した電気容量のアップ等々です。
4) マンションはその誕生過程で周辺地域と対立していることがあります。マンションに住む住民まで
対立することはありません。地域の自治会、町内会等に積極的に参加し、地域と一体の活動をしていることです。まちづくりに参加することで行政のさまざまの助成等も可能になります。
5) これはかなり難しいことですが、望ましいのはそのマンションで育ち、独立した子供が再び帰ってきてそこに住みたいという気持ちを起こさせる環境を維持していることです。
エスカレーターで子供が事故のニュース。エレベーターや車、動く物は便利だが常に危険と隣り合わせ。
Posted by haru at
08:46
│Comments(0)
2007年10月16日
62 マンションは永住にふさわしい住まいか? その2
65歳以上の高齢の居住者が半数以上住むマンションを想像してみましょう。
所帯主が65歳を過ぎれば、子供さんは独立して別居しているでしょうから、夫婦二人だけという家庭が多いでしょう。
又、60歳代は70%、70歳代は80%近くの人がそのマンションを終の棲家と考えているそうです。
住宅ローンは支払い済みでしょうから、住宅の確保という安心感はあるでしょう。年金やある程度の預貯金等で通常の管理費や修繕積立金等は支払が可能な、ある意味では恵まれた階層の人々だと思われます。
しかし、この居住者がそのまま住み続け80歳を過ぎた頃、体が不自由になったり、寝たきりになったり、あるいは認知症になることは当然考えられることです。
いつでも帰れるように、マンションはそのままにして、入退院を繰り返すか、老人施設のお世話になるかでしょう。
そのときに、今までどうりの管理費や修繕積立金等が確実に支払われる保証はなくなります。
ましてや高齢者の為の建物をバリアフリー化するなどの改良工事のための追加費用の支払に耐えられない高齢者も出てくるでしょう。
ましてや建て替え等の対応は不可能に近いでしょう。
残念ながら、現在のマンションはこのような居住者が増えたときの状態を想定して運営されてはいません。
滅失や建て替えによる戸数減を無視すると、10年後には、築40年を過ぎたマンションが63万戸、築30年を過ぎたマンションが172万戸にもなるそうです。
老朽化した建物、高齢化した居住者 共に確実に増えてきます。
だんだん暗い話になってきました。しかし、その対策を考えるのは、今住んでいるマンションの居住者しかいません。
永住にふさわしいマンションにするかしないか、そこに住む元気なうちの貴方次第です。
横浜のマンションで構造計算書の偽造が発覚。3800ページの計算書のうち6箇所で改ざん。第三者が短時間でどこまでチェックできるのだろうか?
所帯主が65歳を過ぎれば、子供さんは独立して別居しているでしょうから、夫婦二人だけという家庭が多いでしょう。
又、60歳代は70%、70歳代は80%近くの人がそのマンションを終の棲家と考えているそうです。
住宅ローンは支払い済みでしょうから、住宅の確保という安心感はあるでしょう。年金やある程度の預貯金等で通常の管理費や修繕積立金等は支払が可能な、ある意味では恵まれた階層の人々だと思われます。
しかし、この居住者がそのまま住み続け80歳を過ぎた頃、体が不自由になったり、寝たきりになったり、あるいは認知症になることは当然考えられることです。
いつでも帰れるように、マンションはそのままにして、入退院を繰り返すか、老人施設のお世話になるかでしょう。
そのときに、今までどうりの管理費や修繕積立金等が確実に支払われる保証はなくなります。
ましてや高齢者の為の建物をバリアフリー化するなどの改良工事のための追加費用の支払に耐えられない高齢者も出てくるでしょう。
ましてや建て替え等の対応は不可能に近いでしょう。
残念ながら、現在のマンションはこのような居住者が増えたときの状態を想定して運営されてはいません。
滅失や建て替えによる戸数減を無視すると、10年後には、築40年を過ぎたマンションが63万戸、築30年を過ぎたマンションが172万戸にもなるそうです。
老朽化した建物、高齢化した居住者 共に確実に増えてきます。
だんだん暗い話になってきました。しかし、その対策を考えるのは、今住んでいるマンションの居住者しかいません。
永住にふさわしいマンションにするかしないか、そこに住む元気なうちの貴方次第です。
横浜のマンションで構造計算書の偽造が発覚。3800ページの計算書のうち6箇所で改ざん。第三者が短時間でどこまでチェックできるのだろうか?
Posted by haru at
08:13
│Comments(0)
2007年10月15日
61 マンションは永住にふさわしい住まいか? その1
国土交通省による平成15年度「マンション総合調査」によると、現在マンションに住む人で「マンションに永住するつもりである」と答えた人が48%だそうである。平成11年度調査の39.6%から8.4%増加している。
「いずれは住み替えるつもりである」が26.5%、「特に考えていない」が25.5%だそうである。
所帯主の年齢でみると、50歳代以上の高齢者ほどマンションの永住志向は高くなり、マンションを終の棲家と考える人が年々多くなっています。
又、将来への不安に対しては 「居住者の高齢化」 が最も多いと報告されている。
平成15年調査時点でのマンション所帯主で40歳代以上の人が85.6%だそうです。
仮に、そのうちの60%がそのまま永住したいと考えれば、あと20年もすれば、多くの子供は独立しているでしょうから、65歳以上の高齢の居住者が50%以上となるマンションがあちこちに誕生していることがと想定されます。
過疎化で人口の50%が65歳以上の高齢者になり、社会的共同生活の維持が困難になった集落のことを 「限界集落」 と呼ぶそうです。
まさに、人口構成だけから見ると、マンションが 「限界集落」 なみになることが予想されます。20年またなくても、すでにそれに近いマンションが存在していてもおかしくはありません。
マンションの限界集落化に対して、どのような問題が想定されるのでしょうか、今のうちに、どのような対策を講じておく必要があるのでしょうか。
次回、そのことを考えてみたいと思います。
偽装防止のため、建築基準法改正で建築確認審査強化。マンション販売業者は価格へ影響すると騒いでいます。いままでの審査はなんだったのか?
「いずれは住み替えるつもりである」が26.5%、「特に考えていない」が25.5%だそうである。
所帯主の年齢でみると、50歳代以上の高齢者ほどマンションの永住志向は高くなり、マンションを終の棲家と考える人が年々多くなっています。
又、将来への不安に対しては 「居住者の高齢化」 が最も多いと報告されている。
平成15年調査時点でのマンション所帯主で40歳代以上の人が85.6%だそうです。
仮に、そのうちの60%がそのまま永住したいと考えれば、あと20年もすれば、多くの子供は独立しているでしょうから、65歳以上の高齢の居住者が50%以上となるマンションがあちこちに誕生していることがと想定されます。
過疎化で人口の50%が65歳以上の高齢者になり、社会的共同生活の維持が困難になった集落のことを 「限界集落」 と呼ぶそうです。
まさに、人口構成だけから見ると、マンションが 「限界集落」 なみになることが予想されます。20年またなくても、すでにそれに近いマンションが存在していてもおかしくはありません。
マンションの限界集落化に対して、どのような問題が想定されるのでしょうか、今のうちに、どのような対策を講じておく必要があるのでしょうか。
次回、そのことを考えてみたいと思います。
偽装防止のため、建築基準法改正で建築確認審査強化。マンション販売業者は価格へ影響すると騒いでいます。いままでの審査はなんだったのか?
Posted by haru at
08:01
│Comments(0)
2007年10月12日
60 マンション管理組合の役員、報酬は必要か?
国が行った平成15年度の「マンション総合調査」では、役員報酬のあるマンションは20%あるそうです。築年数が多いほど、又、規模の大きいほど割合が高くなっているようです。
報酬額は理事長で年間10万円というところもあるようですが、役員一律で年間1~2万円というところが多いようです。
いずれにしても、このくらいの報酬を受け取り、責任を持たされ、組合員から苦情を言われるより、出来ることなら役員をしたくないというのが本音だと思います。
ほとんどの管理組合で役員のなり手がなくて困っています。わずかな報酬を支払うことで、自発的に立候補する人がいなくなることのほうが多いと思われます。
役員報酬の代わりに、役員の活動費としてまとめて計上して、マンション関係の図書の購入や、マンション関連のセミナーに参加したり、又、専門家に依頼してアドバイスを受ける費用に充当するといった、役員としての活動に自由に使えるようにしたほうが、効果的だと思います。
役員の任期は前記の調査によると、70%が1年、27%が2年ということであり、その活動実態も理事会を月1度あるいは年数回程度開催して、管理会社の報告を聞くだけというのが多いようです。
組合員が順番に役員を経験しておくというのは、マンションの管理に対する意識を公平に高める上で必要なことではありますが、現状は、その効果には疑問を感じます。
信頼できる人を専従で役員にして、その中に外部の専門家も入れて、継続的に一貫した管理が出来るようにしているマンションも見受けられるようになりました。
マンションの実情に合わせて、役員のあり方そのものを見直す必要がありそうです。
野菜系飲料「1本で1日分の野菜」、ほとんどが不足だそうです。食品表示、何を信用する?
報酬額は理事長で年間10万円というところもあるようですが、役員一律で年間1~2万円というところが多いようです。
いずれにしても、このくらいの報酬を受け取り、責任を持たされ、組合員から苦情を言われるより、出来ることなら役員をしたくないというのが本音だと思います。
ほとんどの管理組合で役員のなり手がなくて困っています。わずかな報酬を支払うことで、自発的に立候補する人がいなくなることのほうが多いと思われます。
役員報酬の代わりに、役員の活動費としてまとめて計上して、マンション関係の図書の購入や、マンション関連のセミナーに参加したり、又、専門家に依頼してアドバイスを受ける費用に充当するといった、役員としての活動に自由に使えるようにしたほうが、効果的だと思います。
役員の任期は前記の調査によると、70%が1年、27%が2年ということであり、その活動実態も理事会を月1度あるいは年数回程度開催して、管理会社の報告を聞くだけというのが多いようです。
組合員が順番に役員を経験しておくというのは、マンションの管理に対する意識を公平に高める上で必要なことではありますが、現状は、その効果には疑問を感じます。
信頼できる人を専従で役員にして、その中に外部の専門家も入れて、継続的に一貫した管理が出来るようにしているマンションも見受けられるようになりました。
マンションの実情に合わせて、役員のあり方そのものを見直す必要がありそうです。
野菜系飲料「1本で1日分の野菜」、ほとんどが不足だそうです。食品表示、何を信用する?
Posted by haru at
08:08
│Comments(0)
2007年10月11日
59 マンションの管理員の責任は?
マンションの管理員(これまでは一般的に管理人と呼ばれていました)は通常、管理会社から派遣されています。管理組合と管理会社が結んだ管理委託契約書に定められた業務を行い、その範囲内で責任を負います。
管理員はマンションのことを一番良く知る立場にあります。長くいる人はマンションの生き字引といわれたり、多くの住民から慕われている優秀な人も居られますが、中には管理組合を勝手に仕切っているような管理員も見受けられます。
マンションごとに内容は異なりますが、一般的には次のような業務となっています。
1) 居住者が管理組合に提出する各種書類の受理や報告の受付等
2) 建物、設備等の目視点検等
3) 外注業者の業務の着手、履行の立会い等
4) 居住者への書類の配布等、その他の報告連絡業務
管理員に特別な資格は必要ありません。出来れば設備などに詳しい人や簡単な補修作業が出来る身の軽い人が望ましいと思います。又、居住者のプライバシーに触れることがあっても口外しない姿勢が大切です。
マンションの規模によって管理員の勤務形態は通勤、巡回、常駐(住み込み)と色々です。
業務内容がはっきりと、居住者に理解されていないため、又、本人も管理規約や委託契約書の中身を正確に理解していないことにより、居住者とのトラブルの原因となることが多いようです。
常にマンションにいる為に、マンションのことを全て知っているように錯覚しがちですが、具体的なことまで理解している管理員はまれです。
管理会社は自己の管理業務をおこなう為の補助者として管理員を使用するわけです。従って管理員の業務によるトラブルは使用者責任として管理会社が負うことになります。
その意味では、先日の、京都での女児マンホール転落死事故での管理員らに対する有罪判決で、詳細はわかりませんが、管理会社の責任が問われていないのは奇異な感じがします。
マンションの手摺のない屋上で遊ぶ子供を見かけることがあります。この事件を特別視しないで、マンションに子供や高齢者にとって危険な場所はないか、管理組合の責任として見直すことが必要かと思います。
大阪・難波の建物の壁面に、垂直落下型の絶叫マシーンが出来るそうです。そこまでしなくても身近に危険はいっぱい。
管理員はマンションのことを一番良く知る立場にあります。長くいる人はマンションの生き字引といわれたり、多くの住民から慕われている優秀な人も居られますが、中には管理組合を勝手に仕切っているような管理員も見受けられます。
マンションごとに内容は異なりますが、一般的には次のような業務となっています。
1) 居住者が管理組合に提出する各種書類の受理や報告の受付等
2) 建物、設備等の目視点検等
3) 外注業者の業務の着手、履行の立会い等
4) 居住者への書類の配布等、その他の報告連絡業務
管理員に特別な資格は必要ありません。出来れば設備などに詳しい人や簡単な補修作業が出来る身の軽い人が望ましいと思います。又、居住者のプライバシーに触れることがあっても口外しない姿勢が大切です。
マンションの規模によって管理員の勤務形態は通勤、巡回、常駐(住み込み)と色々です。
業務内容がはっきりと、居住者に理解されていないため、又、本人も管理規約や委託契約書の中身を正確に理解していないことにより、居住者とのトラブルの原因となることが多いようです。
常にマンションにいる為に、マンションのことを全て知っているように錯覚しがちですが、具体的なことまで理解している管理員はまれです。
管理会社は自己の管理業務をおこなう為の補助者として管理員を使用するわけです。従って管理員の業務によるトラブルは使用者責任として管理会社が負うことになります。
その意味では、先日の、京都での女児マンホール転落死事故での管理員らに対する有罪判決で、詳細はわかりませんが、管理会社の責任が問われていないのは奇異な感じがします。
マンションの手摺のない屋上で遊ぶ子供を見かけることがあります。この事件を特別視しないで、マンションに子供や高齢者にとって危険な場所はないか、管理組合の責任として見直すことが必要かと思います。
大阪・難波の建物の壁面に、垂直落下型の絶叫マシーンが出来るそうです。そこまでしなくても身近に危険はいっぱい。
Posted by haru at
07:45
│Comments(0)
2007年10月09日
58 マンションの総会決議に疑問があるときは?
総会で議案が議決される為には、総会が適法な手続きで開催され、その総会で議案が有効に採決されることが必要です。
総会は通常では、理事長が、総会開催日の少なくとも1週間前に総会の通知を組合員に出すことになっています。
総会の議案は組合員が意見を決定する為に必要な資料を添えて通知するのが一般的です。
特に重要な議案である管理規約の変更や共用部分の変更等については決議内容がよく理解できる資料が必要です。
又、10年~15年に1度くらいで実施される大規模な改修工事等については総会開催前に住民説明会等で十分な説明をして、工事内容を理解してもらうことが大切です。
時間をかけて、十分住民に納得してもらった上で委任状を集め、説明や議論を重ねた上での決議であれば、総会の決議に疑問があっても従わざるを得ません。
総会の決議事項の中で「詳細については理事会一任とする。」場合が多いようです。大規模な改修工事のように多額な費用が発生する事項等については、決議通りに工事が出来ないことも多く、理事会任せではなく、住民に納得される説明を何度も繰り返すことが大切です。
理事長が十分な対応をしない場合は、解任手続きをとることもできますし、善良なる管理者としての注意義務を尽くさず、管理組合に損害を与えたときには、その賠償を求めることも出来ます。
理事長にはその自覚がなくても、管理組合の代表として重要な職務権限があるということです。
議員の領収書、「一円」でもめています。多額な組合費等を預かる理事長、その責任は重大です。
総会は通常では、理事長が、総会開催日の少なくとも1週間前に総会の通知を組合員に出すことになっています。
総会の議案は組合員が意見を決定する為に必要な資料を添えて通知するのが一般的です。
特に重要な議案である管理規約の変更や共用部分の変更等については決議内容がよく理解できる資料が必要です。
又、10年~15年に1度くらいで実施される大規模な改修工事等については総会開催前に住民説明会等で十分な説明をして、工事内容を理解してもらうことが大切です。
時間をかけて、十分住民に納得してもらった上で委任状を集め、説明や議論を重ねた上での決議であれば、総会の決議に疑問があっても従わざるを得ません。
総会の決議事項の中で「詳細については理事会一任とする。」場合が多いようです。大規模な改修工事のように多額な費用が発生する事項等については、決議通りに工事が出来ないことも多く、理事会任せではなく、住民に納得される説明を何度も繰り返すことが大切です。
理事長が十分な対応をしない場合は、解任手続きをとることもできますし、善良なる管理者としての注意義務を尽くさず、管理組合に損害を与えたときには、その賠償を求めることも出来ます。
理事長にはその自覚がなくても、管理組合の代表として重要な職務権限があるということです。
議員の領収書、「一円」でもめています。多額な組合費等を預かる理事長、その責任は重大です。
Posted by haru at
08:38
│Comments(0)
2007年10月08日
57 マンションの給湯器、誰のもの?
マンションの管理をする上で複雑でわかりにくいのが、専有部分と共用部分です。
それには、大きく4つの問題があります。
1) 専有部分と共用部分の境界はどこか
2) 所有者と使用者が別々の場合がある
3) 管理の責任は誰なのか
4) 管理のための費用負担は誰がするのか
給湯器もこれらの問題を明確にしておくことが必要です。同じようなものに玄関先のインターホンや室内から操作できる玄関灯などもあります。
給湯器には電気を利用した電気温水器やガスを利用したガス給湯器が主に使用され、その設置場所もローカやバルコニーの共用部分に設置されたり、電気温水器に見られるように、住戸内の専有部分に設置されたり、色々です。
多くのマンションに見られる玄関横にあるパイプスペース、メーターボックスは共用部分とされています。しかし、その中にある給湯器や浄水器等それにつながる配管はその住戸で専用に使用するものなので専有部分と考えるのが一般的のようです。
標準的な管理規約には専有部分の範囲として 「専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。」 とありますが、わかりにくい表現がされています。
いずれにしても、居住者間のトラブルは、責任範囲が明確でないことから発生します。
それぞれ具体的に、誰が所有しているのか、誰が使用しているのか、誰が管理するのか、誰が費用を負担するのかわかりやすくしておくことです。
今日は「体育の日」あいにくの空模様です。本来は10月10日の晴れの多い特異日のはずでしたが。
それには、大きく4つの問題があります。
1) 専有部分と共用部分の境界はどこか
2) 所有者と使用者が別々の場合がある
3) 管理の責任は誰なのか
4) 管理のための費用負担は誰がするのか
給湯器もこれらの問題を明確にしておくことが必要です。同じようなものに玄関先のインターホンや室内から操作できる玄関灯などもあります。
給湯器には電気を利用した電気温水器やガスを利用したガス給湯器が主に使用され、その設置場所もローカやバルコニーの共用部分に設置されたり、電気温水器に見られるように、住戸内の専有部分に設置されたり、色々です。
多くのマンションに見られる玄関横にあるパイプスペース、メーターボックスは共用部分とされています。しかし、その中にある給湯器や浄水器等それにつながる配管はその住戸で専用に使用するものなので専有部分と考えるのが一般的のようです。
標準的な管理規約には専有部分の範囲として 「専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。」 とありますが、わかりにくい表現がされています。
いずれにしても、居住者間のトラブルは、責任範囲が明確でないことから発生します。
それぞれ具体的に、誰が所有しているのか、誰が使用しているのか、誰が管理するのか、誰が費用を負担するのかわかりやすくしておくことです。
今日は「体育の日」あいにくの空模様です。本来は10月10日の晴れの多い特異日のはずでしたが。
Posted by haru at
08:11
│Comments(0)
2007年10月06日
56 マンションの水道料、なぜ管理組合に払うのか?
マンション住民はあまり意識はしていないと思いますが、ほとんどのマンションで管理組合が自治体から水を買取、その水を各住戸に販売しているという方式をとっています。
つまり、管理組合は親メーターで一括して自治体に水道料を支払い、各住戸の子メーターを管理員等が検針して自治体での水道料金算定法に基づいて各住戸に請求しています。
親メーターで水道料を支払う場合は、多くの自治体で水道料金の算定の際、共同住宅用の大口割引制度を採用している為、マンション全体の使用量を戸数割りした場合の低い単価を適用しています。
本来、水道料金は水をたくさん使うほど料金単価が割高になる仕組みになっていますが、この大口割引という特例申請をしておけば、各住戸の合計使用料よりも管理組合が自治体に支払う水道料のほうが安いことになります。
管理組合としては、その差益で共用部分で使用する散水用の水道料等を支払うことが出来、さらに剰余金も発生します。自治体にもよりますが100戸ほどのマンションでは年間50万円~100万円くらいの金額になることもあります。
注意が必要なのは、マンションの分譲直後に大量の売れ残りがある場合、最初の入居者分の申請しかなされていませんから、水道料金が高いままで申請されていることがあります。管理会社が忘れていることがありますので、現在の全入居者分で申請されているか水道局に確認しましょう。
また、親メーターから各住戸の子メーターまでに埋設給水管がある場合、漏水が発生していても土中に浸透している為、長い間気がつかないこともありますので、親メーターの水道使用量の変動に注意することも必要です。
水道料金の徴収や支払は管理会社に委託していますが、管理会社は機械的に処理している場合が多いので管理組合で定期的な確認が必要です。
「生保不払い38社910億円」 そういえば、あまり知らないマンションの損害保険の内容。
つまり、管理組合は親メーターで一括して自治体に水道料を支払い、各住戸の子メーターを管理員等が検針して自治体での水道料金算定法に基づいて各住戸に請求しています。
親メーターで水道料を支払う場合は、多くの自治体で水道料金の算定の際、共同住宅用の大口割引制度を採用している為、マンション全体の使用量を戸数割りした場合の低い単価を適用しています。
本来、水道料金は水をたくさん使うほど料金単価が割高になる仕組みになっていますが、この大口割引という特例申請をしておけば、各住戸の合計使用料よりも管理組合が自治体に支払う水道料のほうが安いことになります。
管理組合としては、その差益で共用部分で使用する散水用の水道料等を支払うことが出来、さらに剰余金も発生します。自治体にもよりますが100戸ほどのマンションでは年間50万円~100万円くらいの金額になることもあります。
注意が必要なのは、マンションの分譲直後に大量の売れ残りがある場合、最初の入居者分の申請しかなされていませんから、水道料金が高いままで申請されていることがあります。管理会社が忘れていることがありますので、現在の全入居者分で申請されているか水道局に確認しましょう。
また、親メーターから各住戸の子メーターまでに埋設給水管がある場合、漏水が発生していても土中に浸透している為、長い間気がつかないこともありますので、親メーターの水道使用量の変動に注意することも必要です。
水道料金の徴収や支払は管理会社に委託していますが、管理会社は機械的に処理している場合が多いので管理組合で定期的な確認が必要です。
「生保不払い38社910億円」 そういえば、あまり知らないマンションの損害保険の内容。
Posted by haru at
08:11
│Comments(0)
2007年10月04日
55 マンションの賃借人、理事になれるか?
マンションの賃貸化が進み、役員のなり手がいない等の問題が多くなっています。
立地の良い駅前のマンションなどでは、8割以上が賃借人というマンションもあります。
その人たちがマンション購入者(区分所有者といわれています)でないという理由で管理組合活動から排除してしまうと、マンションの良好な住環境を確保することは難しくなります。
管理組合活動に参加してもらうことで、財産としてのマンションの価値を守ることにもなります。
管理組合は区分所有者の団体ですが、賃借人にも守るべき多くのルールを取り決めています。
一般的な管理規約では、代理人として総会に出席し議決権を行使できるようにしていますし、賃借人が意見を述べることが出来るようにしています。
従って、賃借人の協力がなければ、建物の維持管理は充分に行うことはできません。
管理規約を変更して、賃借人にも居住者として理事会に参加できるよう柔軟な組合運営を考える工夫が必要です。
もちろん、共用部分の変更や建て替え等の区分所有者の基本的な権利に関する事項は除外することは当然のことです。
区分所有法でいうマンションの「管理者」はほとんどのマンションで理事長がなることにしています。
最近では、役員のなり手がいないという理由で管理会社等の外部の第三者に「管理者」の依頼をしようとする考え方があるようです。国もマンションの「新管理者方式」というテーマで議論を開始したようです。
しかし、まずは実際にマンションに住んでいる居住者同士で話し合いが出来る環境づくりが大切ではないでしょうか。
やっと涼しくなったと思いきや、年賀はがきの印刷予約、おせち料理の予約等、きの早いことだ。
立地の良い駅前のマンションなどでは、8割以上が賃借人というマンションもあります。
その人たちがマンション購入者(区分所有者といわれています)でないという理由で管理組合活動から排除してしまうと、マンションの良好な住環境を確保することは難しくなります。
管理組合活動に参加してもらうことで、財産としてのマンションの価値を守ることにもなります。
管理組合は区分所有者の団体ですが、賃借人にも守るべき多くのルールを取り決めています。
一般的な管理規約では、代理人として総会に出席し議決権を行使できるようにしていますし、賃借人が意見を述べることが出来るようにしています。
従って、賃借人の協力がなければ、建物の維持管理は充分に行うことはできません。
管理規約を変更して、賃借人にも居住者として理事会に参加できるよう柔軟な組合運営を考える工夫が必要です。
もちろん、共用部分の変更や建て替え等の区分所有者の基本的な権利に関する事項は除外することは当然のことです。
区分所有法でいうマンションの「管理者」はほとんどのマンションで理事長がなることにしています。
最近では、役員のなり手がいないという理由で管理会社等の外部の第三者に「管理者」の依頼をしようとする考え方があるようです。国もマンションの「新管理者方式」というテーマで議論を開始したようです。
しかし、まずは実際にマンションに住んでいる居住者同士で話し合いが出来る環境づくりが大切ではないでしょうか。
やっと涼しくなったと思いきや、年賀はがきの印刷予約、おせち料理の予約等、きの早いことだ。
Posted by haru at
08:04
│Comments(1)
2007年10月02日
54 マンション法とは?
法律を知らなくても十分生きていけると思う人は適当に読み流してください。
一般的に「マンション法」といわれていますが、正式には「建物の区分所有等に関する法律」のことです。略して「区分所有法」といわれる法律です。
車を運転する人が免許を取得するには必要な「道路交通法」をあまり知らなくても運転しているように、マンション法を知らなくてもマンションに住む事はできますが、少しでも知っておくと無駄なトラブルを防ぎ、安心してマンションに住むことができます。
この法律によると、一棟の建物は一つの物として所有権は一つとするのが原則ですが、一棟の建物に構造上区分されかつ独立して、住居、店舗、事務所、倉庫等、建物の用途に使用する数個の部分があれば、その部分を専有部分と呼び、「区分所有権」の対象とするとあります。
わかりやすく言うと、ある条件を満足すれば一つの建物であってもその一部分を単独で所有し、自由に使用でき、自由に売買できるということです。
そのため、この法律が出来た昭和37年から急速に分譲マンションがつくられるようになりました。
この法律では「区分所有権」をを認めることにより色々な規定を設けています。
分譲マンションは基本的に、この区分して所有する住戸部分の権利と、それ以外の共用する部分の権利と、敷地に対する権利と言う3つの権利があり、これがそろって初めてマンションを所有することができ、これを別々に売買することは出来ないことになっています。
また、マンション購入者は全員で、建物や敷地を維持管理するために管理組合を結成することになっています。
あまり知られていませんが、管理組合の役員等に対する罰則規定があります。
管理規約や総会の議事録の保管をきちんとしなかったり、議事録を作成しなかった場合等「20万以下の過料に処する」と書かれています。
その他、マンションを管理をする上で大切なことが書かれています。
面倒なことですが、少なくとも管理組合の役員になった人は「区分所有法」を一読されることをお勧めいたします。わづか72条ほどの法律ですから、他人の為ではなく自分のために。
10月1日からは「法の日」週間だそうです。法文で頭の体操でもしてみますか。
一般的に「マンション法」といわれていますが、正式には「建物の区分所有等に関する法律」のことです。略して「区分所有法」といわれる法律です。
車を運転する人が免許を取得するには必要な「道路交通法」をあまり知らなくても運転しているように、マンション法を知らなくてもマンションに住む事はできますが、少しでも知っておくと無駄なトラブルを防ぎ、安心してマンションに住むことができます。
この法律によると、一棟の建物は一つの物として所有権は一つとするのが原則ですが、一棟の建物に構造上区分されかつ独立して、住居、店舗、事務所、倉庫等、建物の用途に使用する数個の部分があれば、その部分を専有部分と呼び、「区分所有権」の対象とするとあります。
わかりやすく言うと、ある条件を満足すれば一つの建物であってもその一部分を単独で所有し、自由に使用でき、自由に売買できるということです。
そのため、この法律が出来た昭和37年から急速に分譲マンションがつくられるようになりました。
この法律では「区分所有権」をを認めることにより色々な規定を設けています。
分譲マンションは基本的に、この区分して所有する住戸部分の権利と、それ以外の共用する部分の権利と、敷地に対する権利と言う3つの権利があり、これがそろって初めてマンションを所有することができ、これを別々に売買することは出来ないことになっています。
また、マンション購入者は全員で、建物や敷地を維持管理するために管理組合を結成することになっています。
あまり知られていませんが、管理組合の役員等に対する罰則規定があります。
管理規約や総会の議事録の保管をきちんとしなかったり、議事録を作成しなかった場合等「20万以下の過料に処する」と書かれています。
その他、マンションを管理をする上で大切なことが書かれています。
面倒なことですが、少なくとも管理組合の役員になった人は「区分所有法」を一読されることをお勧めいたします。わづか72条ほどの法律ですから、他人の為ではなく自分のために。
10月1日からは「法の日」週間だそうです。法文で頭の体操でもしてみますか。
Posted by haru at
09:11
│Comments(0)
2007年10月01日
53 望ましいマンション管理会社とは? その5
前回、前々回の話で、同じ総戸数20戸のマンションでも、建物の維持管理をすることにおいて、大きく違うことが想像できると思います。
購入したマンションの誕生した履歴を読み取り、完成したマンションの図面を読み取ることから、今後のマンションの管理方法、それに伴う維持管理費を算出しなければ、適正な、効率の良い管理を継続することは出来ません。
売主から契約時に承諾させられた管理規約や管理会社との契約書は、購入者の為であるより売主の都合が優先されている傾向にあります。
特に、大手といわれる売主やその系列の管理会社は効率の名の下に、その多くはマニュアル化されており、個別のマンションの実態を必ずしも反映されているとはかぎりません。
なるべく早い時期に、公平な第三者の専門的知識を活用して、自分のマンションの管理方法を見直す必要があります。何しろマンションが存在する限り50年、あるいは100年管理を続けなければならないのですから。
その結果を柔軟に受け止め、マンション購入者に納得の出来る説明が出来る管理会社であればいいでしょう。
管理会社が、契約した作業基準どうりの処理をしているか、会計処理は適正か、担当者や管理員の教育をしているか、緊急時の体制は整備されているか、等は当然のことです。
もっとも必要なことは、管理会社自身が、マンションの個別の特殊性を把握し、各種設備の維持管理のための専門的能力と組織力を保持しているかどうかです。
管理会社の現実の組織がどうなっているのか、1級建築士等の建物の専門的知識を保持した社員数が管理を受諾している管理組合数に対応できるほど、実際に存在しているのかを確認することです。
管理会社の事務所をたずねると、ほとんど事務職員だけで技術者は全て外注している、というところが多いので要注意です。
もちろん、マンション購入者全員の団体である管理組合が管理会社等に頼らない自力による管理が可能であれば、それに越したことはありません。
今日から、民営郵政がスタートしました。利用者にとって本当に便利になるかどうかはこれからのようです。
購入したマンションの誕生した履歴を読み取り、完成したマンションの図面を読み取ることから、今後のマンションの管理方法、それに伴う維持管理費を算出しなければ、適正な、効率の良い管理を継続することは出来ません。
売主から契約時に承諾させられた管理規約や管理会社との契約書は、購入者の為であるより売主の都合が優先されている傾向にあります。
特に、大手といわれる売主やその系列の管理会社は効率の名の下に、その多くはマニュアル化されており、個別のマンションの実態を必ずしも反映されているとはかぎりません。
なるべく早い時期に、公平な第三者の専門的知識を活用して、自分のマンションの管理方法を見直す必要があります。何しろマンションが存在する限り50年、あるいは100年管理を続けなければならないのですから。
その結果を柔軟に受け止め、マンション購入者に納得の出来る説明が出来る管理会社であればいいでしょう。
管理会社が、契約した作業基準どうりの処理をしているか、会計処理は適正か、担当者や管理員の教育をしているか、緊急時の体制は整備されているか、等は当然のことです。
もっとも必要なことは、管理会社自身が、マンションの個別の特殊性を把握し、各種設備の維持管理のための専門的能力と組織力を保持しているかどうかです。
管理会社の現実の組織がどうなっているのか、1級建築士等の建物の専門的知識を保持した社員数が管理を受諾している管理組合数に対応できるほど、実際に存在しているのかを確認することです。
管理会社の事務所をたずねると、ほとんど事務職員だけで技術者は全て外注している、というところが多いので要注意です。
もちろん、マンション購入者全員の団体である管理組合が管理会社等に頼らない自力による管理が可能であれば、それに越したことはありません。
今日から、民営郵政がスタートしました。利用者にとって本当に便利になるかどうかはこれからのようです。
Posted by haru at
08:21
│Comments(0)
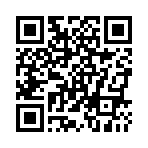
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン







