2007年12月28日
100 マンションライフを快適に!
このブログも、今年の7月からスタートして早くも半年がたち、今回で100回目になりました。
これまで、たくさんのアクセス、ありがとうございました。
マンションは、ほとんどの人にとっては 「人生最大の買い物」 ではないかと思います。
また、偶然の事情から同じ建物に、生まれや育ち、考え方の違う人が集まり、それぞれが独立した所有権を持ちながら、マンションの管理については、基本的には所有者全員が共同して行うという特殊な所有形態となっています。
ところが、購入した価格の大半が他の購入者と共同で所有している部分であるという意識があまりないために、マンション管理に無関心な人が多いのも現実です。
安心して快適な住居として永く住み続ける為には、好むと好まざるとにかかわらず、マンション居住者はマンションコミュニティの一員になるという意識が必要になってきます。
コミュニケーションの本来の意味である 「分かち合う」 という気持ちが大切になってきます。
これからも、マンション居住者の皆さんに「快適なマンションライフ」に役立つ情報を出来るだけわかりやすくお伝えしたいと思います。
皆様からの建設的なコメントをいただければ幸いです。
これまで、たくさんのアクセス、ありがとうございました。
マンションは、ほとんどの人にとっては 「人生最大の買い物」 ではないかと思います。
また、偶然の事情から同じ建物に、生まれや育ち、考え方の違う人が集まり、それぞれが独立した所有権を持ちながら、マンションの管理については、基本的には所有者全員が共同して行うという特殊な所有形態となっています。
ところが、購入した価格の大半が他の購入者と共同で所有している部分であるという意識があまりないために、マンション管理に無関心な人が多いのも現実です。
安心して快適な住居として永く住み続ける為には、好むと好まざるとにかかわらず、マンション居住者はマンションコミュニティの一員になるという意識が必要になってきます。
コミュニケーションの本来の意味である 「分かち合う」 という気持ちが大切になってきます。
これからも、マンション居住者の皆さんに「快適なマンションライフ」に役立つ情報を出来るだけわかりやすくお伝えしたいと思います。
皆様からの建設的なコメントをいただければ幸いです。
Posted by haru at
07:40
│Comments(2)
2007年12月26日
99 最近のマンション管理の現状は? その8
個々のマンションは一般的に閉鎖的です。さらにセキュリティの強化は外部者を拒否しがちです。
近隣に沢山のマンションがあっても、管理組合の役員同士が情報を交換し合うことはあまりされていません。
しかし、マンションにはどこでも共通の課題や共通の管理内容が数多くあります。
一般的にマンションで問題が発生したときは、次のような方法で対応されているのではないかと思われます。
☆ マンション内で対応・・・・管理員に相談、管理会社の担当者に相談、理事会、専門委員会等で検討 等
☆ 外部の専門機関に相談・・・・自治体の相談窓口、 管理組合の団体、 マンションの管理業協会、 マンション管理士会 等
外部の相談機関は一般的な回答が多く、あくまでも参考意見にすぎないようです。
そこで、地域にあるマンションが連合し、共通の課題を解決する仕組みを作ることは、これからのマンション管理を効果的に進める上からも必要ではないかと思われます。
マンション交流会等の名目で情報交換が実施されている地区もあるようですが、さらに発展させて、管理会社やエレベーター点検等の維持管理をする業者の比較をすることで、共通の優良業者を見つけること等が可能です。
また、マンショントラブルの定番である、上下階の騒音紛争やペット飼育紛争等、地域のマンションが共同して対応を考えることは、費用対効果を考えても、居住者の合意を得やすいと思います
地域とのコミュニティを考慮していくことは重要なことであり、他のマンションと情報交換をすることはマンションの価値を高める上からも、必要なことです。
又、これからのマンション問題は次のような地域全体の課題と連動して来るものと思われます。
高齢者の支援、 子育ての支援、 防犯・防災対策、 環境対策 等々
これらの問題の解決には、行政や地域社会、その他の専門家等とのネットワークが必要になってきます。管理組合の内部だけに目を向けるのではなくて、地域のほかのマンションや地域社会と連携することのほうが、より効果的な情報を手に入れることが出来るし、結果的にマンションの価値を高めることになるものと思います。
今年もあとわずかです。気持ちだけがあわただしくなっています。
近隣に沢山のマンションがあっても、管理組合の役員同士が情報を交換し合うことはあまりされていません。
しかし、マンションにはどこでも共通の課題や共通の管理内容が数多くあります。
一般的にマンションで問題が発生したときは、次のような方法で対応されているのではないかと思われます。
☆ マンション内で対応・・・・管理員に相談、管理会社の担当者に相談、理事会、専門委員会等で検討 等
☆ 外部の専門機関に相談・・・・自治体の相談窓口、 管理組合の団体、 マンションの管理業協会、 マンション管理士会 等
外部の相談機関は一般的な回答が多く、あくまでも参考意見にすぎないようです。
そこで、地域にあるマンションが連合し、共通の課題を解決する仕組みを作ることは、これからのマンション管理を効果的に進める上からも必要ではないかと思われます。
マンション交流会等の名目で情報交換が実施されている地区もあるようですが、さらに発展させて、管理会社やエレベーター点検等の維持管理をする業者の比較をすることで、共通の優良業者を見つけること等が可能です。
また、マンショントラブルの定番である、上下階の騒音紛争やペット飼育紛争等、地域のマンションが共同して対応を考えることは、費用対効果を考えても、居住者の合意を得やすいと思います
地域とのコミュニティを考慮していくことは重要なことであり、他のマンションと情報交換をすることはマンションの価値を高める上からも、必要なことです。
又、これからのマンション問題は次のような地域全体の課題と連動して来るものと思われます。
高齢者の支援、 子育ての支援、 防犯・防災対策、 環境対策 等々
これらの問題の解決には、行政や地域社会、その他の専門家等とのネットワークが必要になってきます。管理組合の内部だけに目を向けるのではなくて、地域のほかのマンションや地域社会と連携することのほうが、より効果的な情報を手に入れることが出来るし、結果的にマンションの価値を高めることになるものと思います。
今年もあとわずかです。気持ちだけがあわただしくなっています。
Posted by haru at
09:07
│Comments(0)
2007年12月25日
98 最近のマンション管理の現状は? その7
マンション管理をスムーズに運営していく為には、良好なコミュニティが必要です。
そのためには、マンション居住者がお互いにコミュニケーションが取れる関係になることことだといわれています。
しかし、マンション居住者は他者との「コミュニケーション」を求めて居住しているのでしょうか。どんな場合でもそれを維持したいと思っているでしょうか。正直なところ 「窮屈でわずらわしい」 とか 「他人は他人、自分は自分」 と心の片隅で感じているのではないでしょうか。本当にコミュニケーションを望んでいる人がどれほどいるのでしょうか。
鍵一つで、他人とのわずらわしさから逃れるためにマンション生活を望んでいる人もいるかもしれません。
あるいは、個人の生活には踏み込まれたくないけれども、気持ちよく、安心して暮らす為には適度な関係は維持しておきたいと思っている人は多いと思います。
同じ建物の中で壁や床、天井で仕切られただけの近隣と何年も話しさえしたことがない関係というのは、どう考えても不自然であり、リスクを抱えた環境に違いありません。
マンションという資産を共有している者同志が、お互いにどういう人なのかを知らないというのは不思議なことです。
そこで、コミュニケーションをとることが苦手な人やきっかけがつかめない人に対しての仕掛けが必要です。
マンションのコミュニティを良くするために一般的には次のようなことが行われています。
☆ 各種イベント(お祭り、餅つき、クリスマス会、防災訓練、懇親会、等)
☆ 情報の伝達(広報紙の発行、掲示板の利用、等)
☆ サークル活動(ゴルフ、囲碁・将棋、ガーデニング、子ども会、カラオケ、手芸、育児、ペット等)
☆ ボランティア(マンション内の清掃、防犯パトロール、廃品回収、等)
管理組合の本来の目的である、建物の維持管理とは直接には関係ないと感じている人も多いと思います。そのために管理費を納めているのではないと反論して、参加を拒否する人もいても不思議ではありません。
コミュニティを重視しすぎると、任意参加の自治会なのか強制参加の管理組合なのか目的が曖昧になってきます。結果として居住者の合意形成が難しくなります。
それをどうバランスをとっていくのかが快適なマンションライフの決め手になりそうです。
「足音がうるさい」とマンションで又、傷害事件が発生しました。マンションに住む為のマナーとは?
そのためには、マンション居住者がお互いにコミュニケーションが取れる関係になることことだといわれています。
しかし、マンション居住者は他者との「コミュニケーション」を求めて居住しているのでしょうか。どんな場合でもそれを維持したいと思っているでしょうか。正直なところ 「窮屈でわずらわしい」 とか 「他人は他人、自分は自分」 と心の片隅で感じているのではないでしょうか。本当にコミュニケーションを望んでいる人がどれほどいるのでしょうか。
鍵一つで、他人とのわずらわしさから逃れるためにマンション生活を望んでいる人もいるかもしれません。
あるいは、個人の生活には踏み込まれたくないけれども、気持ちよく、安心して暮らす為には適度な関係は維持しておきたいと思っている人は多いと思います。
同じ建物の中で壁や床、天井で仕切られただけの近隣と何年も話しさえしたことがない関係というのは、どう考えても不自然であり、リスクを抱えた環境に違いありません。
マンションという資産を共有している者同志が、お互いにどういう人なのかを知らないというのは不思議なことです。
そこで、コミュニケーションをとることが苦手な人やきっかけがつかめない人に対しての仕掛けが必要です。
マンションのコミュニティを良くするために一般的には次のようなことが行われています。
☆ 各種イベント(お祭り、餅つき、クリスマス会、防災訓練、懇親会、等)
☆ 情報の伝達(広報紙の発行、掲示板の利用、等)
☆ サークル活動(ゴルフ、囲碁・将棋、ガーデニング、子ども会、カラオケ、手芸、育児、ペット等)
☆ ボランティア(マンション内の清掃、防犯パトロール、廃品回収、等)
管理組合の本来の目的である、建物の維持管理とは直接には関係ないと感じている人も多いと思います。そのために管理費を納めているのではないと反論して、参加を拒否する人もいても不思議ではありません。
コミュニティを重視しすぎると、任意参加の自治会なのか強制参加の管理組合なのか目的が曖昧になってきます。結果として居住者の合意形成が難しくなります。
それをどうバランスをとっていくのかが快適なマンションライフの決め手になりそうです。
「足音がうるさい」とマンションで又、傷害事件が発生しました。マンションに住む為のマナーとは?
Posted by haru at
08:29
│Comments(0)
2007年12月22日
97 最近のマンション管理の現状は? その6
管理組合運営で重要なことは、居住者間のコミュニケーションに配慮し、民主的な管理組合運営に心がけることが大切です。
そのためには、出来るだけ多くの組合員が話し合いに参加することです。
しかし、多様な生活習慣を持ち、考え方や年齢の違う人が集まって話し合いをすることは、そう簡単なことではありません。
特に、マンション管理に関心や知識を持つ人と無関心な人の話し合いは意見の対立が顕著になりやすい傾向にあります。
ところで、マンション居住者の中には、企業活動の過程で話し合いの訓練を経験した人は多いと思います。
このところあまり聞かれなくなりましたが、昭和50年~60年代にかけて多くの企業がTGC活動(全社的品質管理活動)というものに競うように取り組んでいました。
その過程で、親和図法(KJ法)という手法を学ばれたと思います。
これは多くの断片的な情報を統合して、創造的なアイデアを生み出したり、問題解決の糸口を探っていくための道具として使用されていたものです。
企業活動の延長になるようなことを、私生活である管理組合へ持ち込むことに抵抗を感じられるかもしれません。
沢山の居住者が共同して暮らすということは、価値観の相違や優先順位の違いがどうしても発生するのは仕方のないことです。
そこに、話し合いの整理をするための道具を参考にして活用することは、企業内で経験された人にとっては、そう難しいことではないと思います。
また、最近では話し合いを効果的に進めるための道具として、紛争を抱えた人同士がお互いの解決方法を見つけ出し、話し合いの交通整理をする 「メディエーション」 とか、 理事会等の会議の場で話し合いを促したり、話の流れを整理して、参加者の相互理解を促進し、合意形成へ導く手法としての 「ファシリテーション」 とかを活用しようとする動きも出ています。
これらの手法の担い手である「メディエーター」や「ファシリテーター」といわれる人はまだ少ないようですが、考え方は日常の話し合いで活用できる要素があると思います。
まだ、聴きなれない言葉ですが、興味のある方は一度、調べて見られてはどうでしょうか。
コミュニケーションの基本は話を聞くこと。 反対意見を持つ人の顔を見て聞くことだといわれています。
効果的な話し合いをするために少しづつでも参考になる道具を使ってみてはどうでしょう。道具を使いこなせる信頼できる人はマンションの内部にもきっといるはずです。
残業代を支払しなくてもいい管理職を増やす企業があるようです。従業員の幸せとは?・・・
そのためには、出来るだけ多くの組合員が話し合いに参加することです。
しかし、多様な生活習慣を持ち、考え方や年齢の違う人が集まって話し合いをすることは、そう簡単なことではありません。
特に、マンション管理に関心や知識を持つ人と無関心な人の話し合いは意見の対立が顕著になりやすい傾向にあります。
ところで、マンション居住者の中には、企業活動の過程で話し合いの訓練を経験した人は多いと思います。
このところあまり聞かれなくなりましたが、昭和50年~60年代にかけて多くの企業がTGC活動(全社的品質管理活動)というものに競うように取り組んでいました。
その過程で、親和図法(KJ法)という手法を学ばれたと思います。
これは多くの断片的な情報を統合して、創造的なアイデアを生み出したり、問題解決の糸口を探っていくための道具として使用されていたものです。
企業活動の延長になるようなことを、私生活である管理組合へ持ち込むことに抵抗を感じられるかもしれません。
沢山の居住者が共同して暮らすということは、価値観の相違や優先順位の違いがどうしても発生するのは仕方のないことです。
そこに、話し合いの整理をするための道具を参考にして活用することは、企業内で経験された人にとっては、そう難しいことではないと思います。
また、最近では話し合いを効果的に進めるための道具として、紛争を抱えた人同士がお互いの解決方法を見つけ出し、話し合いの交通整理をする 「メディエーション」 とか、 理事会等の会議の場で話し合いを促したり、話の流れを整理して、参加者の相互理解を促進し、合意形成へ導く手法としての 「ファシリテーション」 とかを活用しようとする動きも出ています。
これらの手法の担い手である「メディエーター」や「ファシリテーター」といわれる人はまだ少ないようですが、考え方は日常の話し合いで活用できる要素があると思います。
まだ、聴きなれない言葉ですが、興味のある方は一度、調べて見られてはどうでしょうか。
コミュニケーションの基本は話を聞くこと。 反対意見を持つ人の顔を見て聞くことだといわれています。
効果的な話し合いをするために少しづつでも参考になる道具を使ってみてはどうでしょう。道具を使いこなせる信頼できる人はマンションの内部にもきっといるはずです。
残業代を支払しなくてもいい管理職を増やす企業があるようです。従業員の幸せとは?・・・
Posted by haru at
08:49
│Comments(0)
2007年12月19日
96 最近のマンション管理の現状は? その5
「マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合である」
これは、平成13年に国から告示された「マンションの管理の適正化に関する指針」の一文です。
国から言われるまでもなく、マンション居住者の中には、自発的にこの意味に気づいてきた人が現れてきています。
しかし、マンション居住者には、長い間、管理会社への依存体質が身についています。具体的にどう行動したらよいのか明快な答えが見つからなくて、暗中模索の状態が続いています。
管理組合の管理の対象は、建物だけの物的側面だけではなく、マンション居住者間や外部の存在である管理会社、分譲会社、建設会社、あるいは地域社会等の人的側面があります。
つまり、管理組合はマンションに関するありとあらゆることに関係しています。
そこで、管理組合が主体的に行動するには具体的にどうすればよいのでしょうか。
管理組合を動かすのは組合員です。一つの考え方として、マンション管理の運営に「まちづくり」の概念を取り入れてみたらどうでしょう。
たとえば、100戸のマンションには200人から300人が暮らしています。ある意味では一つの「まち」です。大きな団地は一つの街区に相当します。
「まちづくり」をうまく進めるには「5人の馬鹿がいる」と言われています。
☆ 発想力のある知恵者
☆ すぐに同調して乗りやすい人
☆ 少し別な角度から批判する目を持つ人
☆ 働くことを厭わない人
☆ 雰囲気を楽しくさせる人
幸い、マンションに住む人は特定な人々の集団ではありません。色々な人が集まっています。お互いに知らないだけです。人的資源の宝庫かもしれません。
マンションの将来の姿をどうしたいのか、夢を話してみましょう。禁止事項を話し合うのではなく
楽しくなるような話をして見ましょう。マンション居住者全員が参加できることを話し合ってみましょう。
「まちづくり」に終わりはありません。マンションも建て替えをすれば、又、新しい「まち」に生まれ変わります。
これまでの輪番制による理事会運営を中心とした管理方法では、いつまでたっても、管理組合が主体的にマンションを管理し続けていくことは難しいのではないかと思います。
農水省が全国の郷土料理百選を発表。ふるさと広島の「カキの土手鍋」「あなご飯」も、なるほど、確かにおいしい。
これは、平成13年に国から告示された「マンションの管理の適正化に関する指針」の一文です。
国から言われるまでもなく、マンション居住者の中には、自発的にこの意味に気づいてきた人が現れてきています。
しかし、マンション居住者には、長い間、管理会社への依存体質が身についています。具体的にどう行動したらよいのか明快な答えが見つからなくて、暗中模索の状態が続いています。
管理組合の管理の対象は、建物だけの物的側面だけではなく、マンション居住者間や外部の存在である管理会社、分譲会社、建設会社、あるいは地域社会等の人的側面があります。
つまり、管理組合はマンションに関するありとあらゆることに関係しています。
そこで、管理組合が主体的に行動するには具体的にどうすればよいのでしょうか。
管理組合を動かすのは組合員です。一つの考え方として、マンション管理の運営に「まちづくり」の概念を取り入れてみたらどうでしょう。
たとえば、100戸のマンションには200人から300人が暮らしています。ある意味では一つの「まち」です。大きな団地は一つの街区に相当します。
「まちづくり」をうまく進めるには「5人の馬鹿がいる」と言われています。
☆ 発想力のある知恵者
☆ すぐに同調して乗りやすい人
☆ 少し別な角度から批判する目を持つ人
☆ 働くことを厭わない人
☆ 雰囲気を楽しくさせる人
幸い、マンションに住む人は特定な人々の集団ではありません。色々な人が集まっています。お互いに知らないだけです。人的資源の宝庫かもしれません。
マンションの将来の姿をどうしたいのか、夢を話してみましょう。禁止事項を話し合うのではなく
楽しくなるような話をして見ましょう。マンション居住者全員が参加できることを話し合ってみましょう。
「まちづくり」に終わりはありません。マンションも建て替えをすれば、又、新しい「まち」に生まれ変わります。
これまでの輪番制による理事会運営を中心とした管理方法では、いつまでたっても、管理組合が主体的にマンションを管理し続けていくことは難しいのではないかと思います。
農水省が全国の郷土料理百選を発表。ふるさと広島の「カキの土手鍋」「あなご飯」も、なるほど、確かにおいしい。
Posted by haru at
08:28
│Comments(0)
2007年12月17日
95 最近のマンション管理の現状は? その4
マンション管理に関心を持ち始めた管理組合役員からの質問です。
「マンション内でのトラブルを防ぐには、管理組合として日頃どのようなことに注意すればよいのでしょうか。」
一般的な回答は次のようなものです。
「管理組合の役員一人ひとりが管理規約などの理解を深め、時には専門家の意見も聞いたりしながら、問題になりそうなことについては、できるだけ早めに管理規約を改正するなどして紛争の予防を図ることが大切です。
そのためには良好なコミュニティがベースとして必要である。」
現実の管理組合の役員はどうでしょうか。
国が参考にと公表した「マンション標準管理規約」には 「役員は、法令、規約等並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行する。」と記してあります。
これでは、ふなれな役員には、具体的に何をすればよいのか誰も分かりません。
分かっているはずの専門家である管理会社の担当者は余り積極的に説明をしません。特に居住者間の紛争に関しては、余計なことは出来るだけしないというのが管理会社の一般的な姿勢のようです。
管理組合の役員は特別な人ではありません。順番で回ってきただけの区分所有者です。
任期はほとんどが1年、あるいは、せいぜい2年です。
それも、月に一度程度、理事会に出席して、管理会社の報告を聞くだけで、終わることが多いと思います。管理規約、ましてや区分所有法等を読んで理事会に参加する人はまれでしょう。
管理組合の役員は何をすべきなのか誰も教えてはくれません。トラブルが発生するまでは、余計なことはしない方が、お互いに楽に生活ができるという暗黙の意識が働いているのかもしれません。
仮にトラブルが発生しても、居住者間の問題に関しては いわゆる専門家という人は見つけるほうが困難です。
これが、今までの管理組合の平均像ではないでしょうか。
しかし、自分たちで快適な居住環境を維持する為に努力を始めた管理組合が、確実に増えてきています。
未だに良く分からない「消えた年金」。何が消えたのか? まさか・・・
「マンション内でのトラブルを防ぐには、管理組合として日頃どのようなことに注意すればよいのでしょうか。」
一般的な回答は次のようなものです。
「管理組合の役員一人ひとりが管理規約などの理解を深め、時には専門家の意見も聞いたりしながら、問題になりそうなことについては、できるだけ早めに管理規約を改正するなどして紛争の予防を図ることが大切です。
そのためには良好なコミュニティがベースとして必要である。」
現実の管理組合の役員はどうでしょうか。
国が参考にと公表した「マンション標準管理規約」には 「役員は、法令、規約等並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行する。」と記してあります。
これでは、ふなれな役員には、具体的に何をすればよいのか誰も分かりません。
分かっているはずの専門家である管理会社の担当者は余り積極的に説明をしません。特に居住者間の紛争に関しては、余計なことは出来るだけしないというのが管理会社の一般的な姿勢のようです。
管理組合の役員は特別な人ではありません。順番で回ってきただけの区分所有者です。
任期はほとんどが1年、あるいは、せいぜい2年です。
それも、月に一度程度、理事会に出席して、管理会社の報告を聞くだけで、終わることが多いと思います。管理規約、ましてや区分所有法等を読んで理事会に参加する人はまれでしょう。
管理組合の役員は何をすべきなのか誰も教えてはくれません。トラブルが発生するまでは、余計なことはしない方が、お互いに楽に生活ができるという暗黙の意識が働いているのかもしれません。
仮にトラブルが発生しても、居住者間の問題に関しては いわゆる専門家という人は見つけるほうが困難です。
これが、今までの管理組合の平均像ではないでしょうか。
しかし、自分たちで快適な居住環境を維持する為に努力を始めた管理組合が、確実に増えてきています。
未だに良く分からない「消えた年金」。何が消えたのか? まさか・・・
Posted by haru at
09:01
│Comments(0)
2007年12月14日
94 最近のマンション管理の現状は? その3
マンション居住者にマンション管理に関心や知識を持つ人と無関心な人と二極化の傾向にあるようです。このことを含め、現状ではどのような問題が発生しているのでしょうか。
国が「マンション管理適正化推進センター」として指定した機関である「(財)マンション管理センター」から次のような事例が増えたと報告されています。
☆ 管理組合と居住者との紛争
管理組合に対する居住者の不満や居住者の管理規約違反等
☆ 居住者間の紛争
音の被害を受ける側と音を発している側、双方からの上下階の騒音やペット飼育に関するもの等
☆ 組合役員相互間の紛争
理事長と他の理事、理事会と専門委員会、住宅部会と店舗部会の紛争等
この外にも、団地型マンションにおける棟間でのトラブル、賃借人と区分所有者間のトラブル、大規模なマンションでのマンション内部の自治会と管理組合とのトラブル等も発生しています。
いずれも居住者間の問題であり、原因は単純ではないようです。
管理組合の運営は話し合いで全員が合意することが理想ですが、現実はその通りには行きません。
少しばかり法律を勉強した人や海外生活を経験した人等のなかには、すぐに、法的手段で解決を図ろうとする人がいるようですが、費用と労力や時間がかかるわりには結果は誰も得をしないことが多いようです。
快適なマンションライフをすごすには、どの様な解決方法があるのか、考えてみたいと思います。
もう12月も中旬になりました。年賀はがきを購入したのは早かったのですが・・・
国が「マンション管理適正化推進センター」として指定した機関である「(財)マンション管理センター」から次のような事例が増えたと報告されています。
☆ 管理組合と居住者との紛争
管理組合に対する居住者の不満や居住者の管理規約違反等
☆ 居住者間の紛争
音の被害を受ける側と音を発している側、双方からの上下階の騒音やペット飼育に関するもの等
☆ 組合役員相互間の紛争
理事長と他の理事、理事会と専門委員会、住宅部会と店舗部会の紛争等
この外にも、団地型マンションにおける棟間でのトラブル、賃借人と区分所有者間のトラブル、大規模なマンションでのマンション内部の自治会と管理組合とのトラブル等も発生しています。
いずれも居住者間の問題であり、原因は単純ではないようです。
管理組合の運営は話し合いで全員が合意することが理想ですが、現実はその通りには行きません。
少しばかり法律を勉強した人や海外生活を経験した人等のなかには、すぐに、法的手段で解決を図ろうとする人がいるようですが、費用と労力や時間がかかるわりには結果は誰も得をしないことが多いようです。
快適なマンションライフをすごすには、どの様な解決方法があるのか、考えてみたいと思います。
もう12月も中旬になりました。年賀はがきを購入したのは早かったのですが・・・
Posted by haru at
07:59
│Comments(0)
2007年12月13日
93 最近のマンション管理の現状は? その2
マンション居住者の年齢構成や所帯人数等に変化が現れています。
所帯主の高齢化や所帯人数の減少が進んでいます。所帯主が50歳代以上、一人又は二人所帯が共に居住者の約6割りになるそうです。
これは、統計上の平均ですからこの割合がさらに高いマンションがあることは容易に想像できます。
マンションを終の棲家と考える高齢夫婦、高齢一人暮らしの人が増加しています。これは、暮らしやすさから、高齢になってからマンションに移り住む人も増加していることも起因しているようです。
さらに、マンション居住者の60歳代以上の現在のマンションに対する永住意識は、7割以上の人が考えているそうです。
入居当時は鍵一つで気楽に住める居住形態であると思っている人は多いでしょう。マンションの共用部分に関しては他人任せで、専有部分さえ問題なければ良いとし、自分の仕事を優先して来たと思います。
その結果として永い間マンションの管理に無関心できたことも事実でしょう。
意識するしないに係らず多くのマンションで一般的に次のような問題を抱えています。
☆ 外壁、屋上、給排水管からの漏水等を基本とした建物の維持管理に関すること。
☆ ぺットや騒音等の居住者間の迷惑行為に関すること。
☆ 管理費・積立金等の徴収・滞納あるいは規約、修繕計画、駐車場、理事会等の組合運営に関すること。
☆ 管理を委託している管理会社に関すること等 様々です。
時間に余裕の出来た高齢者がこのような問題に関心を持つようになり、独自で勉強をする人も増えてきました。
もちろん、近年マンションの管理に関する法律改正や新しい法律の制定が関係していることも影響していると思います。
しかし、マンション管理に関心や知識を持つ居住者が増えたことにより、考え方に対立が生じ、新たなトラブルの原因となるマンションも増えています。
マンションの各住戸にビラを配布した人が逆転有罪判決。毎日、新聞に入ってくる沢山のチラシは???
所帯主の高齢化や所帯人数の減少が進んでいます。所帯主が50歳代以上、一人又は二人所帯が共に居住者の約6割りになるそうです。
これは、統計上の平均ですからこの割合がさらに高いマンションがあることは容易に想像できます。
マンションを終の棲家と考える高齢夫婦、高齢一人暮らしの人が増加しています。これは、暮らしやすさから、高齢になってからマンションに移り住む人も増加していることも起因しているようです。
さらに、マンション居住者の60歳代以上の現在のマンションに対する永住意識は、7割以上の人が考えているそうです。
入居当時は鍵一つで気楽に住める居住形態であると思っている人は多いでしょう。マンションの共用部分に関しては他人任せで、専有部分さえ問題なければ良いとし、自分の仕事を優先して来たと思います。
その結果として永い間マンションの管理に無関心できたことも事実でしょう。
意識するしないに係らず多くのマンションで一般的に次のような問題を抱えています。
☆ 外壁、屋上、給排水管からの漏水等を基本とした建物の維持管理に関すること。
☆ ぺットや騒音等の居住者間の迷惑行為に関すること。
☆ 管理費・積立金等の徴収・滞納あるいは規約、修繕計画、駐車場、理事会等の組合運営に関すること。
☆ 管理を委託している管理会社に関すること等 様々です。
時間に余裕の出来た高齢者がこのような問題に関心を持つようになり、独自で勉強をする人も増えてきました。
もちろん、近年マンションの管理に関する法律改正や新しい法律の制定が関係していることも影響していると思います。
しかし、マンション管理に関心や知識を持つ居住者が増えたことにより、考え方に対立が生じ、新たなトラブルの原因となるマンションも増えています。
マンションの各住戸にビラを配布した人が逆転有罪判決。毎日、新聞に入ってくる沢山のチラシは???
Posted by haru at
11:38
│Comments(0)
2007年12月12日
92 最近のマンション管理の現状は? その1
マンションのストック戸数は平成18年末時点で約505万戸、居住人口は約1,300万人と言われています。
居住人口は、一所帯当たり平均人員2.6人(平成17年国勢調査を参考)として計算してあります。
この10年間は毎年17万戸~20万戸のマンションが新たに供給されています。
4年後の平成23年には築30年以上のマンションが100万戸を越すと言われています。
ということは、新耐震設計法の制定前(昭和56年から新制度開始)に完成したマンションが100万戸以上存在していることになります。
昭和56年以後は「建物は硬くつくればいい」という考え方から「硬いだけではだめで建物は多少壊れても人命は助かる」という考えに基づく構造計算方法に変わってきました。
関東大震災クラスの地震でも、重大な被害・崩壊がないこと、あるいは修理をすれば建物を再利用できるという基準に改正されました。
言い換えると、耐震強度が2年前に発覚した耐震偽装事件並みの建物が100万戸以上存在する可能性があると言うことになります。
しかし、昭和56年以前の旧耐震基準でつくられたからと言って、全ての建物が耐震性能が劣っているわけではありません。
4.5階建ての中層の鉄筋コンクリート造、壁式構造、PC工法等で造られた建物は壁量が多い為に旧耐震設計でも耐震性が高いものもあるようです。また、耐震診断の結果、問題なしとされた建物もあります。
いずれにしても、旧耐震設計の建物は耐震診断をして、安全を確認する必要があるようです。
現実には、耐震診断後の本格的な耐震改修工事は、多額の費用負担や居住者に影響がある住戸とない住戸が生ずる等、居住者の合意形成の困難さからあまり進んではいないようですが。
近くの、街路樹が電飾され、サンタクロースが住居の壁面をよじ登っています。これで粉雪でも降れば・・・・。
居住人口は、一所帯当たり平均人員2.6人(平成17年国勢調査を参考)として計算してあります。
この10年間は毎年17万戸~20万戸のマンションが新たに供給されています。
4年後の平成23年には築30年以上のマンションが100万戸を越すと言われています。
ということは、新耐震設計法の制定前(昭和56年から新制度開始)に完成したマンションが100万戸以上存在していることになります。
昭和56年以後は「建物は硬くつくればいい」という考え方から「硬いだけではだめで建物は多少壊れても人命は助かる」という考えに基づく構造計算方法に変わってきました。
関東大震災クラスの地震でも、重大な被害・崩壊がないこと、あるいは修理をすれば建物を再利用できるという基準に改正されました。
言い換えると、耐震強度が2年前に発覚した耐震偽装事件並みの建物が100万戸以上存在する可能性があると言うことになります。
しかし、昭和56年以前の旧耐震基準でつくられたからと言って、全ての建物が耐震性能が劣っているわけではありません。
4.5階建ての中層の鉄筋コンクリート造、壁式構造、PC工法等で造られた建物は壁量が多い為に旧耐震設計でも耐震性が高いものもあるようです。また、耐震診断の結果、問題なしとされた建物もあります。
いずれにしても、旧耐震設計の建物は耐震診断をして、安全を確認する必要があるようです。
現実には、耐震診断後の本格的な耐震改修工事は、多額の費用負担や居住者に影響がある住戸とない住戸が生ずる等、居住者の合意形成の困難さからあまり進んではいないようですが。
近くの、街路樹が電飾され、サンタクロースが住居の壁面をよじ登っています。これで粉雪でも降れば・・・・。
Posted by haru at
08:07
│Comments(0)
2007年12月10日
91 マンションの「建物の維持管理」、責任者は誰? その10
当ブログ、タイトル85で説明しましたが、マンションの管理対象は大きく4項目あります。
その一つは建物の骨組みである構造躯体です。これに関しては、施工段階で基本的な性能は決まる話をしてきました。
しかし、そのまま放置すれば、コンクリートの表面からの経年劣化は進行します。
それを防ぐには管理対象の2項目の構造躯体を保護する仕上げ材が適正に維持管理されることが必要です。
一般的に大規模修繕の対象となる屋根、バルコニー、共用ローカ等の防水、あるいは外壁の仕上げ等に関するもののことです。
この部分も、マンションが完成した時点で、使用されている材料や施工方法により、様々ですが、その後の維持管理の時期、内容、費用等が想定できます。
それらを各マンション毎に具体的に表現したものが「建物の長期修繕計画」と呼ばれるものです。これには管理対象の第3項目の設備関係、第4項目の外構関係も当然含まれます。
マンションの事業主は販売する時点で、このマンションはどのような材料でどのように造られているかを正しく公表し、建物に固有の維持管理項目を購入者に正しく理解させる責任があると思います。
それには、マンション事業主自らが実施した、完成した建物の「調査診断書」をマンション購入者に提供することです。それが、建物の具体的な品質を保証することではないかと思います。
マンション購入者が立地条件や居住部分の広さ、表面的な仕上げ材、設備等だけにこだわり、本当に永住する為に、価値ある建物か、に意識を向けない限り、いつまでも、マンション事業者の「販売が済めば、後は管理会社が対応します」と言う安易な言葉にごまかされることになります。
低コストで造られたマンションを購入して、多額の維持管理費を払い続けるのか、あるいは従来の多くの人が考えてきた、新しいマンションに住み替え続けていくという方法を選ぶのか、あるいは多少建設コストが高くても、安心してすみ続けることができるマンションを選ぶのか。
マンション居住者が何に価値を求めるのかによって、マンションの「建物の維持管理」の責任の所在は変わる要素を含んでいるようです。
灯油の値上がりで湯たんぽや綿入れはんてんが売れているそうです。ホッとする暖かさを感じるものです。
その一つは建物の骨組みである構造躯体です。これに関しては、施工段階で基本的な性能は決まる話をしてきました。
しかし、そのまま放置すれば、コンクリートの表面からの経年劣化は進行します。
それを防ぐには管理対象の2項目の構造躯体を保護する仕上げ材が適正に維持管理されることが必要です。
一般的に大規模修繕の対象となる屋根、バルコニー、共用ローカ等の防水、あるいは外壁の仕上げ等に関するもののことです。
この部分も、マンションが完成した時点で、使用されている材料や施工方法により、様々ですが、その後の維持管理の時期、内容、費用等が想定できます。
それらを各マンション毎に具体的に表現したものが「建物の長期修繕計画」と呼ばれるものです。これには管理対象の第3項目の設備関係、第4項目の外構関係も当然含まれます。
マンションの事業主は販売する時点で、このマンションはどのような材料でどのように造られているかを正しく公表し、建物に固有の維持管理項目を購入者に正しく理解させる責任があると思います。
それには、マンション事業主自らが実施した、完成した建物の「調査診断書」をマンション購入者に提供することです。それが、建物の具体的な品質を保証することではないかと思います。
マンション購入者が立地条件や居住部分の広さ、表面的な仕上げ材、設備等だけにこだわり、本当に永住する為に、価値ある建物か、に意識を向けない限り、いつまでも、マンション事業者の「販売が済めば、後は管理会社が対応します」と言う安易な言葉にごまかされることになります。
低コストで造られたマンションを購入して、多額の維持管理費を払い続けるのか、あるいは従来の多くの人が考えてきた、新しいマンションに住み替え続けていくという方法を選ぶのか、あるいは多少建設コストが高くても、安心してすみ続けることができるマンションを選ぶのか。
マンション居住者が何に価値を求めるのかによって、マンションの「建物の維持管理」の責任の所在は変わる要素を含んでいるようです。
灯油の値上がりで湯たんぽや綿入れはんてんが売れているそうです。ホッとする暖かさを感じるものです。
Posted by haru at
07:56
│Comments(0)
2007年12月07日
90 マンションの「建物の維持管理」、責任者は誰? その9
マンションの骨組みとなる構造躯体を丈夫に造るには、以下のような基本的な条件が必要です。
もちろん、設計が建築基準法に基づき適法にされていることが前提です。
構造は一般的に使用されている「鉄筋コンクリート」とします。
1) 主要材料の生コンクリート(まだ固まっていないコンクリート)、鉄筋材等、適正な材料が使用されている。
2) 鉄筋の径、量、ピッチ等が適正に配筋されている。
3) 型枠(コンクリートを流し込む鋳型のようなもの)が堅固に精度良く組み立てられている。
4) コンクリートが緻密に隙間なく型枠内に流し込まれている。
5) コンクリートの強度が出るまで十分に養生期間が保たれている。
以上は一つでも不十分な項目があると、丈夫な構造体は出来ません。
基本的には建設会社の管理体制と下請け業者との信頼関係が大切であることはもちろんです。
しかし、マンション購入者はこれらのことを確認することはできません。
コンクリートにひび割れが出来てからは遅いのです。補修程度では解決できないのです。
マンションの事業主に全てのプロセスが確実に施工されているかを確認する責任があります。
マンション購入者は構造体が丈夫に出来ていることが前提でその後のマンションの維持管理をしながら安心して住み続けることが出来るのです。
「実績のある大手の企業だから安心です。」という単純な言葉は必要ありません。
構造躯体に10年間程度の保証は必要ないのです。何十年もの間、安心して住み続けたいのです。丈夫な骨組みが確実に造られていると言う証明・証拠がほしいのです。
それが出来ないマンションの事業主はマンションという社会資本を販売する資格はないと思います。
救急患者が16病院受け入れ拒否で死亡。平常時に病院との付き合いを良くしておこうか。
もちろん、設計が建築基準法に基づき適法にされていることが前提です。
構造は一般的に使用されている「鉄筋コンクリート」とします。
1) 主要材料の生コンクリート(まだ固まっていないコンクリート)、鉄筋材等、適正な材料が使用されている。
2) 鉄筋の径、量、ピッチ等が適正に配筋されている。
3) 型枠(コンクリートを流し込む鋳型のようなもの)が堅固に精度良く組み立てられている。
4) コンクリートが緻密に隙間なく型枠内に流し込まれている。
5) コンクリートの強度が出るまで十分に養生期間が保たれている。
以上は一つでも不十分な項目があると、丈夫な構造体は出来ません。
基本的には建設会社の管理体制と下請け業者との信頼関係が大切であることはもちろんです。
しかし、マンション購入者はこれらのことを確認することはできません。
コンクリートにひび割れが出来てからは遅いのです。補修程度では解決できないのです。
マンションの事業主に全てのプロセスが確実に施工されているかを確認する責任があります。
マンション購入者は構造体が丈夫に出来ていることが前提でその後のマンションの維持管理をしながら安心して住み続けることが出来るのです。
「実績のある大手の企業だから安心です。」という単純な言葉は必要ありません。
構造躯体に10年間程度の保証は必要ないのです。何十年もの間、安心して住み続けたいのです。丈夫な骨組みが確実に造られていると言う証明・証拠がほしいのです。
それが出来ないマンションの事業主はマンションという社会資本を販売する資格はないと思います。
救急患者が16病院受け入れ拒否で死亡。平常時に病院との付き合いを良くしておこうか。
Posted by haru at
08:26
│Comments(0)
2007年12月06日
89 マンションの「建物の維持管理」、責任者は誰? その8
前回で説明しましたように、建設業というのは、一般製造業とは違う特徴・特質を持った産業です。
これから少し分かりやすく、どのようにしてマンションの建設工事が実施されていくのか、あくまでも一般的な話として進めて見ます。
事業主から請け負った建設会社は、工事を進める上での基本となる「工事実行予算書」を作成します。
作成上の基本は、発注者から請け負った受注金額から建設会社を維持する為の経費と利益をさし引いた金額が工事の実行金額となります。これが実質的な工事原価です。
この原価を元に建設会社は各専門業者に下請けをさせていきます。
従って、他社と競争で安く受注すれば、あるいは特命で受注しても安い指値であれば、厳しい工事原価とならざるを得ません。その範囲の中で事業主からの要求品質の建物を完成させなければなりません。
これが建設業が存在し続けるための基本です。そこに建設会社の優劣が発生することになります。
工事原価の配分で、建物の構造躯体に関する原価を厳しくすれば、そのまま品質に影響する度合いは高くなります。
そこで、特に、2000年以降の超低価格の受注競争の結果が品質の低下に結びつく要因が理解されると思います。
このような特徴を持つ建設会社を選択するのは、マンションの事業主である売主です。
優秀な建設会社を見分けることが出来、建物完成後の見えない部分、特に構造躯体の施工品質をチェックできる能力を持った事業主がその責任を持つことになるのです。
コストが安いだけで物件ごとに建設会社を次々と変えている事業主や原価意識を持たない、全ての責任を建設会社に委ねるしか、技術スタッフを持たない、監理能力のない事業主の分譲するマンションは欠陥マンションとなる要素を含んでいると言わざるを得ないのです。
建設資材の偽装が次々発覚しています。分からないようにごまかすのがプロと言えるのか?
これから少し分かりやすく、どのようにしてマンションの建設工事が実施されていくのか、あくまでも一般的な話として進めて見ます。
事業主から請け負った建設会社は、工事を進める上での基本となる「工事実行予算書」を作成します。
作成上の基本は、発注者から請け負った受注金額から建設会社を維持する為の経費と利益をさし引いた金額が工事の実行金額となります。これが実質的な工事原価です。
この原価を元に建設会社は各専門業者に下請けをさせていきます。
従って、他社と競争で安く受注すれば、あるいは特命で受注しても安い指値であれば、厳しい工事原価とならざるを得ません。その範囲の中で事業主からの要求品質の建物を完成させなければなりません。
これが建設業が存在し続けるための基本です。そこに建設会社の優劣が発生することになります。
工事原価の配分で、建物の構造躯体に関する原価を厳しくすれば、そのまま品質に影響する度合いは高くなります。
そこで、特に、2000年以降の超低価格の受注競争の結果が品質の低下に結びつく要因が理解されると思います。
このような特徴を持つ建設会社を選択するのは、マンションの事業主である売主です。
優秀な建設会社を見分けることが出来、建物完成後の見えない部分、特に構造躯体の施工品質をチェックできる能力を持った事業主がその責任を持つことになるのです。
コストが安いだけで物件ごとに建設会社を次々と変えている事業主や原価意識を持たない、全ての責任を建設会社に委ねるしか、技術スタッフを持たない、監理能力のない事業主の分譲するマンションは欠陥マンションとなる要素を含んでいると言わざるを得ないのです。
建設資材の偽装が次々発覚しています。分からないようにごまかすのがプロと言えるのか?
Posted by haru at
07:52
│Comments(0)
2007年12月04日
88 マンションの「建物の維持管理」、責任者は誰? その7
マンションの「事業主」あるいは「売主」とは、資金を投じて土地を買い、設計事務所に設計を依頼し、あるいは設計・施工で建設会社に工事を発注し、販売会社に販売を委託する等してマンション事業全体を仕切っている会社です。
新築マンションを購入する場合、契約を結ぶ相手は売主です。全ての責任は、売主である事業主にあります。設計事務所、施工会社、販売会社等は事業主の下請けでしかありません。
ひとくちに売主といっても、大手不動産会社、地場の不動産会社、商社、大企業の関連会社、あるいは公的な住宅供給公社等々、実に様々です。資金と土地さえあれば、マンション事業は可能です。建設会社が売主となる場合を除いて、建物の建設は建設会社にすべてを任せることができます。そこに無責任な売主が介在する素地が潜んでいます。
建物の完成後の品質は基本的には建設会社の力量に左右されることには間違いありません。その前提にはもちろん、すべての最終責任を負う、売主のチェック体制が十分に行われている必要があります。
そこで、少し、回りくどいようですが、建物の品質に最もかかわりのある建物の建設を請け負う「建設会社」の一般的な特徴・特質を考えて見たいと思います。
1) 受注・請負産業です。
事業主から工事の注文を受け、契約し、注文通りの構造物・建築物を完成させ、引渡し、工事代金を受け取る。発注者がいなければ存在しない受身の会社です。
2) 単品・移動産業です。
建物の規模・形等 同一なものはほとんど存在しません。又、建物ができる土地・場所もちがいます。
3) 屋外・天気産業です。
工事は、天候・気象状況等の自然条件に左右されます。それが工事の採算や建物の品質にかかわる大きな要因となります。
4) 多くの専門業者に下請けをさせています。
コンクリートや鉄筋等の主要材料・資材はメーカーから直接購入しますが、型枠・鉄筋等の技能労働者等は下請け・協力業者から提供を受け、仕上げ・電気・水道工事等は専門工事業者に材工共で発注します。
従って、建設会社には設計・施工の管理者だけが要求されているということになります。
自動車や電気産業といった、一般製造業とは明らかに違う業態であると言うことができます。
つまり、マンション工事の品質は建設会社の規模等というより、工事現場で直接働く人達の技術と責任に頼らざるを得ない、ということになります。
そこで、マンションの建設品質に関係する、工事現場の実態を考えてみたいと思います。
今年の流行語に「ハニカミ王子」、去年は「ハンカチ王子」がいました。来年はどんな王子様が現れるのか?
新築マンションを購入する場合、契約を結ぶ相手は売主です。全ての責任は、売主である事業主にあります。設計事務所、施工会社、販売会社等は事業主の下請けでしかありません。
ひとくちに売主といっても、大手不動産会社、地場の不動産会社、商社、大企業の関連会社、あるいは公的な住宅供給公社等々、実に様々です。資金と土地さえあれば、マンション事業は可能です。建設会社が売主となる場合を除いて、建物の建設は建設会社にすべてを任せることができます。そこに無責任な売主が介在する素地が潜んでいます。
建物の完成後の品質は基本的には建設会社の力量に左右されることには間違いありません。その前提にはもちろん、すべての最終責任を負う、売主のチェック体制が十分に行われている必要があります。
そこで、少し、回りくどいようですが、建物の品質に最もかかわりのある建物の建設を請け負う「建設会社」の一般的な特徴・特質を考えて見たいと思います。
1) 受注・請負産業です。
事業主から工事の注文を受け、契約し、注文通りの構造物・建築物を完成させ、引渡し、工事代金を受け取る。発注者がいなければ存在しない受身の会社です。
2) 単品・移動産業です。
建物の規模・形等 同一なものはほとんど存在しません。又、建物ができる土地・場所もちがいます。
3) 屋外・天気産業です。
工事は、天候・気象状況等の自然条件に左右されます。それが工事の採算や建物の品質にかかわる大きな要因となります。
4) 多くの専門業者に下請けをさせています。
コンクリートや鉄筋等の主要材料・資材はメーカーから直接購入しますが、型枠・鉄筋等の技能労働者等は下請け・協力業者から提供を受け、仕上げ・電気・水道工事等は専門工事業者に材工共で発注します。
従って、建設会社には設計・施工の管理者だけが要求されているということになります。
自動車や電気産業といった、一般製造業とは明らかに違う業態であると言うことができます。
つまり、マンション工事の品質は建設会社の規模等というより、工事現場で直接働く人達の技術と責任に頼らざるを得ない、ということになります。
そこで、マンションの建設品質に関係する、工事現場の実態を考えてみたいと思います。
今年の流行語に「ハニカミ王子」、去年は「ハンカチ王子」がいました。来年はどんな王子様が現れるのか?
Posted by haru at
08:36
│Comments(2)
2007年12月03日
87 マンションの「建物の維持管理」、責任者は誰? その6
最近、よく耳にする言葉に「欠陥マンション」とか「欠陥住宅」と呼ばれるものがあります。
欠陥とは「瑕疵」という難しい言葉で呼ばれています。具体的に何を指すのか専門家でも分かりにくい内容です。
最近売り出しのマンションでは、マンションの売主は10年間の「瑕疵担保責任」があります。等という表現を聞かれたことがあると思います。
ここでいう、建物の欠陥とは、クロスの貼り方が悪いとか床に傷があるとかのレベルの問題ではありません。
主として、建物の性能を決定付ける骨組みである「主要構造部分」の欠陥のことです。
「主要構造部分」とは建物の基礎、壁、床、柱、梁、屋根、屋内階段等のことで、一般的には「鉄筋コンクリート」という構造体で造られています。
普通、「RC造」と呼ばれています。 「補強されたコンクリートで造られたもの」と言う意味です。
コンクリート自身は重量を支える、圧縮力に耐える材料です。しかし曲げる力には弱い為に、それを補強するのが棒状の鉄筋材です。
両者が一体となり、初めて安心できる構造体となるものです。
「コンクリート」と「鉄筋」という2種類の材料で構成される、ある意味では単純な構造体です。
2年前に発覚した、耐震偽装事件もこの鉄筋の不足が問題の発端でした。最近でも大手の建設業者の施工中の鉄筋不足、不適正な強度の鉄筋使用が問題になりました。
いずれもコンクリートを解体して造り直しをしなければならないほどの大問題となりました。
これらは、特例でしょうか? 最近改正された「建築基準法」で是正される問題なのかどうか、現実に、建物がどのように造られているのかを考えることで、「マンション購入者が安心して住めるマンションの維持管理とは」の答えを見つけたいと思います。
「マンション購入者に、いちいち、そんなことを気にしている余裕はない」と、お考えの人ほど参考にしていただきたいと思います。
いつの間にか「師走」になりました。これからも出来るだけ肩のこらない「ブログ」を心がけたいと思います。
欠陥とは「瑕疵」という難しい言葉で呼ばれています。具体的に何を指すのか専門家でも分かりにくい内容です。
最近売り出しのマンションでは、マンションの売主は10年間の「瑕疵担保責任」があります。等という表現を聞かれたことがあると思います。
ここでいう、建物の欠陥とは、クロスの貼り方が悪いとか床に傷があるとかのレベルの問題ではありません。
主として、建物の性能を決定付ける骨組みである「主要構造部分」の欠陥のことです。
「主要構造部分」とは建物の基礎、壁、床、柱、梁、屋根、屋内階段等のことで、一般的には「鉄筋コンクリート」という構造体で造られています。
普通、「RC造」と呼ばれています。 「補強されたコンクリートで造られたもの」と言う意味です。
コンクリート自身は重量を支える、圧縮力に耐える材料です。しかし曲げる力には弱い為に、それを補強するのが棒状の鉄筋材です。
両者が一体となり、初めて安心できる構造体となるものです。
「コンクリート」と「鉄筋」という2種類の材料で構成される、ある意味では単純な構造体です。
2年前に発覚した、耐震偽装事件もこの鉄筋の不足が問題の発端でした。最近でも大手の建設業者の施工中の鉄筋不足、不適正な強度の鉄筋使用が問題になりました。
いずれもコンクリートを解体して造り直しをしなければならないほどの大問題となりました。
これらは、特例でしょうか? 最近改正された「建築基準法」で是正される問題なのかどうか、現実に、建物がどのように造られているのかを考えることで、「マンション購入者が安心して住めるマンションの維持管理とは」の答えを見つけたいと思います。
「マンション購入者に、いちいち、そんなことを気にしている余裕はない」と、お考えの人ほど参考にしていただきたいと思います。
いつの間にか「師走」になりました。これからも出来るだけ肩のこらない「ブログ」を心がけたいと思います。
Posted by haru at
07:27
│Comments(0)
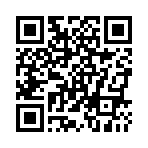
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン







