2007年11月30日
86 マンションの「建物の維持管理」、責任者は誰? その5
多くのマンションが「鉄筋コンクリート」という構造で出来ています。これからの話はこの構造を基準に進めていきます。 「鉄筋コンクリート」とは、「引っ張りに強い鉄筋」と「圧縮に強いコンクリート」を組み合わせた一体構造のことです。
建物の寿命は基本的には、骨組みである「構造躯体」が丈夫にできているという前提があります。そして構造躯体の維持管理は建物が完成した時点での品質に左右されます。
構造物が基準どうり造られており、コンクリートを保護する仕上げ材が適正に維持されていれば、基本的には構造躯体は簡単に劣化するものではありません。
新築マンションを購入するときに、仕上げの良し悪しには関心を持ちますが、建物の構造までチェックをする人はまずいないでしょう。素人には無理ですし、工事現場に立ちいって確認することは、可能ではありますが、あまり現実的ではありません。
今までは、建物は「建築基準法」という法律に基づいて適正に造られているという信頼感がありました。
「建築基準法」は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めたものです。
構造計算方法、コンクリートの強度、コンクリートを打ち込みした後の養生方法、鉄筋のコンクリートによる被覆幅(かぶり厚さ)等最低基準が決められています。
しかし、完成した構造物が基準どうりに出来ているかどうかは、あまり確認はされていません。一般的に、建物の調査診断は築10年前後、最初の、大規模修繕をする前あたりに「建物の劣化調査」と言う名目で行います。
マンションの構造躯体の品質確認は本来であれば、新築マンションの引渡し前の「内覧会」の時期に同時に実施され、マンション購入者に説明され、関係書類を受領しなければ意味がありません。
残念ながら、今の新築マンションの販売システムでは、管理組合がまだ実質上存在していませんから、「内覧会」という、各自が専有部分の表面的な確認だけで、結果的に建物全体のの引渡しを受けています。
これが後々、建物の、特に構造体の保証を曖昧にしていることになっています。
では、どの様な問題が潜んでいるのかを、これからしばらく考えてみたいと思います。
公共工事で「脱談合」による、安値応札が相次いでいるようです。急がれる「建設品質」確保の対応。
建物の寿命は基本的には、骨組みである「構造躯体」が丈夫にできているという前提があります。そして構造躯体の維持管理は建物が完成した時点での品質に左右されます。
構造物が基準どうり造られており、コンクリートを保護する仕上げ材が適正に維持されていれば、基本的には構造躯体は簡単に劣化するものではありません。
新築マンションを購入するときに、仕上げの良し悪しには関心を持ちますが、建物の構造までチェックをする人はまずいないでしょう。素人には無理ですし、工事現場に立ちいって確認することは、可能ではありますが、あまり現実的ではありません。
今までは、建物は「建築基準法」という法律に基づいて適正に造られているという信頼感がありました。
「建築基準法」は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めたものです。
構造計算方法、コンクリートの強度、コンクリートを打ち込みした後の養生方法、鉄筋のコンクリートによる被覆幅(かぶり厚さ)等最低基準が決められています。
しかし、完成した構造物が基準どうりに出来ているかどうかは、あまり確認はされていません。一般的に、建物の調査診断は築10年前後、最初の、大規模修繕をする前あたりに「建物の劣化調査」と言う名目で行います。
マンションの構造躯体の品質確認は本来であれば、新築マンションの引渡し前の「内覧会」の時期に同時に実施され、マンション購入者に説明され、関係書類を受領しなければ意味がありません。
残念ながら、今の新築マンションの販売システムでは、管理組合がまだ実質上存在していませんから、「内覧会」という、各自が専有部分の表面的な確認だけで、結果的に建物全体のの引渡しを受けています。
これが後々、建物の、特に構造体の保証を曖昧にしていることになっています。
では、どの様な問題が潜んでいるのかを、これからしばらく考えてみたいと思います。
公共工事で「脱談合」による、安値応札が相次いでいるようです。急がれる「建設品質」確保の対応。
Posted by haru at
09:05
│Comments(0)
2007年11月29日
85 マンションの「建物の維持管理」、責任者は誰? その4
マンションの管理を適正に行うためには、管理組合が適切な時期に建物・設備・外構等の計画的な点検・修繕を行うことが必要です。
一般的に、マンションの建物の維持管理は具体的には次のような方法で行われています。
1) 日常点検
管理組合や管理会社が日常的に実施する点検で、主として外観を目視により点検するものです。ほとんどのマンションでは管理員が巡回して異常がないかを確認していると思います。
2) 定期点検
マンションには、関係法令により有資格者の点検が義務づけられているものがあり、主として、管理会社に依頼しています。
3) 定期清掃
共用ローカや階段等の清掃と受水槽や排水管の清掃等がありますが、これもほとんどが管理会社に依頼しています。
4) 経常的な修繕
上記1)2)3)の結果に基づく軽微な修繕のことです。これもほとんどが管理会社に依頼しています。
5) 計画修繕
あらかじめ設定した修繕計画(長期修繕計画といわれるものです)に基づき、新築時に持っていた性能や機能を回復し、あるいはそれ以上とするための修繕です。一般的に「大規模修繕工事」と呼ばれるものです。
6) 住環境の改善
居住性向上のための、上記1)~5)に含まれない、マンションの新たな機能の付加、駐車場の増設等のことです。
各項目で共通することは建物の維持管理をする上での「建物の調査診断」です。このことを、もう少し具体的な内容で考えてみたいと思います。
マンションの管理対象物は、一般的には、大きく分けると、主として次のような4項目で構成されています。
(1) 建物の骨組みである基礎・柱・梁・床・壁・屋根等の「構造躯体」と言われるもの
(2) 「構造躯体」に取り付ける仕上げ材や防水材、サッシュ・ガラス・金物材等
(3) 毎日の生活に必要な機能を果たす、給排水・ガス・電気・通信・消防設備・エレベーター等の設備関係。
(4) 建物に附属した、駐車場・通路・擁壁・植栽等の外構を含む諸施設
建物の維持管理を適正に行うには、その建物が各項目毎に、どのような計画で造られ、どのような方法で造られているのかを知らなければ正確な計画を作ることはできません。それを確認することが、ここでいう「建物の調査診断」のことです。
次回、(1)に関する維持管理の問題から考えてみることにします。
床下に現金16億円隠した人、又、10億円寄付した人も。お金は生きもの!
一般的に、マンションの建物の維持管理は具体的には次のような方法で行われています。
1) 日常点検
管理組合や管理会社が日常的に実施する点検で、主として外観を目視により点検するものです。ほとんどのマンションでは管理員が巡回して異常がないかを確認していると思います。
2) 定期点検
マンションには、関係法令により有資格者の点検が義務づけられているものがあり、主として、管理会社に依頼しています。
3) 定期清掃
共用ローカや階段等の清掃と受水槽や排水管の清掃等がありますが、これもほとんどが管理会社に依頼しています。
4) 経常的な修繕
上記1)2)3)の結果に基づく軽微な修繕のことです。これもほとんどが管理会社に依頼しています。
5) 計画修繕
あらかじめ設定した修繕計画(長期修繕計画といわれるものです)に基づき、新築時に持っていた性能や機能を回復し、あるいはそれ以上とするための修繕です。一般的に「大規模修繕工事」と呼ばれるものです。
6) 住環境の改善
居住性向上のための、上記1)~5)に含まれない、マンションの新たな機能の付加、駐車場の増設等のことです。
各項目で共通することは建物の維持管理をする上での「建物の調査診断」です。このことを、もう少し具体的な内容で考えてみたいと思います。
マンションの管理対象物は、一般的には、大きく分けると、主として次のような4項目で構成されています。
(1) 建物の骨組みである基礎・柱・梁・床・壁・屋根等の「構造躯体」と言われるもの
(2) 「構造躯体」に取り付ける仕上げ材や防水材、サッシュ・ガラス・金物材等
(3) 毎日の生活に必要な機能を果たす、給排水・ガス・電気・通信・消防設備・エレベーター等の設備関係。
(4) 建物に附属した、駐車場・通路・擁壁・植栽等の外構を含む諸施設
建物の維持管理を適正に行うには、その建物が各項目毎に、どのような計画で造られ、どのような方法で造られているのかを知らなければ正確な計画を作ることはできません。それを確認することが、ここでいう「建物の調査診断」のことです。
次回、(1)に関する維持管理の問題から考えてみることにします。
床下に現金16億円隠した人、又、10億円寄付した人も。お金は生きもの!
Posted by haru at
07:37
│Comments(0)
2007年11月27日
84 マンションの「建物の維持管理」、責任者は誰? その3
マンションの「価値」をどこに求めるかは、マンションを購入する人のニーズにより異なります。
立地条件、専有部分の広さ、全体の規模、多様な設備、耐震性、高齢者対応、防災・防犯対応等様々です。
一般の商品の販売価格は製造原価に販売コストで決められています。
しかし、マンションの販売価格は一般の商品とは違う基準で決められています。
その一例が、一つのマンションで、同じ面積、同じ間取り、同じ仕様であっても、階数や角部屋か否か等の諸条件を考慮して決められています。
純粋な建設原価はあまり反映されたものとはいえません。
そのため、建物が本来持つべき骨組みの強度や耐久性、仕上げ材や給排水管等の耐用年数等にはほとんど原価意識を持ってこなかったのではないでしょうか。
その結果が近年表面化してきた耐震偽装をはじめとする様々な建設関係資材の不正事件ではないのかと思います。
今年の5月に「自民党の住宅土地調査会長・福田康夫」の名前で「200年住宅ビジョン」の提言がされています。
ここで言う「200年」とは、住宅のロングライフ化を象徴的に表したものです。
それによると、200年住宅のイメージとして
○ スケルトン(構造躯体)については耐久性・耐震性、インフィル(内装・設備)については可変性を確保(堅牢で、かつ、変化する住宅)
○ 維持管理が容易
○ 次世代に引き継ぐにふさわしい住宅の質(省エネ、バリアフリー)を確保
○ 計画的な維持修繕(点検、補修、交換等) 等とされています。
つまり、いままで住宅を供給してきた売主や買主があまり意識しなかった、本来求められるべき建物の品質や長期的に利用可能な状態にすべき、建物の維持管理の重要性を再確認した提言ではないかと思います。
説明が長くなりますが、このタイトルはしばらく続けます。
名建築と言われる築70年以上の「東京中央郵便局舎」が超高層ビルへの建て替えの計画があるそうです。その行方を見守りたいと思います。
立地条件、専有部分の広さ、全体の規模、多様な設備、耐震性、高齢者対応、防災・防犯対応等様々です。
一般の商品の販売価格は製造原価に販売コストで決められています。
しかし、マンションの販売価格は一般の商品とは違う基準で決められています。
その一例が、一つのマンションで、同じ面積、同じ間取り、同じ仕様であっても、階数や角部屋か否か等の諸条件を考慮して決められています。
純粋な建設原価はあまり反映されたものとはいえません。
そのため、建物が本来持つべき骨組みの強度や耐久性、仕上げ材や給排水管等の耐用年数等にはほとんど原価意識を持ってこなかったのではないでしょうか。
その結果が近年表面化してきた耐震偽装をはじめとする様々な建設関係資材の不正事件ではないのかと思います。
今年の5月に「自民党の住宅土地調査会長・福田康夫」の名前で「200年住宅ビジョン」の提言がされています。
ここで言う「200年」とは、住宅のロングライフ化を象徴的に表したものです。
それによると、200年住宅のイメージとして
○ スケルトン(構造躯体)については耐久性・耐震性、インフィル(内装・設備)については可変性を確保(堅牢で、かつ、変化する住宅)
○ 維持管理が容易
○ 次世代に引き継ぐにふさわしい住宅の質(省エネ、バリアフリー)を確保
○ 計画的な維持修繕(点検、補修、交換等) 等とされています。
つまり、いままで住宅を供給してきた売主や買主があまり意識しなかった、本来求められるべき建物の品質や長期的に利用可能な状態にすべき、建物の維持管理の重要性を再確認した提言ではないかと思います。
説明が長くなりますが、このタイトルはしばらく続けます。
名建築と言われる築70年以上の「東京中央郵便局舎」が超高層ビルへの建て替えの計画があるそうです。その行方を見守りたいと思います。
Posted by haru at
10:25
│Comments(0)
2007年11月26日
83 マンションの「建物の維持管理」、責任者は誰? その2
「もったいない」と言う言葉に代表されるように、今、ものに対する考え方が大きく変わりつつあるようです。「使い捨ての時代」から「物を大切に永く使う時代」への変換です。マンションも例外ではないようです。
永住するか、いずれは売却するかにかかわらず、年数を経ても魅力的な建物を維持したいのは、そこに住む人の共通の願いです。
今までは、築40年足らずで、建て替えされるマンションが多くありました。しかし、適切な時期にきちんと手入れをし、必要な改良を加えれば、建物の寿命を伸ばすことが可能な多くの工夫がされるようになってきました。
マンション購入価格の8割以上は、購入者全員で共有する土地や共用部分です。
マンション購入者はそれを維持管理するために、管理費や修繕積立金という名目で、平均的には、毎月2万円前後の費用を負担しています。
マンションに居住する限り払い続けなければなりません。
40年住み続ければ、物価変動を無視した場合、約1千万の費用ということになります。基本的には各居住者負担となる専有部分の費用等を加算すれば、実際にはその倍近くを覚悟しなければならないでしょう。
しかし、マンションの性能は一つ一つ違います。従って維持管理費用も当然各マンションで違うはずです。
設計・施工に十分配慮され、メンテナンスにあまり費用のかからない建物と、設計・施工に問題があり、メンテナンスに予想以上の費用がかかる建物があります。
マンションの購入価格には、土地の購入費用、建物の建設費、販売経費等全て含まれています。
建物の建設費用はいくらなのかを知って、マンションを購入している人はほとんどいないでしょう。ところが、建物の維持管理に影響する重要な要素であることには間違いがありません。
そこで、建物が誕生した条件等の違いから見た、建物の維持管理の問題を考えてみたいと思います。
高速道路を逆走する高齢者運転の車のニュースが続いています。遭遇したらと思うと「ぞーっ」とします。
永住するか、いずれは売却するかにかかわらず、年数を経ても魅力的な建物を維持したいのは、そこに住む人の共通の願いです。
今までは、築40年足らずで、建て替えされるマンションが多くありました。しかし、適切な時期にきちんと手入れをし、必要な改良を加えれば、建物の寿命を伸ばすことが可能な多くの工夫がされるようになってきました。
マンション購入価格の8割以上は、購入者全員で共有する土地や共用部分です。
マンション購入者はそれを維持管理するために、管理費や修繕積立金という名目で、平均的には、毎月2万円前後の費用を負担しています。
マンションに居住する限り払い続けなければなりません。
40年住み続ければ、物価変動を無視した場合、約1千万の費用ということになります。基本的には各居住者負担となる専有部分の費用等を加算すれば、実際にはその倍近くを覚悟しなければならないでしょう。
しかし、マンションの性能は一つ一つ違います。従って維持管理費用も当然各マンションで違うはずです。
設計・施工に十分配慮され、メンテナンスにあまり費用のかからない建物と、設計・施工に問題があり、メンテナンスに予想以上の費用がかかる建物があります。
マンションの購入価格には、土地の購入費用、建物の建設費、販売経費等全て含まれています。
建物の建設費用はいくらなのかを知って、マンションを購入している人はほとんどいないでしょう。ところが、建物の維持管理に影響する重要な要素であることには間違いがありません。
そこで、建物が誕生した条件等の違いから見た、建物の維持管理の問題を考えてみたいと思います。
高速道路を逆走する高齢者運転の車のニュースが続いています。遭遇したらと思うと「ぞーっ」とします。
Posted by haru at
08:44
│Comments(0)
2007年11月22日
82 マンションの「建物の維持管理」、責任者は誰? その1
マンションの管理組合は「マンション購入者が全員で構成する、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体」のことです。
分譲マンションは、マンションの敷地や共用部分はマンション購入者全員の共有財産です。これを維持管理するために、「区分所有法」で管理組合の設立を義務づけられたものです。
管理組合は、管理規約や理事長、理事会の存在、総会の開催が在る無しにかかわらず存在しています。
マンションの新築分譲後、入居が開始された時期から、マンションの維持管理は全て、管理組合の責任となります。
つまり、マンション購入者全員の共同責任ということになるわけです。
一般的に、マンション分譲業者は、管理組合がスムーズに運営開始ができるように、管理組合の業務を代行する管理会社を指定します。
従って、マンションの維持管理に関する品質は指定された管理会社の能力次第と言うことになります。しかし、マンション購入者にその時点では、管理会社の良否を判断することはほとんど不可能です。
マンション購入者は、契約時にそれを半強制的に承諾することになります。結果としてマンションの維持管理は全て管理会社がしてくれるものと錯覚したままマンションに住み続けることになります。
マンションは、見知らぬ人たちが共同で購入した「乗り合いバス」のようなものです。運転の仕方や故障した時の修理の仕方を知らない乗客が安全に目的地(建物の寿命)までどうやって運行していけばいいのでしょうか。
これらの現実を踏まえた上で、マンションの大規模修繕工事等を含む建物の維持管理の問題について考えてみたいと思います。
次々発覚する建築関係の偽装。食品関係の偽装とは比較にならない社会的責任の大きさ。
分譲マンションは、マンションの敷地や共用部分はマンション購入者全員の共有財産です。これを維持管理するために、「区分所有法」で管理組合の設立を義務づけられたものです。
管理組合は、管理規約や理事長、理事会の存在、総会の開催が在る無しにかかわらず存在しています。
マンションの新築分譲後、入居が開始された時期から、マンションの維持管理は全て、管理組合の責任となります。
つまり、マンション購入者全員の共同責任ということになるわけです。
一般的に、マンション分譲業者は、管理組合がスムーズに運営開始ができるように、管理組合の業務を代行する管理会社を指定します。
従って、マンションの維持管理に関する品質は指定された管理会社の能力次第と言うことになります。しかし、マンション購入者にその時点では、管理会社の良否を判断することはほとんど不可能です。
マンション購入者は、契約時にそれを半強制的に承諾することになります。結果としてマンションの維持管理は全て管理会社がしてくれるものと錯覚したままマンションに住み続けることになります。
マンションは、見知らぬ人たちが共同で購入した「乗り合いバス」のようなものです。運転の仕方や故障した時の修理の仕方を知らない乗客が安全に目的地(建物の寿命)までどうやって運行していけばいいのでしょうか。
これらの現実を踏まえた上で、マンションの大規模修繕工事等を含む建物の維持管理の問題について考えてみたいと思います。
次々発覚する建築関係の偽装。食品関係の偽装とは比較にならない社会的責任の大きさ。
Posted by haru at
09:39
│Comments(0)
2007年11月20日
81 マンションの管理規約、居住者に理解されるには?
前回まで、多くのマンションで参考にされ、使用されています「マンション標準管理規約」の内容の一部を見てきました。
マンションで共同生活をするためにはどうしてもルールは必要でしょう。
そのために作成された管理規約はマンション居住者全員に内容が理解され、守られなければ意味がありません。
そこで、前回までのタイトルについて書きながら感じた、管理規約が居住者に理解されるためには、どのようなことに留意すればいいのかを纏めてみたいと思います。
★ マンションを購入した人である区分所有者だけではなく、賃借人等を含むそのマンションに居住する全ての人がわかる内容になっているか。
★ 言葉の解釈によりトラブルにならないように、具体的に分かり易い表現がされているか。
★ 社会環境や居住者意識の変化に対応して、定期的に見直しがされているか。
★ 規約の見直しの手続きが分かりやすく、法的に違反していないか。
★ 規約の内容は実行可能なものになっているか。
★ ルールに違反したときの措置が誰でも納得のできるものになっているか。
★ アンケート調査等でルールに対する居住者の意識調査がなされているか。現実にどのようなトラブルがあるのか。実態が反映されたものになっているか。
貴方のお住まいのマンションの管理規約はどのような状態にありますか?
永く住みよいマンションにするために、真に居住者の為の管理規約となるよう、ぜひ検討してみてください。
大阪市長に元アナウンサーの自称「素人市長」が登場。それでは「プロの市長」とは?
マンションで共同生活をするためにはどうしてもルールは必要でしょう。
そのために作成された管理規約はマンション居住者全員に内容が理解され、守られなければ意味がありません。
そこで、前回までのタイトルについて書きながら感じた、管理規約が居住者に理解されるためには、どのようなことに留意すればいいのかを纏めてみたいと思います。
★ マンションを購入した人である区分所有者だけではなく、賃借人等を含むそのマンションに居住する全ての人がわかる内容になっているか。
★ 言葉の解釈によりトラブルにならないように、具体的に分かり易い表現がされているか。
★ 社会環境や居住者意識の変化に対応して、定期的に見直しがされているか。
★ 規約の見直しの手続きが分かりやすく、法的に違反していないか。
★ 規約の内容は実行可能なものになっているか。
★ ルールに違反したときの措置が誰でも納得のできるものになっているか。
★ アンケート調査等でルールに対する居住者の意識調査がなされているか。現実にどのようなトラブルがあるのか。実態が反映されたものになっているか。
貴方のお住まいのマンションの管理規約はどのような状態にありますか?
永く住みよいマンションにするために、真に居住者の為の管理規約となるよう、ぜひ検討してみてください。
大阪市長に元アナウンサーの自称「素人市長」が登場。それでは「プロの市長」とは?
Posted by haru at
07:43
│Comments(0)
2007年11月19日
80 マンションの管理規約、何故読まれないのか? その7
「マンション標準管理規約」の47条に「総会の議事において、敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)については、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する」と言った内容等のことが規定されています。いわゆる特別決議といわれるものです。
これは、「区分所有法」の規定を管理規約にも確認的に規定されたものですが、そのままでは具体的にどのような内容を言うのかわかりにくい条文です。
言い方を変えると、形状又は効用の著しい変更でないものは、普通決議でも決められますという意味です。
普通決議というのは、一般的には最低、総議決権の4分の1を超えた賛成があればいいわけですから、形状又は効用の著しい変更の解釈の違いでトラブルになるようです。
簡単に言うと組合員の25%なのか75%の賛成が必要なのかの議論になるからです。
通常、共用部分の変更と言うのは階段からエレベーターへの改造、非常階段の増設、倉庫、車庫等の増改築等のことです。
マンションの経年による劣化や老朽化での外壁や屋上防水、給排水管等について行う通常の大規模修繕については形状又は効用の著しい変更とはいえないと言うことで普通決議でよいとされています。
しかし、大規模修繕時に実施される、外壁の打ちっ放し仕上げからタイル仕上げへの変更やベランダ、共用ローカのスチール製の手摺からアルミ製の手摺への変更等、その内容によっては効用又は形状の著しい変更の解釈で議論の分かれるところです。
従って、それぞれのマンションで、どの程度の形状や効用の変更を伴うのか、個別の事情を勘案していくことになります。
法律の文章をそのまま、規約に反映させることは正確を期すためには大切ですが、規約を守る立場の居住者にはかえって分かりにくいものです。誰でもが理解しやすい様に具体的な表現にしておきたいものです。
日本は「世界一のゴミ分別大国」だそうです。ところで、分けたゴミをまとめて焼却しているところがあるそうです。???
これは、「区分所有法」の規定を管理規約にも確認的に規定されたものですが、そのままでは具体的にどのような内容を言うのかわかりにくい条文です。
言い方を変えると、形状又は効用の著しい変更でないものは、普通決議でも決められますという意味です。
普通決議というのは、一般的には最低、総議決権の4分の1を超えた賛成があればいいわけですから、形状又は効用の著しい変更の解釈の違いでトラブルになるようです。
簡単に言うと組合員の25%なのか75%の賛成が必要なのかの議論になるからです。
通常、共用部分の変更と言うのは階段からエレベーターへの改造、非常階段の増設、倉庫、車庫等の増改築等のことです。
マンションの経年による劣化や老朽化での外壁や屋上防水、給排水管等について行う通常の大規模修繕については形状又は効用の著しい変更とはいえないと言うことで普通決議でよいとされています。
しかし、大規模修繕時に実施される、外壁の打ちっ放し仕上げからタイル仕上げへの変更やベランダ、共用ローカのスチール製の手摺からアルミ製の手摺への変更等、その内容によっては効用又は形状の著しい変更の解釈で議論の分かれるところです。
従って、それぞれのマンションで、どの程度の形状や効用の変更を伴うのか、個別の事情を勘案していくことになります。
法律の文章をそのまま、規約に反映させることは正確を期すためには大切ですが、規約を守る立場の居住者にはかえって分かりにくいものです。誰でもが理解しやすい様に具体的な表現にしておきたいものです。
日本は「世界一のゴミ分別大国」だそうです。ところで、分けたゴミをまとめて焼却しているところがあるそうです。???
Posted by haru at
07:53
│Comments(0)
2007年11月16日
79 マンションの管理規約、何故読まれないのか? その6
「マンション標準管理規約」の第17条に(専有部分の修繕等)に関して、要約すると次のような規定があります。
「区分所有者が住戸内の修繕、模様替え等の改修工事をする場合には、事前に、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を提出し、理事会の決議に基づいて理事長の承認を必要とする。」としています。
住戸内の改修工事の内容によっては、建物の構造体への影響、防火、防音、断熱等の影響、耐力計算上の問題、他の住戸への影響等を判断する専門的な能力が必要となります。
しかし、理事長を含む理事が1年ほどの任期の輪番制で決まる一般的なマンションでは、申請書の内容の適否を理事会が判断するのはかなり無理があります。
管理組合としてはそのための相談体制として、次の内、いずれかの前提がいるでしょう。
☆ 管理会社にその能力があり、専有部分の改修に関する相談の業務委託をしている。(管理会社との業務委託契約には管理対象として、一般的には専有部分は除外されています。)
☆ 管理組合に専有部分の改修に関する専門委員会等の設置をしている。
☆ 管理組合で建築士等の専門的知識を有する者との相談体制が出来ている。
実際には、このような体制が出来ているマンションは少ないと思われます。
又、現実的な方法としては、共用部分に影響しない、専有部分の改修だけを認め、その全責任を改修した居住者とし、工事着工前に必要事項を記入した誓約書を提出してもらう等の対応も考えられます。そのためには専有部分の範囲を誰にでも分かりやすくしておく必要があります。
いずれにしても、管理規約は現実に実行できる内容でなければ、守られないことになり、「絵に描いた餅」でしかありません。
丹波三山の紅葉を見てきました。今年は例年に比べかなり遅く、色づきも鮮やかさに欠けるようでした。
「区分所有者が住戸内の修繕、模様替え等の改修工事をする場合には、事前に、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を提出し、理事会の決議に基づいて理事長の承認を必要とする。」としています。
住戸内の改修工事の内容によっては、建物の構造体への影響、防火、防音、断熱等の影響、耐力計算上の問題、他の住戸への影響等を判断する専門的な能力が必要となります。
しかし、理事長を含む理事が1年ほどの任期の輪番制で決まる一般的なマンションでは、申請書の内容の適否を理事会が判断するのはかなり無理があります。
管理組合としてはそのための相談体制として、次の内、いずれかの前提がいるでしょう。
☆ 管理会社にその能力があり、専有部分の改修に関する相談の業務委託をしている。(管理会社との業務委託契約には管理対象として、一般的には専有部分は除外されています。)
☆ 管理組合に専有部分の改修に関する専門委員会等の設置をしている。
☆ 管理組合で建築士等の専門的知識を有する者との相談体制が出来ている。
実際には、このような体制が出来ているマンションは少ないと思われます。
又、現実的な方法としては、共用部分に影響しない、専有部分の改修だけを認め、その全責任を改修した居住者とし、工事着工前に必要事項を記入した誓約書を提出してもらう等の対応も考えられます。そのためには専有部分の範囲を誰にでも分かりやすくしておく必要があります。
いずれにしても、管理規約は現実に実行できる内容でなければ、守られないことになり、「絵に描いた餅」でしかありません。
丹波三山の紅葉を見てきました。今年は例年に比べかなり遅く、色づきも鮮やかさに欠けるようでした。
Posted by haru at
09:47
│Comments(0)
2007年11月13日
78 マンションの管理規約、何故読まれないのか? その5
「マンション標準管理規約」の第12条には「専有部分の用途」として次のように規制しています。
「区分所有者は、その専有部分を専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
分譲時からマンションの一部を店舗や事務所にすることを容認している場合は別ですが、この規約で住戸の使用を制限する根拠として、不特定多数の人が出入りし、騒音を発生させたり、共用部分を汚す等、他の居住者に迷惑を及ぼす可能性が高いことがあります。
しかし、居住者の共同の利益に反しない限りにおいては、専有部分は所有者が自由に使用できるはずのものです。この条項は所有権に対する極めて重大な制限であることには間違いありません。
最近では、マンションの住戸内でSOHO(スモールオフィス・ホームオフィス)と言われるような在宅ワークをする人、又、それを希望する人も増えてきています。
一般の家庭でも普及してきたパソコンやコピー機、ファクスを利用した仕事が可能になったからでしょう。
少人数を対象とした華道、書道、茶道等の伝授をしたいと考えておられる高齢者や主婦の皆さんもおられるでしょう。
住居使用以外は全て禁止と言うより、制限つきで住戸の活用を認めるというほうがマンションのコミュニティの活性化という意味からもこれからは必要かと思われます。
生活の本拠である為に必要な平穏さを保つ範囲でどこまで許容できるのかを、みんなで話し合い、その結果を具体的に規約に反映させておくことで、住民に理解され、無用なトラブルを少なくすることが出来るものと思います。
規約に対する考え方も時代と共に変化していくものです。常に規約の見直しをしていくことで、居住者に読まれ、守られる管理規約になるはずです。
鉄腕投手、稲尾和久さん死去。シーズン最多の42勝、今では考えられない驚異的な記録です。
「区分所有者は、その専有部分を専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
分譲時からマンションの一部を店舗や事務所にすることを容認している場合は別ですが、この規約で住戸の使用を制限する根拠として、不特定多数の人が出入りし、騒音を発生させたり、共用部分を汚す等、他の居住者に迷惑を及ぼす可能性が高いことがあります。
しかし、居住者の共同の利益に反しない限りにおいては、専有部分は所有者が自由に使用できるはずのものです。この条項は所有権に対する極めて重大な制限であることには間違いありません。
最近では、マンションの住戸内でSOHO(スモールオフィス・ホームオフィス)と言われるような在宅ワークをする人、又、それを希望する人も増えてきています。
一般の家庭でも普及してきたパソコンやコピー機、ファクスを利用した仕事が可能になったからでしょう。
少人数を対象とした華道、書道、茶道等の伝授をしたいと考えておられる高齢者や主婦の皆さんもおられるでしょう。
住居使用以外は全て禁止と言うより、制限つきで住戸の活用を認めるというほうがマンションのコミュニティの活性化という意味からもこれからは必要かと思われます。
生活の本拠である為に必要な平穏さを保つ範囲でどこまで許容できるのかを、みんなで話し合い、その結果を具体的に規約に反映させておくことで、住民に理解され、無用なトラブルを少なくすることが出来るものと思います。
規約に対する考え方も時代と共に変化していくものです。常に規約の見直しをしていくことで、居住者に読まれ、守られる管理規約になるはずです。
鉄腕投手、稲尾和久さん死去。シーズン最多の42勝、今では考えられない驚異的な記録です。
Posted by haru at
22:04
│Comments(0)
2007年11月12日
77 マンションの管理規約、何故読まれないのか? その4
今回も、引き続き「マンション標準管理規約」の内容を見ていきます。
これからは、特に区分所有者やその他の居住者にとって日常的に特に影響のある条文について見ていきたいと思います。
規約の第7条には「専有部分の範囲」が規定されています。専有部分とはマンション購入者が単独で所有し、基本的には自由に使用できる部分のことですから、重要な条文です。
言葉の説明だけでは居住者には、わかりにくい条文であり、平面図や断面図を添付し、具体的にどの部分が専有部分なのかを、誰でも理解できるようにしておく必要があります。
例えば、住戸内にある、トイレや台所や浴室等の排水用立て配管が収納されているパイプスペースはコンクリートではなく、ボード類で囲まれている場合が多く、範囲がわかりにくいと思われます。
又、ボードで覆われて見えませんが、住戸内で外部に面する壁、梁、柱にはほとんどのマンションで断熱材が吹き付けされています。厚さが10ミリから20ミリくらいの発砲ウレタンが多く使用されています。
この部分は規約では専有部分となりますが、建物の断熱や結露防止の役目から見ますと居住者が勝手に取り扱う部分ではなくて、共用部分としておくほうが安全かと思われます。
その他、各マンションの実情に合わせてどこまでを専有部分とするかを具体的にわかりやすく表示をしておくことが、無駄なトラブルを防ぐことになります。
住戸内の改修の時等で、日頃は見えない部分でどこまでが専有部分なのかはっきりしないことがあります。
そのためには、マンションの各部分の仕様がどうなっているのか、建物の専門家のアドバイスを受け、誰でもがわかるようにしておきましょう。
こういうことの配慮が、役に立つ、読まれる管理規約とするためには大切なことだと思います。
気温が下がり、周りに風邪気味の人が増えてきました。お互いに気をつけましょう。
これからは、特に区分所有者やその他の居住者にとって日常的に特に影響のある条文について見ていきたいと思います。
規約の第7条には「専有部分の範囲」が規定されています。専有部分とはマンション購入者が単独で所有し、基本的には自由に使用できる部分のことですから、重要な条文です。
言葉の説明だけでは居住者には、わかりにくい条文であり、平面図や断面図を添付し、具体的にどの部分が専有部分なのかを、誰でも理解できるようにしておく必要があります。
例えば、住戸内にある、トイレや台所や浴室等の排水用立て配管が収納されているパイプスペースはコンクリートではなく、ボード類で囲まれている場合が多く、範囲がわかりにくいと思われます。
又、ボードで覆われて見えませんが、住戸内で外部に面する壁、梁、柱にはほとんどのマンションで断熱材が吹き付けされています。厚さが10ミリから20ミリくらいの発砲ウレタンが多く使用されています。
この部分は規約では専有部分となりますが、建物の断熱や結露防止の役目から見ますと居住者が勝手に取り扱う部分ではなくて、共用部分としておくほうが安全かと思われます。
その他、各マンションの実情に合わせてどこまでを専有部分とするかを具体的にわかりやすく表示をしておくことが、無駄なトラブルを防ぐことになります。
住戸内の改修の時等で、日頃は見えない部分でどこまでが専有部分なのかはっきりしないことがあります。
そのためには、マンションの各部分の仕様がどうなっているのか、建物の専門家のアドバイスを受け、誰でもがわかるようにしておきましょう。
こういうことの配慮が、役に立つ、読まれる管理規約とするためには大切なことだと思います。
気温が下がり、周りに風邪気味の人が増えてきました。お互いに気をつけましょう。
Posted by haru at
07:54
│Comments(0)
2007年11月09日
76 マンションの管理規約、何故読まれないのか? その3
これからの話は「マンション標準管理規約」か、これを参考に作られた管理規約をご覧になったことがない方には少しわかりにくいかもしれません。
また、管理規約の視点を区分所有者だけではなく、賃借人等のマンション居住者のすべてにおいていますので、法律の専門家等からは当然に異論、反論があると思います。
それらをふまえた上で、「マンション標準管理規約」の内容を見てみます。
規約の第1条には 「マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。」 とあります。
ここでいう区分所有者とは、この規約の第2条で区分所有法に定める区分所有者のことであると定義されています。
ここで規約を読もうとした人は、この後を読むことをほとんどあきらめるでしょう。
正しく理解しようと思う人ほど、区分所有法を読まなくてはなりません。
又、規約を読む人が、区分所有者とはマンションの住戸を購入した人ぐらいの理解はしているとしましょう。
全部の条文を読めば、規約にはマンションに居住する全ての人が守るべき内容が含まれています。
しかし、規約の第1条を読んで、賃借人や区分所有者と同居する家族は、この規約は区分所有者の為の規約だと判断し、自分たちは関係がないと思うでしょう。
マンションのルールは居住者全員が内容を理解し、常に守るように心がけなければ、快適な居住環境を維持することは出来ません。
そのためには、自分たちのマンションに即した、わかり易いルールに変えていく必要があります。
管理規約は標準に近いものでつくり、細則等でわかり易いものにするのもいいかもしれませんが、言葉の解釈等をめぐって争いが生じないよう、居住者全員が理解でき納得できるルールを、原点に戻り考えて見たいものです。
立体駐車場から車が転落、母子死亡の記事。マンションの駐車場にも不安を感じる時がありますが。
また、管理規約の視点を区分所有者だけではなく、賃借人等のマンション居住者のすべてにおいていますので、法律の専門家等からは当然に異論、反論があると思います。
それらをふまえた上で、「マンション標準管理規約」の内容を見てみます。
規約の第1条には 「マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。」 とあります。
ここでいう区分所有者とは、この規約の第2条で区分所有法に定める区分所有者のことであると定義されています。
ここで規約を読もうとした人は、この後を読むことをほとんどあきらめるでしょう。
正しく理解しようと思う人ほど、区分所有法を読まなくてはなりません。
又、規約を読む人が、区分所有者とはマンションの住戸を購入した人ぐらいの理解はしているとしましょう。
全部の条文を読めば、規約にはマンションに居住する全ての人が守るべき内容が含まれています。
しかし、規約の第1条を読んで、賃借人や区分所有者と同居する家族は、この規約は区分所有者の為の規約だと判断し、自分たちは関係がないと思うでしょう。
マンションのルールは居住者全員が内容を理解し、常に守るように心がけなければ、快適な居住環境を維持することは出来ません。
そのためには、自分たちのマンションに即した、わかり易いルールに変えていく必要があります。
管理規約は標準に近いものでつくり、細則等でわかり易いものにするのもいいかもしれませんが、言葉の解釈等をめぐって争いが生じないよう、居住者全員が理解でき納得できるルールを、原点に戻り考えて見たいものです。
立体駐車場から車が転落、母子死亡の記事。マンションの駐車場にも不安を感じる時がありますが。
Posted by haru at
10:30
│Comments(0)
2007年11月08日
75 マンションの管理規約、何故読まれないのか? その2
このブログを書きながらつくづく思います。「分譲マンションとは、ある意味では、なんとも厄介な住まいなんだろうか!」
「区分所有法」が出来たおかげで、一つの建物の一部(専有部分)を専有所有できる所有権が認められるようになりました。 その代わり、マンションを購入し、住む為には、この法律を守らなければなりません。
マンションを購入した人は、このことをほとんど意識しない、いや何十年住んでいてもまだそれほど意識しなくて住み続けています。
建物の維持管理に関しては、ほとんどの居住者が素人であることから永い間、専門家である管理業者に依頼してきたはずです。
ところが、平成12年に公布された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき出された国の指針には、「マンション管理の主体は区分所有者等で構成される管理組合である」と記されています。
主体的に管理するためにはマンション管理に関するいろいろな法律や情報を、ある程度知らなければ、誰かに管理を依頼することも出来ません。
区分所有法を初めとして多くの関連法の内容を知ってマンションを買う人などほとんどありません。又、それらをマンション居住者が知る仕組みもありません。
これらのことを考えると、マンション居住者も関係する多くの法律を自主的に知らなければ住めないことになり、極論すれば免許制にでもして、マンション居住資格のようなものが必要になるほどです。
タイトルから少し話がそれたようです。
マンションに居住しているのは区分所有者だけではありません。
同居している家族もいれば、賃借人もいます。全てそのマンションに居住する権利を持つ人たちです。
管理規約の目的の一つが「良好な居住環境を確保する」ことであれば、その内容は、等しく全ての居住者に理解される必要があります。
その視点で標準管理規約を見てみたいと思います。
タワーマンションで鉄筋の不足が見つかる。施工担当者のチェックミスだそうです。ミスを防ぐ仕組みは機能していないのか?
「区分所有法」が出来たおかげで、一つの建物の一部(専有部分)を専有所有できる所有権が認められるようになりました。 その代わり、マンションを購入し、住む為には、この法律を守らなければなりません。
マンションを購入した人は、このことをほとんど意識しない、いや何十年住んでいてもまだそれほど意識しなくて住み続けています。
建物の維持管理に関しては、ほとんどの居住者が素人であることから永い間、専門家である管理業者に依頼してきたはずです。
ところが、平成12年に公布された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき出された国の指針には、「マンション管理の主体は区分所有者等で構成される管理組合である」と記されています。
主体的に管理するためにはマンション管理に関するいろいろな法律や情報を、ある程度知らなければ、誰かに管理を依頼することも出来ません。
区分所有法を初めとして多くの関連法の内容を知ってマンションを買う人などほとんどありません。又、それらをマンション居住者が知る仕組みもありません。
これらのことを考えると、マンション居住者も関係する多くの法律を自主的に知らなければ住めないことになり、極論すれば免許制にでもして、マンション居住資格のようなものが必要になるほどです。
タイトルから少し話がそれたようです。
マンションに居住しているのは区分所有者だけではありません。
同居している家族もいれば、賃借人もいます。全てそのマンションに居住する権利を持つ人たちです。
管理規約の目的の一つが「良好な居住環境を確保する」ことであれば、その内容は、等しく全ての居住者に理解される必要があります。
その視点で標準管理規約を見てみたいと思います。
タワーマンションで鉄筋の不足が見つかる。施工担当者のチェックミスだそうです。ミスを防ぐ仕組みは機能していないのか?
Posted by haru at
08:32
│Comments(0)
2007年11月07日
74 マンションの管理規約、何故読まれないのか? その1
マンションの快適な居住環境を確保する為に、マンション購入者は、具体的な住まい方のルールを定めることが要求されています。
そして、マンション管理の主体はあくまでもマンション購入者等であり、居住者の意見が十分に反映されていることが望ましいとされています。
国は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、「マンション標準管理規約」を作成してそれを公表しています。
最近は、多くのマンションがこの「標準管理規約」をそのままに近い形で採用しているようです。
主として規約案を作成しているマンション分譲業者や管理業者にとっては非常に便利だということが一つの理由でしょう。
又、多くの専門家によりマンション関係法との整合性を保ちながら作成され、将来の発生が予測される問題についても対応可能な内容であるという安心感があることもその理由でしょう。
「標準管理規約」はマンション管理に詳しい大学教授や弁護士の先生方及び行政担当者が作成した案をさらに管理業者やマンション管理士等のマンション管理を業としている方の意見を参考にして最終的にまとめられたもののようです。
普通の生活者にとっては法律の文章そのものを読む機会はほとんどありません。マンション居住者も例外ではありません。
従って、管理規約を使う立場である多くの居住者にとっては、法律の文章に近い規約はなじみにくいのは仕方のないことかもしれません。
そこで、「標準管理規約」の内容を見ながら、何故当事者であるマンション居住者に読まれないのかを少し具体的に考えてみたいと思います。
民主党の小沢代表、2日で辞意撤回。なるほど、政権担当能力がまだない理由がわかる気がします。
そして、マンション管理の主体はあくまでもマンション購入者等であり、居住者の意見が十分に反映されていることが望ましいとされています。
国は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、「マンション標準管理規約」を作成してそれを公表しています。
最近は、多くのマンションがこの「標準管理規約」をそのままに近い形で採用しているようです。
主として規約案を作成しているマンション分譲業者や管理業者にとっては非常に便利だということが一つの理由でしょう。
又、多くの専門家によりマンション関係法との整合性を保ちながら作成され、将来の発生が予測される問題についても対応可能な内容であるという安心感があることもその理由でしょう。
「標準管理規約」はマンション管理に詳しい大学教授や弁護士の先生方及び行政担当者が作成した案をさらに管理業者やマンション管理士等のマンション管理を業としている方の意見を参考にして最終的にまとめられたもののようです。
普通の生活者にとっては法律の文章そのものを読む機会はほとんどありません。マンション居住者も例外ではありません。
従って、管理規約を使う立場である多くの居住者にとっては、法律の文章に近い規約はなじみにくいのは仕方のないことかもしれません。
そこで、「標準管理規約」の内容を見ながら、何故当事者であるマンション居住者に読まれないのかを少し具体的に考えてみたいと思います。
民主党の小沢代表、2日で辞意撤回。なるほど、政権担当能力がまだない理由がわかる気がします。
Posted by haru at
08:05
│Comments(0)
2007年11月04日
73 マンションの管理規約、読んだことがありますか?
マンションは一つの建物の中に、独立した権利を持ち、また、さまざまな生活スタイルをもった人たちが一緒に暮らしています。
各居住者が、好きなように住もうとすれば、それに応じた、しくみやルールが必要になります。そして、このルールを居住者全員が守ることで、快適な居住環境を維持することが出来ます。
建物等の管理維持とマンション居住者相互の共同生活のルールを文書化したものが、管理規約、使用細則、協定とか言われるものです。
マンション管理における自治規範として必要不可欠な管理規約は、ほとんどのマンションで作成されています。
そのほとんどは、国がモデルとして作成した標準的な管理規約を参考に作られています。しかし標準管理規約と呼ばれるものは、最初に作られたのが昭和57年ですから、それ以前に分譲されたマンションは、分譲業者が独自に作成したものです。
少し面倒な話になりますが、管理規約は「区分所有法」正確には「建物の区分所有等に関する法律」に反して作ることはできません。
「区分所有法」は昭和37年に始めて作られました。その後、実情を考慮して昭和58年、平成14年と改正されてきました。
モデルとなる標準管理規約も法改正等にあわせるように昭和58年、平成9年、平成16年に見直しがなされています。
管理規約は、基本的にはマンション購入者自身が標準管理規約等を参考にして、マンションの実態や居住者の意向を踏まえ、適切なものが作成されるべきものです。
現実には、マンション分譲業者かマンション管理業者が作成したものをそのまま使用しているマンションが8割くらいはあるようです。
マンション居住者は管理規約があることは知っていても、その内容を全て知っている人は少ないでしょう。
問題が発生してはじめて、規約の内容を確認することが多いようです。
次回、このマンションの管理規約の内容について考えてみたいと思います。
国が、築30年以上のマンション建て替え促進へ調査開始。建て替えが必要なのはマンションだけか?
各居住者が、好きなように住もうとすれば、それに応じた、しくみやルールが必要になります。そして、このルールを居住者全員が守ることで、快適な居住環境を維持することが出来ます。
建物等の管理維持とマンション居住者相互の共同生活のルールを文書化したものが、管理規約、使用細則、協定とか言われるものです。
マンション管理における自治規範として必要不可欠な管理規約は、ほとんどのマンションで作成されています。
そのほとんどは、国がモデルとして作成した標準的な管理規約を参考に作られています。しかし標準管理規約と呼ばれるものは、最初に作られたのが昭和57年ですから、それ以前に分譲されたマンションは、分譲業者が独自に作成したものです。
少し面倒な話になりますが、管理規約は「区分所有法」正確には「建物の区分所有等に関する法律」に反して作ることはできません。
「区分所有法」は昭和37年に始めて作られました。その後、実情を考慮して昭和58年、平成14年と改正されてきました。
モデルとなる標準管理規約も法改正等にあわせるように昭和58年、平成9年、平成16年に見直しがなされています。
管理規約は、基本的にはマンション購入者自身が標準管理規約等を参考にして、マンションの実態や居住者の意向を踏まえ、適切なものが作成されるべきものです。
現実には、マンション分譲業者かマンション管理業者が作成したものをそのまま使用しているマンションが8割くらいはあるようです。
マンション居住者は管理規約があることは知っていても、その内容を全て知っている人は少ないでしょう。
問題が発生してはじめて、規約の内容を確認することが多いようです。
次回、このマンションの管理規約の内容について考えてみたいと思います。
国が、築30年以上のマンション建て替え促進へ調査開始。建て替えが必要なのはマンションだけか?
Posted by haru at
09:42
│Comments(0)
2007年11月01日
72 マンション管理組合の法人化、メリットは何か?
現在、マンション管理組合の約一割が法人化しているといわれています。
法人とは、「自然人以外のもので、法律上の権利義務の主体とされるもの。一定の目的の為に結合した人の集団や財産について権利能力が認められる。」と辞書にありますが、一般の管理組合は法人格を有していませんので「権利能力なき社団」といわれています。
管理組合を法人化すると次のようなメリットがあります。
● 法律関係が明確になる。
法人名義で不動産の登記ができる。
● 管理組合財産と個人財産との区別が明確になる。
電話加入権、預金等の名義が理事長個人名義から法人名義で可能となる。
● 取引の安全が確保される。
管理組合の存在と代表者である理事の氏名は登記によって公示されるので、相手方も、登記簿を調べることによって安心して取引をすることが出来ます。
具体的には、マンション内で売りに出た住戸を管理組合が取得して、集会室やキッズルーム等にすることが出来ます。又、近隣の土地を購入して駐車場を拡張することが出来ます。
その他、大規模修繕等での融資が金融機関から借りやすくなり、訴訟時での手続きが簡便化され、銀行の預金名義等が継続できる。また、管理組合による競売住戸の買取で売買価格の低下防止等というメリットがあります。
通常の管理組合を法人化するには、総会での特別決議や登記、財産目録の作成等が必要ですが、それほど面倒な手続きではありません。
管理組合に特別必要な理由がなければ、わざわざ、法人化をすることはありませんが、将来に備えて管理組合で話し合っておくことは有益なことです。
今度は建材メーカーによる耐火材性能の偽装が発覚、信頼できるのか、不正が見抜けぬ認定機関。
法人とは、「自然人以外のもので、法律上の権利義務の主体とされるもの。一定の目的の為に結合した人の集団や財産について権利能力が認められる。」と辞書にありますが、一般の管理組合は法人格を有していませんので「権利能力なき社団」といわれています。
管理組合を法人化すると次のようなメリットがあります。
● 法律関係が明確になる。
法人名義で不動産の登記ができる。
● 管理組合財産と個人財産との区別が明確になる。
電話加入権、預金等の名義が理事長個人名義から法人名義で可能となる。
● 取引の安全が確保される。
管理組合の存在と代表者である理事の氏名は登記によって公示されるので、相手方も、登記簿を調べることによって安心して取引をすることが出来ます。
具体的には、マンション内で売りに出た住戸を管理組合が取得して、集会室やキッズルーム等にすることが出来ます。又、近隣の土地を購入して駐車場を拡張することが出来ます。
その他、大規模修繕等での融資が金融機関から借りやすくなり、訴訟時での手続きが簡便化され、銀行の預金名義等が継続できる。また、管理組合による競売住戸の買取で売買価格の低下防止等というメリットがあります。
通常の管理組合を法人化するには、総会での特別決議や登記、財産目録の作成等が必要ですが、それほど面倒な手続きではありません。
管理組合に特別必要な理由がなければ、わざわざ、法人化をすることはありませんが、将来に備えて管理組合で話し合っておくことは有益なことです。
今度は建材メーカーによる耐火材性能の偽装が発覚、信頼できるのか、不正が見抜けぬ認定機関。
Posted by haru at
08:57
│Comments(0)
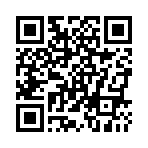
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン







