2007年08月31日
32 マンションは何年持つのか? その7
マンションの寿命を考えるのに鉄筋コンクリートのことを話してきたのには理由があります。
マンションにはたくさんの資材が使用されていますが、マンションの骨組みである鉄筋コンクリートが劣化し、地震に耐えられなくなればマンションは解体するしかありません。
屋上の防水材、外装材、水道管、エレベーター等は多少の費用がかかっても、取り替えることでマンションを維持することが出来ます。
一般的なマンションの鉄筋コンクリートの構造物を造るには、足場を組んだり、コンクリートを型枠に流し込んだりする「鳶、土工」と鉄筋を組む「鉄筋工」それに「型枠大工」の3職種がいれば造ることが出来ます。
一般的なマンションの骨組みは、まだ仕上げをしない工事現場を見ればよくわかりますが単なるコンクリートの箱にバルコニーと廊下のついた単純なものです。
特に「デザイナーズマンション」とか呼ばれているものには複雑な形をしたものもありますが、マンションの寿命から見ると好ましいものではありません。
優秀な責任感のある工事担当者、それを沢山抱えている建設会社、その建設会社を選択できる能力のあるマンションの売主。
そこには、優秀な職人が自然と集まってきます。そして結果的に品質の良い寿命の永いマンションの構造が出来上がります。
もちろん、マンションの寿命は骨組みだけで決まるものではありません。骨組みであるコンクリートの劣化を保護するタイル等の仕上げ材、それを維持する定期的な保守、修繕が必要であることは言うまでもありません。
マンション購入者が購入金額、マンションの見栄えとか使い勝手等だけでなく、上記のことを少しでも意識すれば、寿命の永いマンションを手に入れることが不可能ではありません。
「マンションは何年持つのか?」は、何年持たせたいかという意識を持ったマンション購入者の考え方しだいということになります。
「信頼できるマンションの売主について」は後日タイトルを改めてお話したいと思います。
あるマンションのバルコニーで体長1.5メートルの大蛇が見つかりました。成長すれば10メートルになるそうです。 ペットも色々。
マンションにはたくさんの資材が使用されていますが、マンションの骨組みである鉄筋コンクリートが劣化し、地震に耐えられなくなればマンションは解体するしかありません。
屋上の防水材、外装材、水道管、エレベーター等は多少の費用がかかっても、取り替えることでマンションを維持することが出来ます。
一般的なマンションの鉄筋コンクリートの構造物を造るには、足場を組んだり、コンクリートを型枠に流し込んだりする「鳶、土工」と鉄筋を組む「鉄筋工」それに「型枠大工」の3職種がいれば造ることが出来ます。
一般的なマンションの骨組みは、まだ仕上げをしない工事現場を見ればよくわかりますが単なるコンクリートの箱にバルコニーと廊下のついた単純なものです。
特に「デザイナーズマンション」とか呼ばれているものには複雑な形をしたものもありますが、マンションの寿命から見ると好ましいものではありません。
優秀な責任感のある工事担当者、それを沢山抱えている建設会社、その建設会社を選択できる能力のあるマンションの売主。
そこには、優秀な職人が自然と集まってきます。そして結果的に品質の良い寿命の永いマンションの構造が出来上がります。
もちろん、マンションの寿命は骨組みだけで決まるものではありません。骨組みであるコンクリートの劣化を保護するタイル等の仕上げ材、それを維持する定期的な保守、修繕が必要であることは言うまでもありません。
マンション購入者が購入金額、マンションの見栄えとか使い勝手等だけでなく、上記のことを少しでも意識すれば、寿命の永いマンションを手に入れることが不可能ではありません。
「マンションは何年持つのか?」は、何年持たせたいかという意識を持ったマンション購入者の考え方しだいということになります。
「信頼できるマンションの売主について」は後日タイトルを改めてお話したいと思います。
あるマンションのバルコニーで体長1.5メートルの大蛇が見つかりました。成長すれば10メートルになるそうです。 ペットも色々。
Posted by haru at
08:36
│Comments(0)
2007年08月30日
31 マンションは何年持つのか? その6
これまで、このブログを見られた方はなんとなくお分かりだと思いますが、
マンションの骨組みの寿命は建設された時点でほぼ決まってきます。それも個々のマンションによって違うということです。生まれつき骨粗鬆症のマンションであるかどうかは誰もその事実は確認していません。
売主から「このマンションの寿命は何年です」と提示されることはありません。せいぜい新築から10年間はマンションの骨組みと雨水の浸入の防止について保証する程度です。
又、マンション購入者も購入する住戸内だけを見て、クロスの張り方が悪いとか床に傷があるとかを確認するだけで、基本的なマンションの骨組みを確認することはありません。
マンションが一つの建物にいくつもの所有権(区分所有権といいます)が与えられている結果として、
マンションの売主もマンション購入者も共有部分であるマンションの骨組みに関しては確認する仕組みがないということです。
定期借地権を利用して郊外にショッピングセンターが作られていますが、10年ほど持てばいい建物を依頼するオーナーがいるようです。
しかし、建築基準法を遵守すれば、どのように造っても最低でも20年~30年は持つ建物にならざるを得ません。
今の基準で、きちんと造られたマンションの構造は90年は大丈夫だといわれています。
大正末期に造られた鉄筋コンクリートの建物がまだ現存していることからも想像できると思います。
これまで建て替えされたマンションの平均的な寿命は37年といわれています。高度成長期に質の悪いマンションが建てられたのも事実ですが、居住面積が少ないとか、設備等が時代遅れになったとかの理由によるものが多いようです。
マンション購入者が自分のマンションの骨組みの寿命は何年ぐらいあるのか、費用を掛ければ確認する方法はいくらでもあります。
きちんと造られた新築マンションであれば、その骨組みはマンション購入者の平均余命よりは永いということは言えそうです。
このタイトル、もう少し続きます。
久しぶりの雨です。これから少し涼しくなるのかな?
Posted by haru at
08:55
│Comments(0)
2007年08月29日
30 マンションは何年持つのか? その5
マンションの主要な骨組みの一つであるコンクリートの話です。
まだ固まらないコンクリートを型枠に流し込むことを「コンクリートを打ち込む」といいます。
固まったコンクリートから型枠を取り外したままの仕上げのことを「コンクリート打っ放し仕上げ」といいます。
タイル仕上げや塗装仕上げ等をしない分だけ安く出来ると思われるかもしれませんが、きちんとしたした「コンクリート打っ放し仕上げ」を造る為には意外と費用がかかります。
なんといっても良質なコンクリートであることの証明でもあるのです。
まず、使用するセメント、砂、砂利が均質でなければ均一な色むらのない、きれいな仕上げにはなりません。
又、十分に突き固められていなければ、色むらや、仕上げ面に砂利が見えたり、コンクリートの打ち継ぎの線が見えたりして、仕上げ面が見苦しいものとなります。
きちんとコンクリートが固まるまで養生しなければ、仕上げを傷つけることにもなります。
他の仕上げをしない分だけ、型枠の精度が要求されます。
仕上げをしない分だけコンクリートを2~3センチメートル厚くしていますので、中に入る鉄筋の保護にもなり、他の仕上げに比べて建物の構造体の寿命を延ばすことにもなります。
「コンクリート打っ放し仕上げ」は無機質な独特な風合いとなり、昔から好んで使用する有名な建築家もあるようです。
土木工事で使用されるコンクリートにはほとんど仕上げが施されない「コンクリート打っ放し仕上げ」となっており、きちんと造られたものは、その強度や耐久性が確認されています。建築工事とは違う管理がなされており、コンクリートの品質については建築工事でも参考にすべきものと思います。
マンションで使用された「コンクリート打っ放し仕上げ」は経年変化により汚れが目立つようになりますので、一定の時期には、そのままで維持するよりも塗装等で仕上げを施すのが妥当かと思われます。
きちんと造られた「コンクリート打っ放し仕上げ」のマンションは他の仕上げをしたものより高品質の構造体である一つの目安になると思います。
このブログもいつの間にか今日で30回となりました。コメントをいただければ有難いのですが。
まだ固まらないコンクリートを型枠に流し込むことを「コンクリートを打ち込む」といいます。
固まったコンクリートから型枠を取り外したままの仕上げのことを「コンクリート打っ放し仕上げ」といいます。
タイル仕上げや塗装仕上げ等をしない分だけ安く出来ると思われるかもしれませんが、きちんとしたした「コンクリート打っ放し仕上げ」を造る為には意外と費用がかかります。
なんといっても良質なコンクリートであることの証明でもあるのです。
まず、使用するセメント、砂、砂利が均質でなければ均一な色むらのない、きれいな仕上げにはなりません。
又、十分に突き固められていなければ、色むらや、仕上げ面に砂利が見えたり、コンクリートの打ち継ぎの線が見えたりして、仕上げ面が見苦しいものとなります。
きちんとコンクリートが固まるまで養生しなければ、仕上げを傷つけることにもなります。
他の仕上げをしない分だけ、型枠の精度が要求されます。
仕上げをしない分だけコンクリートを2~3センチメートル厚くしていますので、中に入る鉄筋の保護にもなり、他の仕上げに比べて建物の構造体の寿命を延ばすことにもなります。
「コンクリート打っ放し仕上げ」は無機質な独特な風合いとなり、昔から好んで使用する有名な建築家もあるようです。
土木工事で使用されるコンクリートにはほとんど仕上げが施されない「コンクリート打っ放し仕上げ」となっており、きちんと造られたものは、その強度や耐久性が確認されています。建築工事とは違う管理がなされており、コンクリートの品質については建築工事でも参考にすべきものと思います。
マンションで使用された「コンクリート打っ放し仕上げ」は経年変化により汚れが目立つようになりますので、一定の時期には、そのままで維持するよりも塗装等で仕上げを施すのが妥当かと思われます。
きちんと造られた「コンクリート打っ放し仕上げ」のマンションは他の仕上げをしたものより高品質の構造体である一つの目安になると思います。
このブログもいつの間にか今日で30回となりました。コメントをいただければ有難いのですが。
Posted by haru at
08:43
│Comments(4)
2007年08月28日
29 マンションは何年持つのか? その4
今日の話は、マンション購入者に「いまさら言われても」という話であるが、マンションの基本的な品質、寿命に関するものです。
マンションの構造の基本を占めるコンクリートは、生コンクリート工場で造られ、コンクリート運搬車(生コンクリート車)で工事現場まで運ばれ、コンクリートポンプ車(コンクリートを圧送する機械)で目的の場所までコンクリートを運び、型枠の中に流し込まれる。一定期間の養生期間を経て型枠が解体されコンクリート構造物が出来上がる。
「生コンクリート」とはまだコンクリートが固まっていない状態のことです。
コンクリートが出来上がる各過程での品質に影響する問題点。
1) コンクリートの主要材料の砂、砂利に未洗浄の海砂が使用されていないか。塩分が鉄筋をさびさせる。
特に、昭和45年以降、高度成長期に良質な山砂、川砂が不足したため多くの海砂が使用され始めた。山陽新幹線の架橋に使われたコンクリートにその影響が現れていた。
2) コンクリートを安く購入する為、JIS認定工場以外の生コンを使用していないか。
3) 工事現場で生コンクリートの1部を抜き取り、強度試験をおこなうことになっている。
公的試験場で試験をするがその結果が出るのは、抜き取りした後1ヵ月後である。そのときには建物は2~3階上が出来上がっている。
試験結果が強度不足で建物を解体した例はほとんど聞かない(関東で銀行の建物を完成後コンクリートの強度不足が発覚し解体した事例はあるが)
この試験が形式的になされていることが良くわかる。
4) コンクリートを型枠に流しやすくする為に水を加えていないか。
昭和40年代、コンクリートポンプ車が使われ始めた時期にみられるもので、ポンプの能力不足で硬いコンクリートは圧送しにくかった。「シャブコン」と呼ばれ、コンクリートの強度不足となる。
5) 型枠解体後、十分コンクリートが詰まっていない箇所の処理が適正にされているか。
仕上げをすれば、欠陥が発覚するまで誰もわからない。
では、マンション購入者はどうすればいいか、明日に続きます。
新しい安倍内閣が決まりました。この内閣の寿命は?
マンションの構造の基本を占めるコンクリートは、生コンクリート工場で造られ、コンクリート運搬車(生コンクリート車)で工事現場まで運ばれ、コンクリートポンプ車(コンクリートを圧送する機械)で目的の場所までコンクリートを運び、型枠の中に流し込まれる。一定期間の養生期間を経て型枠が解体されコンクリート構造物が出来上がる。
「生コンクリート」とはまだコンクリートが固まっていない状態のことです。
コンクリートが出来上がる各過程での品質に影響する問題点。
1) コンクリートの主要材料の砂、砂利に未洗浄の海砂が使用されていないか。塩分が鉄筋をさびさせる。
特に、昭和45年以降、高度成長期に良質な山砂、川砂が不足したため多くの海砂が使用され始めた。山陽新幹線の架橋に使われたコンクリートにその影響が現れていた。
2) コンクリートを安く購入する為、JIS認定工場以外の生コンを使用していないか。
3) 工事現場で生コンクリートの1部を抜き取り、強度試験をおこなうことになっている。
公的試験場で試験をするがその結果が出るのは、抜き取りした後1ヵ月後である。そのときには建物は2~3階上が出来上がっている。
試験結果が強度不足で建物を解体した例はほとんど聞かない(関東で銀行の建物を完成後コンクリートの強度不足が発覚し解体した事例はあるが)
この試験が形式的になされていることが良くわかる。
4) コンクリートを型枠に流しやすくする為に水を加えていないか。
昭和40年代、コンクリートポンプ車が使われ始めた時期にみられるもので、ポンプの能力不足で硬いコンクリートは圧送しにくかった。「シャブコン」と呼ばれ、コンクリートの強度不足となる。
5) 型枠解体後、十分コンクリートが詰まっていない箇所の処理が適正にされているか。
仕上げをすれば、欠陥が発覚するまで誰もわからない。
では、マンション購入者はどうすればいいか、明日に続きます。
新しい安倍内閣が決まりました。この内閣の寿命は?
Posted by haru at
08:31
│Comments(0)
2007年08月27日
28 マンションは何年持つのか? その3
マンションは何百種類もの部材を使用して造られています。
材料ごとに寿命が違います。
ほとんどのマンションが鉄筋コンクリート造といわれる建築構造で出来ています。棒状の鉄筋とコンクリートを組み合わせたものです。
鉄筋コンクリート構造は「RC造」と呼ばれており、「鉄筋で補強されたコンクリート」という意味です。
建物の基本的な寿命はマンションの骨組みである「RC造」を堅固に造ることで決まります。
堅固に造る条件は次のような項目です。
1) 構造計算に基づき、適量で、適正な鉄筋が配置されていること。
2年前の耐震強度偽装事件は論外です。
2) コンクリートに混ぜる水の量を減らして緻密なコンクリートを使用すること。
3) コンクリートが固まるまで、型枠が頑丈に出来ており、鉄筋との隙間が十分に確保されていること。
型枠とは、コンクリートを形作る為の鋳型の役割をするものです。
4) やわらかいコンクリートを型枠に流し込むときに十分つき固めること。
有名な建築家の「安藤忠雄」はコンクリートを型枠に流し込むときに竹の棒を自ら持ち、職人と一緒にコンクリートを突いていたそうです。今もしているかどうかは知りません。
5) コンクリートが固まるまで、養生期間を一定以上取ること。
工事期間を十分確保されていない場合は要注意です。特に3月に完成予定のマンションは無理な工期になる可能性があります。
これらの管理は工事業者の能力と良心で決まります。それも基本的には工事現場で直接指揮を執る工事担当者に任されています。
つまり、マンションの骨組みが堅固に造られているかどうかは、工事担当者の能力による部分が大半を占めることになります。
もちろん、工事担当者以外による工程ごとの検査が実施されていますが、形式的な検査と考えたほうが良いかと思います。
このタイトルはまだ続きます。
体調不良で5日間ほど入院をしていました。マンションの診断も大切ですが、自分の体の診断を忘れていました。
材料ごとに寿命が違います。
ほとんどのマンションが鉄筋コンクリート造といわれる建築構造で出来ています。棒状の鉄筋とコンクリートを組み合わせたものです。
鉄筋コンクリート構造は「RC造」と呼ばれており、「鉄筋で補強されたコンクリート」という意味です。
建物の基本的な寿命はマンションの骨組みである「RC造」を堅固に造ることで決まります。
堅固に造る条件は次のような項目です。
1) 構造計算に基づき、適量で、適正な鉄筋が配置されていること。
2年前の耐震強度偽装事件は論外です。
2) コンクリートに混ぜる水の量を減らして緻密なコンクリートを使用すること。
3) コンクリートが固まるまで、型枠が頑丈に出来ており、鉄筋との隙間が十分に確保されていること。
型枠とは、コンクリートを形作る為の鋳型の役割をするものです。
4) やわらかいコンクリートを型枠に流し込むときに十分つき固めること。
有名な建築家の「安藤忠雄」はコンクリートを型枠に流し込むときに竹の棒を自ら持ち、職人と一緒にコンクリートを突いていたそうです。今もしているかどうかは知りません。
5) コンクリートが固まるまで、養生期間を一定以上取ること。
工事期間を十分確保されていない場合は要注意です。特に3月に完成予定のマンションは無理な工期になる可能性があります。
これらの管理は工事業者の能力と良心で決まります。それも基本的には工事現場で直接指揮を執る工事担当者に任されています。
つまり、マンションの骨組みが堅固に造られているかどうかは、工事担当者の能力による部分が大半を占めることになります。
もちろん、工事担当者以外による工程ごとの検査が実施されていますが、形式的な検査と考えたほうが良いかと思います。
このタイトルはまだ続きます。
体調不良で5日間ほど入院をしていました。マンションの診断も大切ですが、自分の体の診断を忘れていました。
Posted by haru at
07:18
│Comments(2)
2007年08月21日
27 マンションは何年持つのか? その2
マンションの寿命は、単に建物の老朽化、改修費用より建替えたほうが良いという費用対効果だけでなく、社会的ニーズや経済情勢などの要因も絡み合ってくる。
昭和30年代に建てられたマンションで、築10数年で建替えの話が持ち上がった。
もちろん、建物に不具合があるわけでもなく、傷んでもう住めないというわけではなかった。
建替えの理由は「平均的な居住面積が15坪で家族や家具が増えて窮屈になった。」である。
立地の良い場所でもあり、調べてみると、敷地に余裕があり、建て替えれば今の住戸の3倍くらいの戸数の住戸がつくれることがわかった。現住民は建替えの費用負担なしで最新の設備機能を備え、しかも広い住戸を手に入れることが出来る。
それでも、全入居者の最終合意を得て、建て替えが実行されるまでには何年もかかっている。
現在建てられているマンションは、敷地の有効面積を最大限利用しており、建替えても今以上の面積を増やし、戸数を増やすことはほとんど不可能である。
むしろ、規制が強化され、現状面積も確保できないマンションもあるくらいである。
新しい法律を作り、住民の多数決で建て替えが容易に出来るようになったが、なかなか、現実的ではない。
物理的に寿命の来たマンションはいくら補修を繰り返しても限度があるので、人がすまなくなれば解体の運命を待つしかない。
これから、現実の問題として必要とされるにのは、実際に販売されているマンションを100年以上耐えうるマンションにすることである。
今でも、技術的には可能である。要はマンション購入者のニーズがどこにあるかである。
沖縄で飛行機が着陸直後、炎上した。間一髪助かった人は、又、飛行機に乗るのだろうか。
昭和30年代に建てられたマンションで、築10数年で建替えの話が持ち上がった。
もちろん、建物に不具合があるわけでもなく、傷んでもう住めないというわけではなかった。
建替えの理由は「平均的な居住面積が15坪で家族や家具が増えて窮屈になった。」である。
立地の良い場所でもあり、調べてみると、敷地に余裕があり、建て替えれば今の住戸の3倍くらいの戸数の住戸がつくれることがわかった。現住民は建替えの費用負担なしで最新の設備機能を備え、しかも広い住戸を手に入れることが出来る。
それでも、全入居者の最終合意を得て、建て替えが実行されるまでには何年もかかっている。
現在建てられているマンションは、敷地の有効面積を最大限利用しており、建替えても今以上の面積を増やし、戸数を増やすことはほとんど不可能である。
むしろ、規制が強化され、現状面積も確保できないマンションもあるくらいである。
新しい法律を作り、住民の多数決で建て替えが容易に出来るようになったが、なかなか、現実的ではない。
物理的に寿命の来たマンションはいくら補修を繰り返しても限度があるので、人がすまなくなれば解体の運命を待つしかない。
これから、現実の問題として必要とされるにのは、実際に販売されているマンションを100年以上耐えうるマンションにすることである。
今でも、技術的には可能である。要はマンション購入者のニーズがどこにあるかである。
沖縄で飛行機が着陸直後、炎上した。間一髪助かった人は、又、飛行機に乗るのだろうか。
Posted by haru at
07:14
│Comments(0)
2007年08月20日
26 マンションは何年持つのか? その1
一般的なマンションは、何年ぐらい堅牢さを保ち続けるものだろうか。
ほとんどのマンションの骨組みはコンクリートと鉄筋を組み合わせたものでできています。
コンクリートは圧縮に強く、鉄筋は引っ張りに強い性質を利用したのです。
又、コンクリートは水とセメントと砂と砂利を混ぜ合わせたものです。材料と調合の管理さえきちんとすれば、誰でも造れる単純なものです。
昭和30年代までは現場で材料を練り合わせてコンクリートを作っていました。
今までは、コンクリート構造物の耐用年数は50年から60年といわれてきました。
税務上の耐用年数が決められていますが、これは当てになりません。
マンション毎に劣化状態に違いがあり、どの段階で寿命が尽きたという物理的な基準を示すのは難しいといわれています。
最近のコンクリートは高強度のもので耐用年数の長い物が造られるようになりました。
理論的には、半永久的に数百年持つコンクリート構造物を作ることは可能です。費用対効果でまだ実現されていないだけです。
補修技術の進歩でマンションの耐用年数をのばすことが可能になっています。
住む側から言えることは、コンクリートの中の鉄筋が錆び始め、コンクリートが剥離し、漏水が始まり、安心して住めなくなる。補修しても「費用対効果」から考えて限界に来たときでしょう。
しかし、コンクリートの寿命より、今までは別の理由から建物の寿命が決まってきました。
この続きは又、明日です。
ほとんどのマンションの骨組みはコンクリートと鉄筋を組み合わせたものでできています。
コンクリートは圧縮に強く、鉄筋は引っ張りに強い性質を利用したのです。
又、コンクリートは水とセメントと砂と砂利を混ぜ合わせたものです。材料と調合の管理さえきちんとすれば、誰でも造れる単純なものです。
昭和30年代までは現場で材料を練り合わせてコンクリートを作っていました。
今までは、コンクリート構造物の耐用年数は50年から60年といわれてきました。
税務上の耐用年数が決められていますが、これは当てになりません。
マンション毎に劣化状態に違いがあり、どの段階で寿命が尽きたという物理的な基準を示すのは難しいといわれています。
最近のコンクリートは高強度のもので耐用年数の長い物が造られるようになりました。
理論的には、半永久的に数百年持つコンクリート構造物を作ることは可能です。費用対効果でまだ実現されていないだけです。
補修技術の進歩でマンションの耐用年数をのばすことが可能になっています。
住む側から言えることは、コンクリートの中の鉄筋が錆び始め、コンクリートが剥離し、漏水が始まり、安心して住めなくなる。補修しても「費用対効果」から考えて限界に来たときでしょう。
しかし、コンクリートの寿命より、今までは別の理由から建物の寿命が決まってきました。
この続きは又、明日です。
Posted by haru at
08:02
│Comments(0)
2007年08月19日
25 超高層マンション、住みやすい? その5
超高層マンション(タワーマンション)の良さは、マンション販売業者の宣伝文句では同じような表現が多いようです。
立地の良さ、土地の高度利用による低価格、高層階からの眺望の良さ、充実した共用施設、最新の設備や地震に強い構造、多様なライフスタイルに対応した多種多様な間取り等々である。
夢のような住まいの提供です。
それに水をさす気はありません。タワーマンション購入者が、私が昨日まで4日間にわたって指摘した問題点を理解しようが、無視しようが「購入者の自由だ~」。
売主も売主から依頼された工事業者も建物の所有権がマンション購入者に移った後は、一定期間のアフターサービス、法的な瑕疵担保責任等を除けば建物の維持管理の責任はない。
未解決の内在した問題を抱えたタワーマンションにおける管理組合の責任は重い。多種多様な居住者を抱えて、合意形成の困難さは一般のマンションの比ではない。
タワーマンションにおける管理組合の運営方法についてはあらためて考えてみたいと思います。
タワーマンションもいつの日か、建替えの時期が必ず来る。
まだ日本では超高層ビルを解体した事例はないに等しい。
確かに、日本の総合建設業者の建物を造る技術はすばらしい。
しかし、超高層ビルの解体技術の検討はどこまでなされているのだろうか。アメリカのように発破での解体はまず無理だろう。
規模の大きな建設物の解体は、たとえば公共施設ともいえる原子力発電所、各所に残るお役ごめんのごみ焼却場等でさえ思うように出来ない。
個人資産(もちろん、建物の大部分が購入者の共有だが)であるタワーマンションが、いづれ誰も住まなくなり、都心に巨大な墓石として放置されないことを祈るばかりである。
このブログも、あっという間に一ヶ月たちました。これからも、独り言をつぶやき続けたいと思います。
立地の良さ、土地の高度利用による低価格、高層階からの眺望の良さ、充実した共用施設、最新の設備や地震に強い構造、多様なライフスタイルに対応した多種多様な間取り等々である。
夢のような住まいの提供です。
それに水をさす気はありません。タワーマンション購入者が、私が昨日まで4日間にわたって指摘した問題点を理解しようが、無視しようが「購入者の自由だ~」。
売主も売主から依頼された工事業者も建物の所有権がマンション購入者に移った後は、一定期間のアフターサービス、法的な瑕疵担保責任等を除けば建物の維持管理の責任はない。
未解決の内在した問題を抱えたタワーマンションにおける管理組合の責任は重い。多種多様な居住者を抱えて、合意形成の困難さは一般のマンションの比ではない。
タワーマンションにおける管理組合の運営方法についてはあらためて考えてみたいと思います。
タワーマンションもいつの日か、建替えの時期が必ず来る。
まだ日本では超高層ビルを解体した事例はないに等しい。
確かに、日本の総合建設業者の建物を造る技術はすばらしい。
しかし、超高層ビルの解体技術の検討はどこまでなされているのだろうか。アメリカのように発破での解体はまず無理だろう。
規模の大きな建設物の解体は、たとえば公共施設ともいえる原子力発電所、各所に残るお役ごめんのごみ焼却場等でさえ思うように出来ない。
個人資産(もちろん、建物の大部分が購入者の共有だが)であるタワーマンションが、いづれ誰も住まなくなり、都心に巨大な墓石として放置されないことを祈るばかりである。
このブログも、あっという間に一ヶ月たちました。これからも、独り言をつぶやき続けたいと思います。
Posted by haru at
09:00
│Comments(0)
2007年08月18日
24 超高層マンション、住みやすい? その4
超高層マンション(タワーマンション)の問題点、今日は主に日常生活に関するものです。
7) 高層部の住民の心身への影響が懸念されています。
ストレスの増大、高血圧症の増加、妊娠障害の出現率の増大、子供の発達障害、住民同士のコミュニティー形成の難しさ等です。
8) バルコニーでの風の強さ。30階当たりでは3階より2倍くらいの強風となることもあります。
洗濯物が干せない状況が生まれます。上階部では初めから禁止しているマンションもあります。強風で引き戸さえ開かないこともあります。特に風切りの音に注意です。
9) ゴミ出しが面倒です。最近では各フロアーに集積場所を設けているところもあるようですが。
朝刊の受け取りも、防犯の認識が高いところは新聞配達は1階のメールボックスまでのところもあります。
10) 携帯電話が通じにくい場合がある。最近では配慮されたマンションもあるようです。
11) 上階部では、下階部では聞こえないような色々な音が聞こえてきます。機密性の高いサッシュが使用されていますので閉めている限りはあまり気にならないと思います。
むしろ、建物内部の隣家の音は案外気になるかもしれません。
建物の自重を軽くする為、戸境壁が耐力壁になっていない影響もあるかもしれません。
12) 高層部まで虫は飛んでこないとか、強風があるとか、見栄えが悪いとかで網戸のないマンションもあるようですが、案外、色々な虫が,高いところでも飛んできますので要注意です。
明日でいったん、このタイトルのまとめとします。
むかし、「暑いといったら罰金」とよく言っていました。今なら、いくら罰金を払えばいいのか?
7) 高層部の住民の心身への影響が懸念されています。
ストレスの増大、高血圧症の増加、妊娠障害の出現率の増大、子供の発達障害、住民同士のコミュニティー形成の難しさ等です。
8) バルコニーでの風の強さ。30階当たりでは3階より2倍くらいの強風となることもあります。
洗濯物が干せない状況が生まれます。上階部では初めから禁止しているマンションもあります。強風で引き戸さえ開かないこともあります。特に風切りの音に注意です。
9) ゴミ出しが面倒です。最近では各フロアーに集積場所を設けているところもあるようですが。
朝刊の受け取りも、防犯の認識が高いところは新聞配達は1階のメールボックスまでのところもあります。
10) 携帯電話が通じにくい場合がある。最近では配慮されたマンションもあるようです。
11) 上階部では、下階部では聞こえないような色々な音が聞こえてきます。機密性の高いサッシュが使用されていますので閉めている限りはあまり気にならないと思います。
むしろ、建物内部の隣家の音は案外気になるかもしれません。
建物の自重を軽くする為、戸境壁が耐力壁になっていない影響もあるかもしれません。
12) 高層部まで虫は飛んでこないとか、強風があるとか、見栄えが悪いとかで網戸のないマンションもあるようですが、案外、色々な虫が,高いところでも飛んできますので要注意です。
明日でいったん、このタイトルのまとめとします。
むかし、「暑いといったら罰金」とよく言っていました。今なら、いくら罰金を払えばいいのか?
Posted by haru at
09:41
│Comments(0)
2007年08月17日
23 超高層マンション、住みやすい? その3
超高層マンション(タワーマンション)の問題点、今日も続けます。
6) タワーマンションも一般のマンションと同様に10年~15年毎に大規模な修繕をしなければなりません。特に高層部は日差しが強く、強風にさらされる為、建物の傷みが激しいことが予想され、修繕回数を増やすことも必要です。
又、共用施設が充実すればするほど、その修繕費用の負担が増加しますし、機械式駐車場やエレベーターも一般のマンションに比べて特殊なものが使用されています。
タワーマンションの維持管理費用には一般のマンションとは違い莫大な費用がかかります。
しかも、修繕の実績がまだ少ないため、費用の総額がどの程度になるかは正確に把握されていないのが実態です。
タワーマンションを建てるときは、本体に取り付けたクレーンを利用し、外壁等も工場で製作されたものを取り付ける方法をとっています。
完成した後は、クレーンは利用できませんし、高すぎて外部足場を組むこともできませんので、ゴンドラを使用して外壁の修繕をするしかありません。
建物の形状によっては、特別なゴンドラを作らなければならないこともあり、さらに費用がかさみます。
計画的に修繕をするためにマンション購入者で毎月積み立てている修繕積立金が意外に低く抑えられているのは、マンション売主の「販売促進のため」だけです。
タワーマンションの修繕実績が積み重なり、費用の総額の実態把握ができるには、まだまだ時間が必要のようです。
将来の修繕計画の責任を負わないマンション販売業者に納得のできる説明を求めるのは無理なのかもしれません。
このタイトルはまだ明日も続きます。
ヒロシマをテーマにした映画「夕凪の街 桜の国」を見ました。広島は「朝凪の街」でもあります。
6) タワーマンションも一般のマンションと同様に10年~15年毎に大規模な修繕をしなければなりません。特に高層部は日差しが強く、強風にさらされる為、建物の傷みが激しいことが予想され、修繕回数を増やすことも必要です。
又、共用施設が充実すればするほど、その修繕費用の負担が増加しますし、機械式駐車場やエレベーターも一般のマンションに比べて特殊なものが使用されています。
タワーマンションの維持管理費用には一般のマンションとは違い莫大な費用がかかります。
しかも、修繕の実績がまだ少ないため、費用の総額がどの程度になるかは正確に把握されていないのが実態です。
タワーマンションを建てるときは、本体に取り付けたクレーンを利用し、外壁等も工場で製作されたものを取り付ける方法をとっています。
完成した後は、クレーンは利用できませんし、高すぎて外部足場を組むこともできませんので、ゴンドラを使用して外壁の修繕をするしかありません。
建物の形状によっては、特別なゴンドラを作らなければならないこともあり、さらに費用がかさみます。
計画的に修繕をするためにマンション購入者で毎月積み立てている修繕積立金が意外に低く抑えられているのは、マンション売主の「販売促進のため」だけです。
タワーマンションの修繕実績が積み重なり、費用の総額の実態把握ができるには、まだまだ時間が必要のようです。
将来の修繕計画の責任を負わないマンション販売業者に納得のできる説明を求めるのは無理なのかもしれません。
このタイトルはまだ明日も続きます。
ヒロシマをテーマにした映画「夕凪の街 桜の国」を見ました。広島は「朝凪の街」でもあります。
Posted by haru at
07:52
│Comments(0)
2007年08月16日
22 超高層マンション、住みやすい? その2
超高層マンション(最近はタワーマンションと呼ばれています。)の問題点、昨日の続きです。
5) 高さ60メーター以上のタワーマンションは、地震時の安全に対して、通常のマンションより法的に厳しい制限が設けられており、国の構造認定を受けないと建築許可が下りません。
タワーマンションは約30年前から建てられていますが、平成7年の阪神・淡路大震災以降の急速な耐震技術の革新により、最近分譲されているものは「免震構造」、「制震構造」と呼ばれる地震のゆれを建物に伝えない特殊な構造技術が使用されています。
従って、建築年代でタワーマンションの耐震性能はまちまちです。
タワーマンションは、一般のマンションに比べて建物の固有周期が長いとされ、地震のゆれと建物のゆれが共振しあってユラリ、ユラリとしたゆれを増幅するといわれています。
1ヶ月前に発生した「新潟県中越沖地震」の影響で、東京の高層階用エレベーターが緊急停止したのはその影響によるものです。
大地震(震度6強~7)で建物が崩壊しない設計になっていますが、住戸内の家具が転倒し、ゆれがさらに増幅すれば、外壁の仕上げ材が落下する可能性があります。
エレベーターは震度4以上で緊急停止し、点検後でないと運転再開しないので、上下の移動手段は歩くしかありません。
阪神・淡路大震災の時、神戸の27階の事務所に歩いて上がったとき、また、歩いて降りたときのひざの痛さは今でも覚えています。
タワーマンションでは一般のマンション以上に日頃の備えが重要になるといえます。
免震構造、制震構造にしろ、あくまでもシミュレーションに頼るしかなく、実物大の実験による確認をされた物ではありません。
想定の範囲外の問題は「新潟の原発」で経験しているところです。タワーマンションも例外ではありません
このタイトルは明日も続きます。
映画館の前、珍しく長蛇の列でした。涼を求めているようでした。
5) 高さ60メーター以上のタワーマンションは、地震時の安全に対して、通常のマンションより法的に厳しい制限が設けられており、国の構造認定を受けないと建築許可が下りません。
タワーマンションは約30年前から建てられていますが、平成7年の阪神・淡路大震災以降の急速な耐震技術の革新により、最近分譲されているものは「免震構造」、「制震構造」と呼ばれる地震のゆれを建物に伝えない特殊な構造技術が使用されています。
従って、建築年代でタワーマンションの耐震性能はまちまちです。
タワーマンションは、一般のマンションに比べて建物の固有周期が長いとされ、地震のゆれと建物のゆれが共振しあってユラリ、ユラリとしたゆれを増幅するといわれています。
1ヶ月前に発生した「新潟県中越沖地震」の影響で、東京の高層階用エレベーターが緊急停止したのはその影響によるものです。
大地震(震度6強~7)で建物が崩壊しない設計になっていますが、住戸内の家具が転倒し、ゆれがさらに増幅すれば、外壁の仕上げ材が落下する可能性があります。
エレベーターは震度4以上で緊急停止し、点検後でないと運転再開しないので、上下の移動手段は歩くしかありません。
阪神・淡路大震災の時、神戸の27階の事務所に歩いて上がったとき、また、歩いて降りたときのひざの痛さは今でも覚えています。
タワーマンションでは一般のマンション以上に日頃の備えが重要になるといえます。
免震構造、制震構造にしろ、あくまでもシミュレーションに頼るしかなく、実物大の実験による確認をされた物ではありません。
想定の範囲外の問題は「新潟の原発」で経験しているところです。タワーマンションも例外ではありません
このタイトルは明日も続きます。
映画館の前、珍しく長蛇の列でした。涼を求めているようでした。
Posted by haru at
07:54
│Comments(2)
2007年08月15日
21 超高層マンション、住みやすい? その1
超高層マンションを厳密に定義するものはないようですが、一般には高さ60メートル以上、地上20階建て以上の居住用の建物を指しています。
最近では、高さが200メートルを超え、階数が50階を超えるマンションも出現しており、「タワーマンション」と呼ばれています。
都心を中心に、近郊の都市まで次々に建てられており、価格も高い高層部ほど早く売れているようです。
タワーマンションの最大の魅力はなんといっても窓からの眺めの良さです。
又、駅に近い立地の良さ、共用施設(フィットネスルーム、キッズルーム、スカイラウンジ、シアタールーム等)やサービス(コンシェルジュの配置等)の充実、地震を含む防災対策、防犯対策の完備等です。
しかし、タワーマンションには次のような問題点があることを理解しておきましょう。
但し、あまり、先のことを考えたくない方やこだわりのない方は読み流してください。
1) タワーマンションの周りにも同じようなあるいはもっと高層のタワーマンションや超高層ビルが建つ可能性があり、最大のメリットの視界を遮られることもあります。
2) 共用施設の充実は、利用する人にとっては大変便利です。しかし、施設の維持管理費用は充実すればするほどかかります。マンションの購入者は利用する、しないに係らず、共用施設の維持管理費用は負担し続けなければなりません。
3) 防犯対策はどうしても機械設備に頼りすぎになりがちです。しかし、防犯の基本は入居者同士のコミュニケーションの良さにあるといわれています。
1棟に数百戸が入居しているタワーマンションでは顔見知りになることはまれです。又、居住者のライフスタイルも多種多様です。働く時間もまちまちでしょう。一般的なマンションよりもっと、コミュニティが希薄になるのは覚悟しておく必要があります。
4) 防災対策は充実しているように見えますが、特に震災時での緊急避難用のヘリポートは役に立ちません。都会ではヘリポートの数に比べてヘリコプターの数が足りません。又、警備会社の迅速な対応はほとんど不可能といわれています。
災害を想定した入居者による避難訓練は一般のマンションに比べて実施されにくい環境です。緊急時の対応はもっと検討する必要がありそうです。
このタイトルは明日に続きます。
今日も気温35度を越える猛暑が続きそうです。ふ~
最近では、高さが200メートルを超え、階数が50階を超えるマンションも出現しており、「タワーマンション」と呼ばれています。
都心を中心に、近郊の都市まで次々に建てられており、価格も高い高層部ほど早く売れているようです。
タワーマンションの最大の魅力はなんといっても窓からの眺めの良さです。
又、駅に近い立地の良さ、共用施設(フィットネスルーム、キッズルーム、スカイラウンジ、シアタールーム等)やサービス(コンシェルジュの配置等)の充実、地震を含む防災対策、防犯対策の完備等です。
しかし、タワーマンションには次のような問題点があることを理解しておきましょう。
但し、あまり、先のことを考えたくない方やこだわりのない方は読み流してください。
1) タワーマンションの周りにも同じようなあるいはもっと高層のタワーマンションや超高層ビルが建つ可能性があり、最大のメリットの視界を遮られることもあります。
2) 共用施設の充実は、利用する人にとっては大変便利です。しかし、施設の維持管理費用は充実すればするほどかかります。マンションの購入者は利用する、しないに係らず、共用施設の維持管理費用は負担し続けなければなりません。
3) 防犯対策はどうしても機械設備に頼りすぎになりがちです。しかし、防犯の基本は入居者同士のコミュニケーションの良さにあるといわれています。
1棟に数百戸が入居しているタワーマンションでは顔見知りになることはまれです。又、居住者のライフスタイルも多種多様です。働く時間もまちまちでしょう。一般的なマンションよりもっと、コミュニティが希薄になるのは覚悟しておく必要があります。
4) 防災対策は充実しているように見えますが、特に震災時での緊急避難用のヘリポートは役に立ちません。都会ではヘリポートの数に比べてヘリコプターの数が足りません。又、警備会社の迅速な対応はほとんど不可能といわれています。
災害を想定した入居者による避難訓練は一般のマンションに比べて実施されにくい環境です。緊急時の対応はもっと検討する必要がありそうです。
このタイトルは明日に続きます。
今日も気温35度を越える猛暑が続きそうです。ふ~
Posted by haru at
09:19
│Comments(0)
2007年08月07日
20 「マンション管理士」とはどんな資格?
「マンション管理士」という名前は聞いたことがあるが、何をする人か知らない人は多いようです。
平成13年から施行された「マンション管理の適正化の推進に関する法律」で創設された国家資格です。まだ、生まれて間がないため、なじみの薄い資格です。
法律の文章は面倒な表現がされていますので、わかりやすく言いますと
マンション管理士とは、マンションの管理についての専門的知識に関する試験に合格し、国に登録をし、管理組合や組合員からの相談をうけ、管理組合の立場に立って、管理組合の支援をする人です。
同時に創設された「管理業務主任者」という資格は、管理会社の社員として必要な資格のことです。
マンション管理士は、管理組合の依頼によって管理組合や組合員の活動を支援する者で、管理会社にかわって、あるいは管理組合にかわってマンションの管理をおこなう者ではありません。
マンション管理士の試験は毎年1回行われ、昨年末で6回目が実施されました。合格率7~8%のかなりの難関です。現在、1万4000人の登録者がいます。
しかし、マンション管理士の資格だけで独立して仕事をしている人はごくまれで、他の資格の追加資格として所持して、不動産関係や管理会社に所属している人が多いようです。
これから実務経験を積んだマンション管理士が増え、それぞれのマンションに合ったトラブル解決方法や管理組合の運営方法が示され、現実にマンションで起こっている様々なトラブルが減少することが期待されています。
ここでこっそり、望ましいマンション管理士の選び方を紹介しておきます。
資格を取得しただけではなく、マンション管理に関する実務経験がある。
的確な情報が取得できる他の資格を持つ者とのネットワークを持っている。
自分の考えを押し付けないで、説明が素人にもわかり易い。
管理組合にとって最適な方法が選択できる複数の提案ができる。
このブログは明日から1週間、夏休みです。墓参りをしてきます。
これからも、より具体的なわかり易い情報を皆様にお届けしたいと思います。
平成13年から施行された「マンション管理の適正化の推進に関する法律」で創設された国家資格です。まだ、生まれて間がないため、なじみの薄い資格です。
法律の文章は面倒な表現がされていますので、わかりやすく言いますと
マンション管理士とは、マンションの管理についての専門的知識に関する試験に合格し、国に登録をし、管理組合や組合員からの相談をうけ、管理組合の立場に立って、管理組合の支援をする人です。
同時に創設された「管理業務主任者」という資格は、管理会社の社員として必要な資格のことです。
マンション管理士は、管理組合の依頼によって管理組合や組合員の活動を支援する者で、管理会社にかわって、あるいは管理組合にかわってマンションの管理をおこなう者ではありません。
マンション管理士の試験は毎年1回行われ、昨年末で6回目が実施されました。合格率7~8%のかなりの難関です。現在、1万4000人の登録者がいます。
しかし、マンション管理士の資格だけで独立して仕事をしている人はごくまれで、他の資格の追加資格として所持して、不動産関係や管理会社に所属している人が多いようです。
これから実務経験を積んだマンション管理士が増え、それぞれのマンションに合ったトラブル解決方法や管理組合の運営方法が示され、現実にマンションで起こっている様々なトラブルが減少することが期待されています。
ここでこっそり、望ましいマンション管理士の選び方を紹介しておきます。
資格を取得しただけではなく、マンション管理に関する実務経験がある。
的確な情報が取得できる他の資格を持つ者とのネットワークを持っている。
自分の考えを押し付けないで、説明が素人にもわかり易い。
管理組合にとって最適な方法が選択できる複数の提案ができる。
このブログは明日から1週間、夏休みです。墓参りをしてきます。
これからも、より具体的なわかり易い情報を皆様にお届けしたいと思います。
Posted by haru at
09:01
│Comments(0)
2007年08月06日
19 マンションの居住者、全部で何人?
貴方のマンションに何人住んでいるか知っていますか?
日本の人口は、1億2705万3471人(平成19年3月末)と国から、先日発表がありました。
不思議なことに、自分の住むマンションの人口は何人いるのか、ほとんど知りません。
大規模な団地では、何千人もの人口になるマンションも存在します。
マンションのルールでは、誰が組合員で、同居人は何人いるのか、あるいは誰に部屋を貸しているのか、貸している場合は本人はどこに住んでいるのか等を管理組合に届けることになっていると思います。
しかし、マンションの持ち主つまり組合員が替わらなければ、同居人の変動までは届けられていない為、現時点での、住民の数が把握されていないのが実態と思われます。
日常の生活においては、どの住戸に何人住んでいようが、ほとんど関係ありません。
何号室に誰が住んでいるかは、玄関ロビーに掲示されていますし、各戸のメールボックスにも表示されていますので、別に不自由はありません。
最近では、特に「個人情報保護法」を理由に名簿の提出に敏感な人も増えています。
しかし、管理組合における居住者名簿は法規制を受けているわけではありません。居住者の自主性を尊重する管理組合としては、居住者のプライバシーを守る為、お互いに話し合い、どのようにして居住者名簿を管理しておくかを決めておくことが大切です。
マンションは共同生活をしているわけですから、ガス漏れや火災等の万一の事故に備えて、正確な居住者名簿(緊急連絡先等を含めた)を整備しておきましょう。
62年前の今日(8月6日)、広島に原爆が投下されました。広島の親たちは原爆のことを「ピカドン」と呼んでいました。
日本の人口は、1億2705万3471人(平成19年3月末)と国から、先日発表がありました。
不思議なことに、自分の住むマンションの人口は何人いるのか、ほとんど知りません。
大規模な団地では、何千人もの人口になるマンションも存在します。
マンションのルールでは、誰が組合員で、同居人は何人いるのか、あるいは誰に部屋を貸しているのか、貸している場合は本人はどこに住んでいるのか等を管理組合に届けることになっていると思います。
しかし、マンションの持ち主つまり組合員が替わらなければ、同居人の変動までは届けられていない為、現時点での、住民の数が把握されていないのが実態と思われます。
日常の生活においては、どの住戸に何人住んでいようが、ほとんど関係ありません。
何号室に誰が住んでいるかは、玄関ロビーに掲示されていますし、各戸のメールボックスにも表示されていますので、別に不自由はありません。
最近では、特に「個人情報保護法」を理由に名簿の提出に敏感な人も増えています。
しかし、管理組合における居住者名簿は法規制を受けているわけではありません。居住者の自主性を尊重する管理組合としては、居住者のプライバシーを守る為、お互いに話し合い、どのようにして居住者名簿を管理しておくかを決めておくことが大切です。
マンションは共同生活をしているわけですから、ガス漏れや火災等の万一の事故に備えて、正確な居住者名簿(緊急連絡先等を含めた)を整備しておきましょう。
62年前の今日(8月6日)、広島に原爆が投下されました。広島の親たちは原爆のことを「ピカドン」と呼んでいました。
Posted by haru at
09:58
│Comments(0)
2007年08月05日
18 マンションの騒音トラブル、どうする?
マンションは、集合住宅である以上、ある程度の生活騒音が生じるのはやむを得ないことです。
ピアノ・テレビ・ステレオ等の音、洗濯機・掃除機・給排水音・冷暖房機・扉の開閉音・会話・子供の叫び声・足音等実に様々な音が、日常的に発生しています。
音の伝わり方には、空気を伝わっていく「空気伝播音」と、床などに直接、衝撃を与えることにより伝わる「固体伝播音」と呼ばれるものがあります。
音の伝わり方は、複雑ですから、音の発生している場所が住戸に接している直上階、隣戸とは限りません。
隣戸との境となる壁には法的に、遮音性能が規制されていますが、上下階の床の遮音の規制はされていません。
最近のマンションは部屋を広く見せる為に、梁のない構造としている建物もありますが、床の振動が伝わりやすい場合があり、トラブルの原因となった例があります。
騒音と感じるかどうかは個人差があり、我慢できない騒音かどうかは判断するのは難しいことです。
居住者が合意できる騒音レベルの限界をみんなで話し合ってわかり易く決めておくことが大切です。
親しくしている人の出す音は氣にならないが、知らない人の出す音は気になるものです。騒音トラブルは、知り合いどうしでは発生しにくいものです。
対立した個人対個人の解決は人間関係をより悪化させるだけで、根本的な解決にはなりません。
法的な解決はどちらかが退去するだけです。
騒音トラブルを防ぐには、日頃からの住民同士お互いのあいさつや、少しばかりの気配りだけでも、少なくすることができます。
夏祭りの季節です。浴衣に花火、風情があります。
ピアノ・テレビ・ステレオ等の音、洗濯機・掃除機・給排水音・冷暖房機・扉の開閉音・会話・子供の叫び声・足音等実に様々な音が、日常的に発生しています。
音の伝わり方には、空気を伝わっていく「空気伝播音」と、床などに直接、衝撃を与えることにより伝わる「固体伝播音」と呼ばれるものがあります。
音の伝わり方は、複雑ですから、音の発生している場所が住戸に接している直上階、隣戸とは限りません。
隣戸との境となる壁には法的に、遮音性能が規制されていますが、上下階の床の遮音の規制はされていません。
最近のマンションは部屋を広く見せる為に、梁のない構造としている建物もありますが、床の振動が伝わりやすい場合があり、トラブルの原因となった例があります。
騒音と感じるかどうかは個人差があり、我慢できない騒音かどうかは判断するのは難しいことです。
居住者が合意できる騒音レベルの限界をみんなで話し合ってわかり易く決めておくことが大切です。
親しくしている人の出す音は氣にならないが、知らない人の出す音は気になるものです。騒音トラブルは、知り合いどうしでは発生しにくいものです。
対立した個人対個人の解決は人間関係をより悪化させるだけで、根本的な解決にはなりません。
法的な解決はどちらかが退去するだけです。
騒音トラブルを防ぐには、日頃からの住民同士お互いのあいさつや、少しばかりの気配りだけでも、少なくすることができます。
夏祭りの季節です。浴衣に花火、風情があります。
Posted by haru at
08:13
│Comments(0)
2007年08月04日
17 管理の良いマンションとは? その2
昨日は、主として、マンションの表面に現れている、管理状態の良さを見てきました。
今日は、主として、マンションの管理組合の運営状態の良さを考えてみます。
7) 管理費や修繕積立金を滞納している居住者がいない。
滞納があっても、3ヶ月以内には回収されていれば、良いでしょう。
総会の資料で確認しましょう。
8) 管理組合の役員の集まりである理事会が、毎月開かれ、話し合いの内容が組合員に報告されている。
9) マンションの将来の修繕計画(25年以上が望ましい)が作成されており、総会の承認を受けている。
修繕計画書が貴方の手元にありますか?
修繕計画に基づいた、修繕積立金が毎月徴収されているのかを確認しましょう。
10) 管理会社から専任の技術者が定期的にマンションの施設を点検し、その結果が組合員に報告されている。
11) 組合員名簿、居住者名簿の最新版が管理組合で保管されている。
自分のマンションにいったい、何人住んでいるのか、一度確認してみましょう。
12) 管理組合の総会に組合員の半数以上が実際に出席している。
委任状の提出だけで、機械的に総会を開催しているマンションが多いようです。
マンションの規模、築年数等の条件によりますが、
年に1度くらいは、組合員が集まり、コミュニケーションを活性化をする工夫が大切です。
以上、昨日から12項目のチェック項目を挙げてみました。
自分のマンションと比べてみましょう。
このブログ、なんとか続いています。コメントをいただければ幸いです。
今日は、主として、マンションの管理組合の運営状態の良さを考えてみます。
7) 管理費や修繕積立金を滞納している居住者がいない。
滞納があっても、3ヶ月以内には回収されていれば、良いでしょう。
総会の資料で確認しましょう。
8) 管理組合の役員の集まりである理事会が、毎月開かれ、話し合いの内容が組合員に報告されている。
9) マンションの将来の修繕計画(25年以上が望ましい)が作成されており、総会の承認を受けている。
修繕計画書が貴方の手元にありますか?
修繕計画に基づいた、修繕積立金が毎月徴収されているのかを確認しましょう。
10) 管理会社から専任の技術者が定期的にマンションの施設を点検し、その結果が組合員に報告されている。
11) 組合員名簿、居住者名簿の最新版が管理組合で保管されている。
自分のマンションにいったい、何人住んでいるのか、一度確認してみましょう。
12) 管理組合の総会に組合員の半数以上が実際に出席している。
委任状の提出だけで、機械的に総会を開催しているマンションが多いようです。
マンションの規模、築年数等の条件によりますが、
年に1度くらいは、組合員が集まり、コミュニケーションを活性化をする工夫が大切です。
以上、昨日から12項目のチェック項目を挙げてみました。
自分のマンションと比べてみましょう。
このブログ、なんとか続いています。コメントをいただければ幸いです。
Posted by haru at
08:59
│Comments(0)
2007年08月03日
16 管理の良いマンションとは?その1
管理がきちんとされているマンションは、築年数が経つほどに価値が上がることもあり、住み心地も良くなるものです。
管理状態の良いマンションを見るポイントは次のようなものがあります。自分の居住するマンションと比べてみましょう。
1) 外壁に目立つひび割れや金物類の錆が少ない。
特に、割れ目から、白いはなたれや赤い錆汁の様な物が、長い間、放置されていると、建物の寿命を縮めることになります。また、金物類の錆を放置しておくと、鉄部の劣化を早めます。
そのマンションが計画的に適切な時期に修繕が行われているかの目安となります。
2) マンションのルールが良く周知されており、良く守られている。
ペットの飼育、バルコ二ーの使用方法、駐車場、駐輪場の整備等、マンション居住者はもちろん外来者にもよく理解されている。
3) 常駐の管理員がいて、住民と挨拶をしている。又、住民同士の挨拶が交わされている。
4) マンションの各出入り口に掲示板が設置されており、各種の広報がタイムリーに掲示されている。
やたらに注意事項の多い掲示は良い管理状態とはいえません。
5) 清掃が行き届いている。
特に、タバコの吸殻が落ちていない、ローカに面した各住戸の窓周り(格子、窓台、窓ガラス等)が清掃されている、植栽の手入れが良い等に注意してみましょう。
6) 防犯カメラが適正に配置されており、夜間の照明が人の顔が判断できる程度の明るさがある。
このタイトルは明日に続きます。
管理状態の良いマンションを見るポイントは次のようなものがあります。自分の居住するマンションと比べてみましょう。
1) 外壁に目立つひび割れや金物類の錆が少ない。
特に、割れ目から、白いはなたれや赤い錆汁の様な物が、長い間、放置されていると、建物の寿命を縮めることになります。また、金物類の錆を放置しておくと、鉄部の劣化を早めます。
そのマンションが計画的に適切な時期に修繕が行われているかの目安となります。
2) マンションのルールが良く周知されており、良く守られている。
ペットの飼育、バルコ二ーの使用方法、駐車場、駐輪場の整備等、マンション居住者はもちろん外来者にもよく理解されている。
3) 常駐の管理員がいて、住民と挨拶をしている。又、住民同士の挨拶が交わされている。
4) マンションの各出入り口に掲示板が設置されており、各種の広報がタイムリーに掲示されている。
やたらに注意事項の多い掲示は良い管理状態とはいえません。
5) 清掃が行き届いている。
特に、タバコの吸殻が落ちていない、ローカに面した各住戸の窓周り(格子、窓台、窓ガラス等)が清掃されている、植栽の手入れが良い等に注意してみましょう。
6) 防犯カメラが適正に配置されており、夜間の照明が人の顔が判断できる程度の明るさがある。
このタイトルは明日に続きます。
Posted by haru at
09:53
│Comments(0)
2007年08月02日
15 マンションで漏水発生、どうする?
マンションでの漏水事故は、屋上、外壁、バルコニー等からの雨水による漏水、壁の結露による漏水等があります。
しかし、1番多いのが建物内部の水周りの配管による漏水事故です。
今日は、その水周りの配管による漏水事故の話です。
この事故の原因は、大きく分けて3つあります。また、原因ごとに対応の仕方が変わってきます。
しかし、マンションの水周りは、2重床となっており、コンクリートと床仕上げ材との間に配管されているので、床材をめくらなければ、漏水場所の特定が困難です。そのために多くの管理組合では、調査費用を負担してくれる保険に加入しています。
1) 明らかに本人の不注意による、風呂、洗濯機、洗面所の水の止め忘れ、又排水管につまり易いものを流した結果による場合。
これは明らかに本人の責任で処理せざるを得ません。
2) マンションの建設時、あるいはリフォーム時にその原因がある場合。
当然、工事業者の責任です。
3) 配管の老朽化が原因の場合
これが、1番多い漏水事故の原因です。建築後15年も経てば、配管の使用材料、配管方法によりますが、老朽化が進み漏水の可能性が多くなります。
下階に漏水が確認されなければ、漏水しているかどうかが、居住者には判りにくいのが漏水事故です。
基本的には、漏水を発生させた住戸の所有者の責任となります。
漏水の原因が特定できない場合は、管理組合が責任を持つこともあります。
いずれにしても、あらかじめ水漏れ事故に備えて、個人賠償も含めて管理組合で損害保険に加入している場合が多いので、どのような条件の保険に加入しているのかを確認しておきましょう。
漏水トラブルで、下階に迷惑を掛け、自己負担で費用負担をしたが、実は保険で対応できた事例があります。
漏水事故が発生したら、すぐに、管理組合を通じて保険会社に連絡をすることです。
昨日から、プロフィールを記載しています。
しかし、1番多いのが建物内部の水周りの配管による漏水事故です。
今日は、その水周りの配管による漏水事故の話です。
この事故の原因は、大きく分けて3つあります。また、原因ごとに対応の仕方が変わってきます。
しかし、マンションの水周りは、2重床となっており、コンクリートと床仕上げ材との間に配管されているので、床材をめくらなければ、漏水場所の特定が困難です。そのために多くの管理組合では、調査費用を負担してくれる保険に加入しています。
1) 明らかに本人の不注意による、風呂、洗濯機、洗面所の水の止め忘れ、又排水管につまり易いものを流した結果による場合。
これは明らかに本人の責任で処理せざるを得ません。
2) マンションの建設時、あるいはリフォーム時にその原因がある場合。
当然、工事業者の責任です。
3) 配管の老朽化が原因の場合
これが、1番多い漏水事故の原因です。建築後15年も経てば、配管の使用材料、配管方法によりますが、老朽化が進み漏水の可能性が多くなります。
下階に漏水が確認されなければ、漏水しているかどうかが、居住者には判りにくいのが漏水事故です。
基本的には、漏水を発生させた住戸の所有者の責任となります。
漏水の原因が特定できない場合は、管理組合が責任を持つこともあります。
いずれにしても、あらかじめ水漏れ事故に備えて、個人賠償も含めて管理組合で損害保険に加入している場合が多いので、どのような条件の保険に加入しているのかを確認しておきましょう。
漏水トラブルで、下階に迷惑を掛け、自己負担で費用負担をしたが、実は保険で対応できた事例があります。
漏水事故が発生したら、すぐに、管理組合を通じて保険会社に連絡をすることです。
昨日から、プロフィールを記載しています。
Posted by haru at
08:39
│Comments(0)
2007年08月01日
14 バルコニーは自由に使用できるか?
バルコニーはべランダとも言いますが、厳密な区分けはしていないようです。ここでは、バルコニーと呼ぶことにします。
バルコニーは住戸部分の外側に張り出した部分で、手摺等で囲まれ、隣戸とは区切られた住戸専用のスぺースのことです。
次の3つのパターンがあります。
1) 隣戸のバルコニーと接しているが、避難通路として造られたもの。そのため、隣戸との境は避難用に比較的薄いボードで簡単に破壊、撤去可能な造りになっています。
2) 隣戸とのバルコニーとは独立しているもの。
3) 斜線制限により階段状にセットバックしている建物に見られる、ルーフバルコニーとかルーフテラスとか呼ばれるもの。下階の屋上と兼ねています。
いづれのバルコニーも建物の構造部分であり、マンション所有者全員で共有している部分(共用部分と呼ばれています)です。
従って、バルコニーの使用方法は、ルール化されており、安全や建物の美観を損ねない範囲でと限定されています。
一般的には、洗濯物干し場、空調機の屋外機置場、ちょっとした植木鉢置場等の使用は容認されています。
禁止されているのは、物置の設置(避難時に動かせない大きさの物)、動物の飼育、サンルームの設置、手摺への布団掛け、アンテナの設置、多量の土砂の搬入等です。
最近は、バルコニーでの喫煙によるトラブルもあるようで、ほたる族は場所を失いつつあります。
ルールはマンションの状況に応じて、居住者の使用権の不当な制限にならないよう、合理的な範囲で決めることが大切であると思います。
今日から8月です。毎月1日は近所の神社に参拝に行きます。
バルコニーは住戸部分の外側に張り出した部分で、手摺等で囲まれ、隣戸とは区切られた住戸専用のスぺースのことです。
次の3つのパターンがあります。
1) 隣戸のバルコニーと接しているが、避難通路として造られたもの。そのため、隣戸との境は避難用に比較的薄いボードで簡単に破壊、撤去可能な造りになっています。
2) 隣戸とのバルコニーとは独立しているもの。
3) 斜線制限により階段状にセットバックしている建物に見られる、ルーフバルコニーとかルーフテラスとか呼ばれるもの。下階の屋上と兼ねています。
いづれのバルコニーも建物の構造部分であり、マンション所有者全員で共有している部分(共用部分と呼ばれています)です。
従って、バルコニーの使用方法は、ルール化されており、安全や建物の美観を損ねない範囲でと限定されています。
一般的には、洗濯物干し場、空調機の屋外機置場、ちょっとした植木鉢置場等の使用は容認されています。
禁止されているのは、物置の設置(避難時に動かせない大きさの物)、動物の飼育、サンルームの設置、手摺への布団掛け、アンテナの設置、多量の土砂の搬入等です。
最近は、バルコニーでの喫煙によるトラブルもあるようで、ほたる族は場所を失いつつあります。
ルールはマンションの状況に応じて、居住者の使用権の不当な制限にならないよう、合理的な範囲で決めることが大切であると思います。
今日から8月です。毎月1日は近所の神社に参拝に行きます。
Posted by haru at
07:39
│Comments(0)
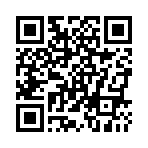
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン







